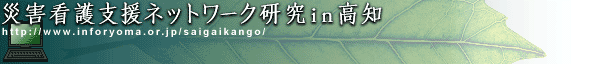■ 研究活動の報告
|
■ 研究活動に関する意見 |
■ TOPページへ戻る |
● 平成19年度 研究活動の報告 ●
![]()
![]()
|
◆◆ 平成19年度の研究成果発表
災害看護活動支援システム構築の構想 | ||||
|
| 1.はじめに |
| 筆者らが行った「災害看護活動における行政システムを補完する横の連携の構築」の分析結果から、発災時の災害支援ナースが独自の判断で活動を行うことの必要性が明らかになった。これには、独自に活動するボランティア要員の活動を調整する機能が必須なので、ここでは、看護職の災害救援活動を効率的に行うためのネットワークの構築構想を提案する。 |
| 2.研究の方法 |
| DMAT(Disaster Medical Assistance Team)管理システム、商用コミュニティーサイト及び筆者らが行った「災害看護活動における行政システムを補完する横の連携の構築」の分析結果を基に、災害看護活動を効率的にサポートするためのシステム構築を検討した。倫理的配慮として、研究参加、学会発表等について関係機関の同意を得た。 |
| 3.システムに必要な機能 |
|
1.災害支援ナース登録データベース機能 日本看護協会平成19年度事業5.6-1に「災害への備え及び災害時支援ネットワークの強化」が挙げられているが、実際に活動に参加する看護職の登録情報を発災時に迅速に読み出し、派遣要請の条件に適合した要員をリストアップできる機能が必要である。 2.派遣要請などの伝達機能 発災時の電話(音声通話)は、不通になることが多く、登録災害支援ナース個々に電話で連絡するのは難しく、効率的とは言いがたい。一方、メールなどのデータ通信は、通信が比較的とりやすく、主に携帯電話のメール機能を用いた派遣要請やその回答のコミュニケーション方法として活用が期待できる。 3.報告機能 災害支援ナースの活動を組織化するためには、従事する看護職の活動内容の報告を分析する必要がある。また、自律的に活動を開始した災害支援ナースの活動状況を把握し、安全な活動を保証するためにも、この機能は重要である。この機能は、前述の伝達機能と同様にメールを中心としたシステムとする。 4.情報照会機能 情報共有を図るため被災状況や支援を必要とする内容などを照会できるようにする。情報元は、行政から提供されたものに加え、都道府県看護協会が集約したもの、また上記3の情報を含むものとする。 5.システムの稼動範囲 本システムは、発災直後から稼動するが、通信回線の不通が予想され、システムの機能が最大限に発揮される時期は、亜急性期以降を想定する。本システムは、都道府県単位で運用し、広域災害を想定し日本看護協会をはじめ他県からアクセスできるようにする。データは、遠隔地にバックアップをとる。 |
| 4.提唱されたシステムの運用例 |
|
1.通常時 県看護協会は、本システムを用いて支援ナースの登録・更新を行う。定期的に本システムの運用講習を加える。 2.発災時 ①発災直後 災害支援ナースに登録しているAさんは、活動が可能であったので、自身の判断で活動を開始した。活動場所について情報を収集しようとしたが、通信手段が確保できず、自身の判断で最寄の救護所で活動を開始した。 ②発災48~72時間後 Aさんは、通信手段が復旧したので、本システムを用いてこれまでの活動と現在の救護所の状況を報告した。 B病院の看護部は、自施設への応援要請を本システムを用いて行った。その際、応募の条件に団体での派遣を希望した。 県看護協会は、上記などから寄せられた派遣依頼を統合し、派遣要請を本システムにアップした。隣接県の看護協会は、これを基に自県内の登録看護職に派遣要請をメールで打診した。 他県から来たCさんは、本システムを用いて地図情報と条件検索から活動場所を探し、活動に加わる旨を登録した。 |
![]()
![]()
| ← 戻る |
|