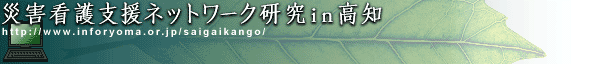■ 研究活動の報告
|
■ 研究活動に関する意見 |
■ TOPページへ戻る |
● 平成22年度 研究活動の報告 目次 ●
| ◆◆ 都道府県看護協会と都道府県との災害看護協力状況 | ||||
|
| 1.はじめに |
| 都道府県看護協会(以下、看護協会)と都道府県(以下、県)の間で、効果・効率的な災害看護活動を保証するために、災害看護協力協定を締結するところが次第に増えている。しかし、明確な統計はなく、どこの県でどのよう災害看護協力協定が締結され、その体制が構築されているのかわからないのが現状である。そこで本研究は、各看護協会と県との間で、どのような災害看護の協力体制が整えられているのか、その状況を調査したので報告する。 |
| 2.研究方法 |
| 全ての看護協会および県に、互いの災害看護協力に関する質問紙を送付し、回答を求めた。本調査は、高知女子大学看護研究倫理審査委員会の承認を得て実施した。 |
| 3.結果と考察 | ||||||||||||||||||
|
看護協会から39件(回収率83.0%)、県から35件(回収率74.5%)の回答があった。 1.どのような災害看護に関する協力をしているのか 看護協会と県の間で災害看護協力協定を締結しているところは、13ヶ所(27.7%)であった。看護協会が防災会議等の委員として参加しているという回答は、看護協会のデータからは21ヶ所(53.8%)、県のデータでは13ヶ所(37.1%)であった。全く協力関係に無いと回答のあったところは6 ヶ所(12.8%)であり、この場合の看護協会と県との意見の一致率は高く、何もしていない場合の認識は互いに明確であった。その他、県国民保護計画や防災計画に指定地方公共機関として登録されていることが協力関係にあると認識しているところもあったが、具体的な活動があるわけではなく、形ばかりの協力関係と伺える。 2.災害看護協力協定の必要性の認識 表1の通り、災害看護協力協定の必要性の認識は、「とても必要である」が県より看護協会が1.5倍多く、「どちらかというと必要である」を加えるとその割合は、看護協会が86.1%、県が67.6%であった。一方、「あまり必要でない」との回答は、看護協会が2.8%であるのに対し、県は11.8%と4倍もあり、必要性に関しては、看護協会と県では大きな認識の差があることがわかった。(p<0.05)
3.災害看護協力協定を締結していない理由 1) 看護協会側の理由 締結の準備や体制が整っていなかったり、県が関わるDMATが組織されているので、県は特に看護協会に期待してはいないのではないかと思っていた。また、県防災会議に参加したり、県国民保護計画や防災計画に指定地方公共機関として登録されていることで、既に関係性は確立されていると考えている協会もあり、過去の具体的な災害看護活動の実態からは、かなり甘い見方であると言わざるを得ない。更に、あまり災害に縁のない地域の看護協会は、それを理由に自ら意識レベルの低いことを認めており、地域の特殊性も含め、看護協会によりかなり認識に温度差があることが伺える。 2) 県側の理由 医師会との協定締結のみで十分と考えていたり、DMATが組織されていること、あるいは救護班や拠点病院を指定していることから、実質的に看護師の確保は担保されていると考えている。しかし、実際の災害現場では、看護職独自の活動も大変意義があることはこれまでの災害にて実証されており、災害における看護職の役割に対し、県の認識の薄さが指摘される。また、県として支援するための財源がないとの回答もあり、現行法の活用を検討していなかったり、看護協会から協定締結の申請がないので考えていないなどの消極的理由も多く回答されていた。 |
| 4.結論 |
| 看護協会と県との災害看護協力は、会議の参加や防災計画等での登録にとどまり、具体的な活動における協力関係は、十分に築かれているとは言えない。 |
|