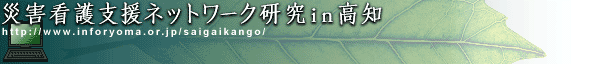■ 研究活動の報告
|
■ 研究活動に関する意見 |
■ TOPページへ戻る |
● 平成23年度 研究活動の報告 目次 ●
| ◆◆ 都道府県看護協会と都道府県との災害看護協力協定締結要因 | ||||
|
| 1.はじめに |
| 都道府県看護協会(以下、看護協会)と都道府県(以下、県)の間で、災害看護協力協定(発災時に県と協力して看護活動を行うことを期待される取り決め)を締結するところが次第に増えている。しかし、全く協定締結に関心の無いところもあり、地域により温度差があるように思われる。そこで本研究は、各看護協会と県が考える協定締結の必要性、およびその程度がどの様な要因に影響されているのか調査し、協定締結への方策を検討したので報告する。 |
| 2.研究方法 |
| 全ての看護協会および県に、互いの災害看護協力に関する質問紙を送付し、回答を求めた(平成21年12月~翌1月)。本調査は、高知女子大学看護研究倫理審査委員会の承認を得て実施した。 |
| 3.結果 |
看護協会から39件(回収率83.0%)、県から35件(回収率74.5%)の回答があった。図1は互いの災害看護協力関係において、どの程度災害看護協力協定を必要と考えているか、-2から+2までのリッカートスケールで測定した結果である。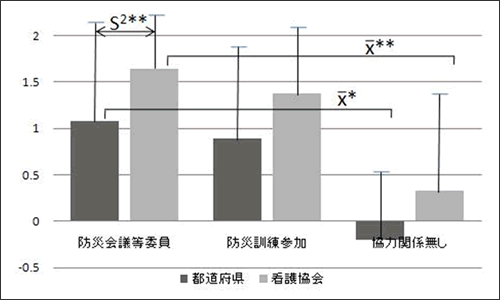 図1 互いの災害看護協力関係における協定の必要性
「防災会議等委員」に関しては、県と看護協会の分散に1%有意水準で差が認められ、県の「防災会議等委員」と「協力関係無し」に5%で、看護協会の「防災会議等委員」と「協力関係無し」に1%有意水準でそれぞれ平均に差が認められた。表1は県および看護協会のデータにおいて、目的変数を「協定の必要性」、説明変数を「防災会議等委員」、「定期的な防災訓練参加」および「協力関係無し」としたときのステップワイズ法による重回帰分析の結果である。県①には説明変数として協定の締結状況「協定締結」を追加した分析である。看護協会の分析においては、「協定締結」は分析過程で削除されたので、これを追加していない分析と同様の結果となった。 表1 協定の必要性に影響する要因
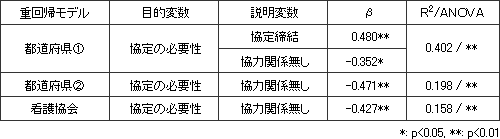 |
| 4.考査 |
| 看護協会に防災会議等の委員を依頼している県は、依頼されている看護協会に比して認識のバラツキが大きく、協定の必要性をかなり認識しているところもあれば、あまり認識していないところもある。よって、防災会議等の委員に看護協会のメンバーを登用している県であっても、必ずしも協定の必要性を十分に感じているわけではない。つまり防災会議における発言を期待していても、発災時に看護職が協働して活動を行うことについては、期待する県とそうでない県があるということである。看護協会に防災会議等の委員を依頼している県は、看護協会と災害に関し全く協力関係にないと答えている県に比して、協定の必要性を認識している。これは看護職が行う救援活動が、一般的な救護班の活動とは異なる意義を持つことが、防災会議における看護協会の発言などを通して、理解されているためではないかと考える。よって、協定締結に向け看護協会は、防災訓練への参加をはじめ、防災会議にも積極的に参画し、救護だけでなく被災者の生活と健康を守る救援活動の重要性について、発言していくべきである。 |
| 5.結論 |
| 協定を締結するために、看護協会として先ずは定期的な防災訓練に参加するなど、県との関係作りを促進し、防災会議等の委員登用を通して、救護に留まらない看護活動をアピールし、協定締結を県に対して働きかけるべきである。 |
|