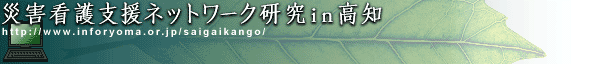■ 研究活動の報告
|
■ 研究活動に関する意見 |
■ TOPページへ戻る |
● 平成24年度 研究活動の報告 目次 ●
| ◆◆ 東日本大震災後の都道府県看護協会と都道府県との災害看護協力状況 | ||||
|
| 1.はじめに |
| 都道府県看護協会(以下、看護協会)と都道府県(以下、県)の間で、効果・効率的な災害看護活動を保証するために、災害看護協力協定を締結するところが次第に増えている。しかし、明確な統計はなく、どのような災害看護協力協定が締結され、その体制が構築されているのかわからない状況であったため、本研究は平成21年に各看護協会と県との間で、どのような災害看護の協力体制が整えられているのか、その状況を調査した。今回は、東日本大震災後に同様の調査を実施したので、比較して結果を報告する。 |
| 2.研究方法 |
| 全ての看護協会および県に、互いの災害看護協力に関する質問紙を送付し、回答を求めた。本調査は、高知県立大学看護研究倫理審査委員会の承認を得て実施した。調査は、平成23年12月から翌年1月まで実施された。 |
| 3.結果と考察 | ||||||||||||||||||
|
看護協会から39件(回収率83.0%)、県から35件(回収率74.5%)の回答があった。 1. どのような災害看護に関する協力をしているのか 看護協会と県の間で災害看護協力協定を締結しているところは、15ヶ所(前回27.7%→今回31.9%)で、前回より2ヶ所増加した。看護協会が防災会議等の委員として参加しているという回答は、看護協会のデータからは24ヶ所(53.8%→61.5%)、県のデータでは12ヶ所(37.1%→34.3%)であった。全く協力関係に無いと回答のあったところは県のみ1ヶ所(12.8%→2.9%)であり、協定には至らないものの、何らかの協力関係の構築が進んでいることが伺える。 2. 災害看護協力協定の必要性の認識 表の通り、災害看護協力協定の必要性の認識は、「とても必要である」が県より看護協会が1.5倍多いことは前回と変わりはないが、「どちらかというと必要である」を加えるとその割合は、看護協会が86.1%→89.5%、県が67.6%→78.1%と変化し、特に県の考える協定の必要性の認識がかなり高くなった。また、「あまり必要でない」との回答は、看護協会が2.8%→0%、県は11.8%→3.1%となり、ポジティブな回答と同様に、両者の災害における認識が高くなったことがわかった。県の自由回答からは、看護協会との協定を検討していると述べているところが複数あり、災害看護協力協定締結に向け、積極的に動き出したと考えられる 表 災害看護協力協定の必要性の認識(震災前後%)
3. 災害看護協力協定を締結していない理由 1)看護協会側の理由 前回の調査と同様に、比較的多くの協会が県の防災関係の委員会に参加していることを理由に、協定を結ばなくても災害時に対応できると考えていた。更に、前回と同様に県からの申し出が無いことも理由として挙げ、消極的な状況が伺えた。過去の災害時における看護活動の重要性からみても、切迫感の無さに疑問を感じると言わざるを得ない。また、これまで災害支援ナースの役割が県に十分理解されていなかったことを理由として挙げている一方、東日本大震災の派遣実績で、災害支援ナースの役割が理解されつつあるとの考えもあった。 2)県側の理由 医師会との協定締結、あるいはDMATの活動を通し、看護職との協働は十分であると考えていることは、前回の調査と同様であった。また、看護協会と同様に、看護協会から協定締結の申請がないので考えていないなどの消極的理由も回答されていた。 |
| 4.結論 |
| 東日本大震災を経験し、災害看護協力の認識は両者とも高くなって来ていることが伺え、県の認識が高まっている今こそ、両者の更に踏み込んだ努力を期待する結果であった。 |
|