本文
【開催報告】地域共生学研究機構シンポジウム「歴史文化を通じた地域づくり・まちづくり」(令和6年12月14日)
高知県立大学では、令和6年度から高知県立大学10年戦略「UoK Vision 2033」をスタートさせました。戦略の一つとして「地域共生社会を支援する実践的な教育・研究」を進めるため、地域を支える様々な立場の人々がつながり合い、地域の課題を共に乗り越え、地域のつながりを再構築するための取り組みである「リ・デザイン プロジェクト」を行っています。
このプロジェクトの一環として、地域共生社会の文化学的側面にスポットを当てたシンポジウム「歴史文化を通じた地域づくり・まちづくり」を、永国寺キャンパスで対面・オンラインのハイブリッド形式で開催しました。
地域共生学研究機構シンポジウム「歴史文化を通じた地域づくり・まちづくり」
第1部は高知県での取り組みについて、3名の登壇者に事例を紹介していただきました。
中内勝氏(高知県文化生活部歴史文化財課 課長)は、中山間地域の民俗芸能支援について、その維持・継承・活用に向けた取り組みを説明しました。特に、担い手不足に悩む地域と外部の支援者をマッチングする担い手支援事業には、県立大の学生も参加していることも紹介されました。
中村茂生氏(NPO法人地域文化計画 理事)はNPOの活動を通じて知った、安芸市で伝承されている赤野獅子舞保存会の活動を紹介しました。コロナ禍で休止していた獅子舞の上演を復活させた保存会の取り組みが、伝統芸能の継承にとどまらず、地域づくりに寄与するのではないかと、聴講者に呼びかけました。
香南市赤岡町で町家の保全活用に取り組む北山めぐみ氏(NPO法人すてきなまち・赤岡プロジェクト 副代表理事)からは、取り壊しの危機にあった同町の旧小松家住宅(通称:赤れんが商家)の修繕から活用に至るまでの取り組みが紹介されました。また歴史的文化遺産の保存・活用に重要な役割を果たす「ヘリテージマネージャー」についても説明されました。
事例紹介の後、聴講者を交えて意見交換が行われたほか、第2部で基調講演を行う西村幸夫氏より、それぞれの取り組みについて、「足元のつながりや、コミュニティなどから少しずつ取り組むことで歴史文化を伝えることにつながると、可能性を感じられた」と感想をいただきました。
第2部では、都市計画や歴史的都市の保全を軸としたまちづくりが専門の西村幸夫氏(國學院大學観光まちづくり学部 学部長)による「歴史文化を活かしたまちづくりのこれまでとこれから」と題した基調講演を行いました。
西村氏は、これまでの歴史文化を活かしたまちづくりを振り返り、歴史文化への認識は時代によって変化してきたが、それを守ろうという動きは時々の開発圧力によって生まれていることを説明されました。しかし今後の人口減少時代において圧力は減っていくために、新しいアプローチとして内発的な物語「ナラティブ」をつくることが重要で、そこに歴史文化を活かす必要性を強調されました。「何気ない都市空間にも、歴史の中で蓄積されたさまざまな物語があります。それをうまく発信し、広く共有できれば、次につながるエネルギーになるのです」と呼びかけました。
さらに、西村氏がこれまで調査した高知市と四万十市中村地区、ご自身がまちづくりに関わる福井県小浜市を例に、まちの読み解き方と歴史文化を活かした具体的な取り組みを説明されました。「歴史や文化を物語の中で地域に位置付けることで、今まで見えなかったような地域の可能性が見えてきます。低成長の時代、これを手掛かりに次のまちづくりの構想を立てることができるのではないか」と、これからのまちづくりの在り方を示唆されました。
続いて質疑応答が行われ、地域再生の成功事例や文化的景観を活用した地域活性化などについて議論が交わされました。
ご来場いただいた方々に心よりお礼申し上げます。
当日の様子
学長挨拶


第1部 事例紹介「高知県での取り組みについて」
「高知県の中山間地域の民俗芸能支援の取組」中内 勝 氏(高知県 文化生活部 歴史文化財課 課長)


「獅子舞地域づくりは可能か?ー赤野獅子舞、コロナ以後の展開ー」中村 茂生 氏(NPO法人地域文化計画 理事)


「歴史文化を通じた地域づくり・まちづくりーすてきなまち・赤岡プロジェクトを中心にー」北山 めぐみ 氏(NPO法人すてきなまち・赤岡プロジェクト 副代表理事)


意見交換会


第2部 基調講演「歴史文化を活かしたまちづくりのこれまでとこれから」
西村 幸夫 氏(國學院大學 観光まちづくり学部 学部長)



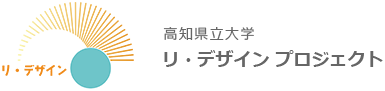

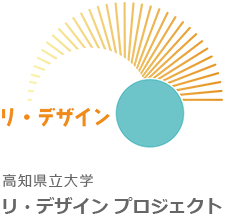
 学校サイトトップ
学校サイトトップ