本文
【開催報告】令和6年度 地域共生学研究機構 講演会 「兵庫県養父市における社会的処方の取組」(2025年2月15日)
2月15日、令和6年度地域共生学研究機構講演会「兵庫県養父市における社会的処方の取組~つながりで誰もが健康になるまちをめざして~」を永国寺キャンパスにて開催しました。行政、NPO法人、高校生、大学生、教職員など対面・オンライン合わせて約60人の参加がありました。
兵庫県養父市は「社会的処方」の考え方を取り入れ、個々が抱える孤独や孤立の問題の解決をめざす事業を積極的に推し進めています。令和6年度に全国の自治体として初めて「社会的処方推進課」を設置し、つながりを通じて誰もが健康になり、住み慣れた地域で互いに支え合い、幸せに暮らせるまちづくりに市全体で取り組んでいます。
本講演会では、養父市健康福祉部社会的処方推進課 課長 余根田一明 氏をお招きし、厚生労働省社会的処方モデル事業を活用した仕組みづくりや同市での取組の具体例についてお話しいただきました。
兵庫県養父市における社会的処方の取組~つながりで誰もが健康になるまちをめざして~
養父市は兵庫県北部の但馬地方に位置し、高齢化率は40%を超えます。面積の84%が山林で、谷あいに集落が点在しており、市全体が過疎地域となっています。
余根田氏は、社会の変化で「つながり」が希薄化し、人々が孤立や生きづらさを感じる状況の中で、「社会とのつながり」を処方し、個々が抱える問題を解決する「社会的処方」という概念をまちづくりに取り入れ、社会との『つながりで誰もが健康になるまちづくり』を目指していることを説明されました。社会的処方の要となるリンクワーカー※について、養父市では、専門職をはじめ市民の皆さんがリンクワーカーとしての役割を担っていただけるようなまちづくりを推進していることを紹介されました。
※リンクワーカー:人のしあわせのために、人や地域・社会資源へのつながりをつくる人
(養父市HPより)
令和4年度には厚生労働省社会的処方モデル事業に採択され、仕組み作りに取り組み、医療とリンクワーカーの連携により個々の社会生活環境を改善(ケア)する社会的処方の仕組みを提案しました。
その具体的な事例として「社会とのつながり処方箋」を紹介。健康面とあわせて孤立など社会生活面に課題を抱える住民に対し、趣味や楽しみのマッチングや、本人の持つ回復力に焦点をあてる関わりなどを通じて、住民の健康への意識の高まりや、前向きな言動がみられるようになったケースが紹介されました。
養父市版リンクワーカーは2層に分かれており、一つは専門職者がそれぞれの専門的な知識をもってつないでいく「ヘルスコネクター」、もう一つは市民が地域の中でつながりをつくる「コミュニティコネクター」です。他にも養父市に暮らす全ての人がリンクワーカーになりえることを紹介されました。社会的処方があまり知られていない中で、関係機関等の協力を得ながらリンクワーカー養成研修等をすすめていった苦労や工夫、手応えをお話しくださいました。
また、地域コミュニティなどの「つなぎ先・つながる先」の見える化と、発掘・開拓の事例を2つ紹介されました。一つ目は、市内で行われているつどいの場の情報を集約した社会的処方ポータルサイト「つながるDAY YABU※1」。二つ目は、個人の小さな想いやアイデアを見えるカタチにする新しい学びの場「KANAUカレッジ※2」です。そのほか、社会的処方に関する取組として、コミュニティナースの活躍や介護支援団体との連携、一般財団法人 医療文化経済グローカル研究所の設立等を挙げられました。
最後に、これまでの取組を通じ、社会的処方をすすめていくためには、医療を起点とした相談支援の拡充、包括的な支援体制の強化と多職種連携の充実、多様な居場所づくりや住民主体の活動の促進、市民意識の醸成が重要であることが示唆されました。また行政としては、組織内での分野横断的に行う取組・事業づくりや、組織の縦割りの壁を低くしていき、業務や支援に対する意識の重なりをつくっていくことが市民の皆さんの幸せにつながっていくのでは、と締めくくられました。
続いて質疑応答が行われ、社会的処方ポータルサイトへの市民の反応や、地域コミュニティの発掘方法、行政における社会的処方の考え方、社会的処方の研究、今後の展開などについて参加者と議論が交わされました。
参加者からは「看護師を目指していて、病院内でどう患者さんと関わっていきたいのか、どんな治療法があるのかについて調べるばかりでした。しかし、社会的処方を知り、あまりイメージのできていなかった保健師の仕事が少し分かったり、患者さんの生きがい作りをどのように行うのかがイメージできたりしたので、参加して良かったと感じました」「医療と生活の分野の壁が低くなるほど、社会とのつながりが身近になるほど、個々人の健康、幸福度に直結すると、改めて感じました」「社会的処方についてあまりよく分かっていなかったが、今回の講演会を通して、誰もが健康に生きていくために社会的処方が重要だと感じました」などの感想をいただきました。
ご来場いただいた方々に心よりお礼申し上げます。
※1「つながるDAY YABU」
https://tsunagaruday-yabu.jp/(外部サイトへ)
※2「KANAUカレッジ」
https://tsunagaruday-yabu.jp/report/1349/(外部サイトへ)
当日の様子
学長挨拶

講 演 余根田 一明 氏(養父市 健康福祉部 社会的処方推進課 課長)



質疑応答

オンデマンド配信中
令和6年度高知県立大学地域共生学研究機構講演会 (PDFファイル:13.74MB)
高知県立大学は令和6年度から高知県立大学10年戦略「UoK Vision 2033」をスタートさせ、柱となる3つの戦略の一つである「地域共生社会を支援する実践的な教育・研究」を進めています。具体的には、「リ・デザインプロジェクト」として、地域を支える様々な立場の「人々がつながり合い」、地域に山積する課題を共に乗り越え、地域のつながりを再構築するための取組を行っています。また、人と地域のつながりで人を元気にする取組「社会的処方」の実践と研究成果の地域還元を「リ・デザイン プロジェクト」の中核と位置付け、プロジェクトを発掘・検討・深化させるための様々な意見交換を行う場として「社会的処方研究会」の開催などにも取り組んでいます。
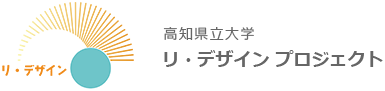

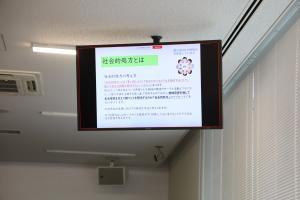


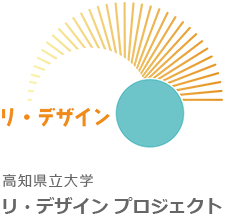
 学校サイトトップ
学校サイトトップ