本文
高知県立大学地域共生学研究機構シンポジウム『共生社会の未来を描く認知症カフェ』を開催しました(2025年6月14日)
高知県立大学では、令和6年度より10年戦略「UoK Vision 2033」を始動し、戦略の一つとして「地域共生社会を支援する実践的な教育・研究」に取り組んでいます。その一環として、地域の多様な主体が連携し、地域課題の解決とつながりの再構築を目指す「リ・デザイン プロジェクト」を推進しています。
このたび、本プロジェクトの一環として実施している「土曜の永国寺カフェ(認知症カフェ)」の活動成果や気づき、今後の展望等を広く共有することを目的に、地域共生学研究機構主催によるシンポジウム「共生社会の未来を描く認知症カフェ」を開催しました。
当日の様子
当日は医療福祉関係者、自治体、企業・NPO法人、一般の方等、県外も含め173名(オンライン含む)の参加がありました。
第1部では、本学社会福祉学部・矢吹知之教授から「共生社会の未来を描く認知症カフェ」をテーマとした講演をいただき、認知症カフェを仕掛ける意義や、カフェの持つ「力」や魅力について、「土曜の永国寺カフェ」の活動を例に挙げながら、説明されました。
第2部は、土曜の永国寺カフェ実行委員会の4名の方にもご登壇いただき、矢吹教授も交えて、認知症カフェを立ち上げた経緯やメンバーとして参加したきっかけ、運営する中での成果や課題、学生視点での学びなど、それぞれの視点からの意見が語られ、最後に矢吹教授からは、「認知症カフェは、全てを解決するものではない」と前置きしつつも、多様な社会資源やピアサポートが連携し、住民一人ひとりの力が合わさることで、「ここにいても大丈夫かな?」と思えるような地域づくりができる、とシンポジウムを締めくくりました。
アンケートでは「認知症カフェが持つ力、共生社会にどのような影響があるのか学ぶことができた」、「カフェが居場所づくりに留まらず、地域とつながりやゆるやかな学びを提供し、その積み重ねによって共生社会に向かっていく流れが分かった」、「心の問題を医療でなく、地域で問題に向き合うその場所が、認知症カフェなのかと理解しました」、「学生さんの参加があることで新たな感覚が芽生えた、学生さんの力がすごい」などの感想があり、認知症カフェの活動の意義や運営者の話を聞くことで、参加者自身の活動への振り返りや気付きを得られたことが伺えました。
今後も、自治体や関係機関との連携を深め、地域共生社会の地域づくりの一助となる活動を進めていきます。
第1部 講演 「共生社会の未来を描く認知症カフェ」
講 師:矢吹 知之 (高知県立大学 社会福祉学部 教授)

第2部 シンポジウム「共生社会の未来を描く認知症カフェの在り方について」
登壇者:廣田 淳也 氏(上街・高知街・小高坂地域包括支援センター)
高橋 英美 氏(サードプレイスすろー)
出嶋 夏奈 さん(高知県立大学 社会福祉学部 3回生)
矢吹 知之 (高知県立大学 社会福祉学部 教授)
進 行:田部 佳枝 氏(高知市基幹型地域包括支援センター)
宇都宮 千穂(高知県立大学 地域教育研究センター センター長)

オンデマンド配信中
地域共生学研究機構シンポジウム「共生社会の未来を描く認知症カフェ」 (PDFファイル:4.68MB)
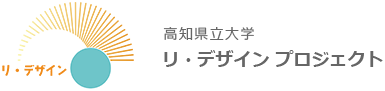


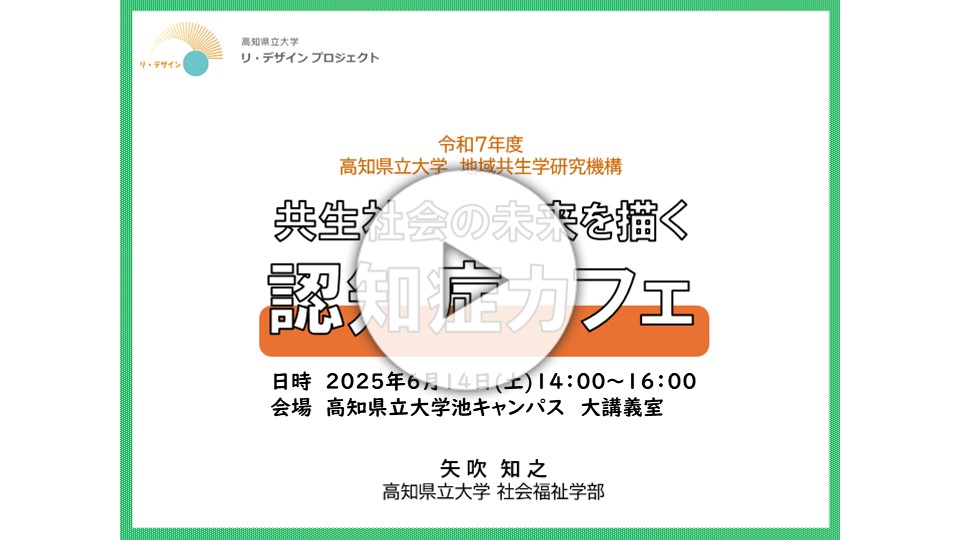

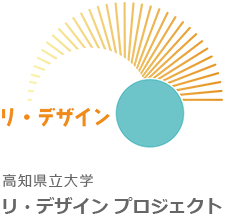
 学校サイトトップ
学校サイトトップ