本文
【開催報告】社会的処方研究会 特別編 「土佐絵金歌舞伎と弁天座」(2024年11月22日)
高知県立大学は、令和6年度から高知県立大学10年戦略「UoK Vision 2033」をスタートさせました。柱となる3つの戦略の一つ、「地域共生社会を支援する実践的な教育・研究」を進めていくため、地域を支える様々な立場の「人々がつながり合い」、地域に山積する課題を共に乗り越え、地域を再構築(リ・デザイン)するための取り組み=「リ・デザイン プロジェクト」を行っていきます。
そこで本学では、人と地域のつながりで人を元気にする取り組み「社会的処方」の実践と研究成果の地域還元を「リ・デザイン プロジェクト」の中核と位置付け、プロジェクトを発掘・検討・深化させるための様々な意見交換を行う場として「社会的処方研究会」を開催しています。
社会的処方研究会 特別編「土佐絵金歌舞伎と弁天座」(2024年11月22日)
2024年11月22日(金曜日)、社会的処方研究会 特別編を池キャンパスにて開催しました。ライブ配信も行い、対面・オンライン合わせて約40人の参加がありました。
今年7月に、高知県津野町の「高野農村歌舞伎」についてご講演いただいた社会的処方研究会 特別編に続き、今回は、土佐絵金歌舞伎伝承会の方や弁天座運営委員会の方から、土佐絵金歌舞伎の歴史や面白さ、また伝統文化の維持・保存・継承への課題や、歴史文化を通じたまちづくりなどについてご講演いただきました。
まず、土佐絵金歌舞伎伝承会 事務局長 横矢 佐代 氏より、土佐絵金歌舞伎についてご講演いただきました。高知県香南市赤岡町は、江戸時代末期には商都として栄え、土佐藩の御用絵師であった弘瀬金蔵(通称 絵金)が描き残した芝居絵屏風23点を現在も大切に保存しています。「土佐絵金歌舞伎」は、絵屏風に描かれた歌舞伎の演目を実際に演じてみようと、地元の有志が平成5年に発足させた文化活動です。毎年、7月に行われる絵金祭りの2日間に合わせて上演されています。横矢氏は、「土佐絵金歌舞伎伝承会」の発足時から今まで携わってこられ、0(ゼロ)からのスタートだった土佐絵金歌舞伎が始まった経緯、衣裳や大道具・小道具を手作りした苦労話、役場や地域の方の協力を得ながら進めていったことをお話しくださいました。
また、今年7月の絵金歌舞伎公演までの流れを紹介。今年は子供たちだけで「義経千本桜 鮨屋の段」を演じたそうです。指導役の先生に演目のあらすじの説明を受け、勉強することから始まり、発声練習、立ち稽古、下座音楽の練習など、本番までの様子をお話しくださいました。
土佐絵金歌舞伎伝承会は弁天座の運営にも大きく関わっておられ、これからは弁天座を中心に地域文化の伝承に取り組んでいきたいと締めくくられました。


続いて、弁天座運営委員会 小屋番 浜口 尚之 氏より、弁天座についてご講演いただきました。芝居小屋「弁天座」は平成19年に再建され、赤岡町の様々な文化的活動や地域交流の拠点となっています。弁天座が開館した経緯、舞台の特徴、これまでの自主事業、地域活性に向けた取り組みなどについてお話しくださいました。また、新たに始めた体験プログラムや蚤の市、展覧会などについて紹介されました。


発表に続いて行われた質疑応答では、1999年に行われた土佐絵金歌舞伎のフランス公演での様子や、“津野町の「高野農村歌舞伎」”や“いの町の「八代農村歌舞伎」”など他地域の地芝居との交流、次の世代へつなげる伝承における課題等について質問がありました。


会場には実際に絵金屏風のレプリカも飾られ、初めて絵金屏風をご覧になった参加者も多く、興味深く眺めていました。


参加者からは「歌舞伎を通じたまちおこし、地域の活性化の実際をお聞かせいただき大変勉強になった」「絵金歌舞伎、弁天座を通じて地域を活性化させる意欲がひしひしと伝わってきた」「高知県にこんなに素敵な場所があるのかと、驚いた。あきらめない、とりあえずやってみようという心意気が大事であることを学び、自分も今後おこなってみたいと思った」などの感想をいただきました。
ご参加いただいた方々に心よりお礼申し上げます。
オンデマンド配信中
社会的処方研究会 特別編 「土佐絵金歌舞伎と弁天座」当日配布資料 (PDFファイル:20.82MB)
社会的処方は大学だけで形作るものではありません。ぜひ社会的処方の取り組みを一緒に進めていきませんか。
社会的処方について学びたい、プロジェクトの内容を知りたい、何かしら大学と連携してみたい、など大歓迎ですので、お気軽にご参加ください。
※社会的処方研究会 特別編 「土佐絵金歌舞伎と弁天座」の詳細はこちらをご覧ください。
(開催案内のページへ)

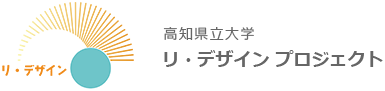


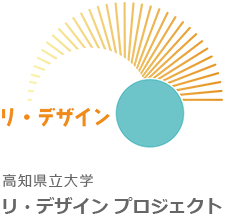
 学校サイトトップ
学校サイトトップ