本文
歴史文化を通じたまちづくり
先端技術を駆使して
地域の歴史文化の保存・継承・活用を考える
 高知県にいくつも残る有形・無形の文化財や民俗芸能。しかし、住民の高齢化や人口減少などによる担い手不足から、継承や保存が困難になっている地域も少なくありません。
高知県にいくつも残る有形・無形の文化財や民俗芸能。しかし、住民の高齢化や人口減少などによる担い手不足から、継承や保存が困難になっている地域も少なくありません。
このプロジェクトでは、地域に残る地歌舞伎・盆踊りなどの保存・継承がコミュニティの活性化につながるよう、新たな形でのサポートができればと、「モーションキャプチャー」を用いたスポーツ科学の領域からのアプローチを考えました。
また、「3Dスキャン技術」を使って、建築物などの有形文化財をインターネット上の仮想空間に取り込み、世界中の人がアクセスできる新しい空間を生み出したいと考えています。
目的
地域に受け継がれた有形・無形の歴史文化をデジタルデータとして記録することにより、歴史文化の保存・継承や活用を支援する。
活動内容
人の動作を3次元データとして記録する「モーションキャプチャー」を用いて、津野町高野地区の「高野農村歌舞伎※1」や佐川町尾川地区の「尾川踊り※2」などの動きを科学的に分析しようと計画を進めています。データを保存するだけでなく、見せ場となる動きのコツを分かりやすく解説したり、PR用のコンテンツ制作に活用したいと考えています。
また、建築物などを3次元のデジタルデータとして取り込む「3Dスキャン技術」を使って、津野町の有形民俗文化財「高野の舞台」のデジタル化にも取り組んでいこうと計画を進めています。こちらも、3Dデータとして保存するだけでなく、インターネット上に構築された3次元仮想空間(VRプラットフォーム)に取り込んで、コミュニケーションの場を生み出したいと考えています。
※1 高野農村歌舞伎
津野町高野地区で約150年前から続いている地歌舞伎。日本で唯一の「鍋蓋上回し式舞台」を持ち、昭和52年に国の重要有形民俗文化財の指定を受けた。
※2 尾川踊り
佐川町全域に古くから伝わる盆踊りのひとつ。毎年10月に開催される「おがわ秋祭り」では、祭りの終盤になると集まった地域住民が踊り場の花台を囲み、大きな輪を作って踊る。
担当教員
地域教育研究センター 高徳 希 准教授
総合情報研究センター 根本 大志 講師
関係団体
高野農村歌舞伎保存会
尾川踊り保存伝承会(尾川地区活性化協議会)
KEY WORD
歴史文化/文化財/民俗芸能/継承/デジタル化/モーションキャプチャー/3Dスキャン/地域のつながり/…
関連リンク
高知県立大学と津野町との地域共生社会の推進に向けた連携協定を締結(2024年3月27日)
社会的処方研究会 特別編 高野農村歌舞伎 (2024年7月17日)
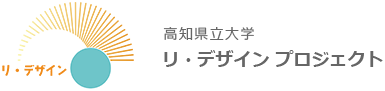

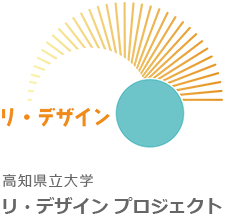
 学校サイトトップ
学校サイトトップ