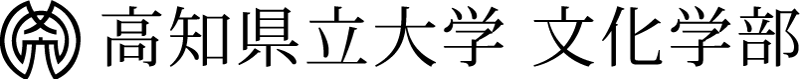地域文化創造系|地域文化・地域づくり領域|教員紹介
宇都宮千穂 UTSUNOMIYA, Chiho

【役職】 教授
【専門分野】 日本経済史・地域経済学
【研究テーマ】 地域における生活空間の形成、企業都市形成論
【主な担当科目 】 地域学概論、地域学実習、文化政策論、地域づくり論、地域づくりフィールドスタディ、地域づくり専門演習、文化学課題研究ゼミナール
- ►研究者総覧
- ►researchmap
-
MESSAGE 近現代の地域を、経済史の視点から研究しています。
地域が発展するときは、きっかけがあります。代表的なきっかけは、産業が誘致されることです。このような産業を地域の基幹産業と呼びますが、私の研究は、地域が基幹産業の影響を受けながら形成されていく過程を明らかにするものです。
ですが、私の一番の関心は、実は基幹産業ではなく、その基幹産業の影響をうけながらかたちづくられる「暮らし」です。基幹産業が違えば、働きかたも違い、暮らしかたも違います。例えば、工場で働く人と林業をしている人では、暮らしかたが全然違います。その違いが、地域形成に大きく影響を与え、結果として、地域独自の空間と生活文化をつくりあげていきます。その独自性を発見するのが、とても面白いのです。思わぬところに独自性を発見し、びっくりすることもしばしばです。これら暮らしの特徴は記録し、その特徴が存在する要因も分析する必要があります。こうした調査研究の積み重ねは、地域の社会経済構造をとらえることに役立ち、様々な政策を考えるときの資料になります。
「地域の暮らし」にまつわる研究テーマは、たくさんあります。高知をフィールドに、高知らしい暮らしの文化を一緒に研究しませんか?
大井方子 OI, Masako

【役職】 教授
【専門分野】 労働経済学・計量経済学
【研究テーマ】 技術革新と賃金の関係、女性労働、少子化問題、若年者雇用、地域の雇用などに関する実証研究
【主な担当科目 】 経済学、文化と経済、社会調査論、地域産業論
- ►研究者総覧
- ►researchmap
- ►ホームページ
-
MESSAGE 経済学は、産業や市場などにおいて、個々の企業や個人の意思決定がどのように相互に作用しているのか、また、意思決定に何が影響しているのか、そして、人々の幸福度を引き上げるにはどのような政策を取ればいいのかなどを考える学問です。
私は経済学のなかでも、労働経済学を専門としており、その実証研究をしています。つまり、働くということに関して、経済学的に考えるとこういうことが起きているのではないか、と実際のデータを使って示しています。例えば、労働経済学のトピックの一つとして少子化問題があります。子供を産み育てること、仕事と両立させることという意思決定・行動に何がどう影響しているかを、経済学を用いて考え、それをデータで示すということは、エビデンス(証拠)に基づいた政策形成を推進しようという昨今、大きな意味があります。
経済学という道具を用いて社会を見ると、理解が深まり、面白いと思うことが多々あります。データを見ながら一緒に考えることができたら嬉しく思います。
吐合 大祐 HAKIAI, Daisuke

【役職】 講師
【専門分野】 政治学(政治過程論・行政学・公共政策論)
【研究テーマ】 地方政治における政策形成メカニズム、地方議会議員(都道府県議会議員)の行動分析、政策形成における都道府県の役割、国会議員の選挙戦略と議会内行動の関係
【主な担当科目 】 政治学、地域分析論、地方自治論、地域づくり専門演習、文化学課題研究ゼミナール
- ►researchmap
-
MESSAGE 私の専門分野は政治学で、これまで主に「地方自治体における政策決定メカニズム」を対象とする研究に取り組んできました。選挙公報や議会活動などの公開データを分析しながら、政治家たちの考えや戦略をどうやって見出すことができるのか。そして政治家たちの考えや戦略は、私たちの政策にどう影響をもたらすのか。データ分析だけでなく、議員への聞き取り調査や歴史的資料にも活用しながら、研究活動に取り組んできました。
私が研究対象とする政策(Public Policy:公共政策とも呼ぶ)には、地域に住む人々は当然のこと、我々が選び出した政治家、政策を動かす立場の公務員・地域団体の人々、政策を考える有識者の人々の意見、そして地域社会や経済などコミュニティに携わる多様な人々の「利益」「信念」「アイデア」が色濃く反映されます。
一見すると、政治学講座は、文化学部の中でも「すわりの悪い」分野かもしれませんが、決して無縁ではありません。政策が生み出す社会現象が文化に及ぼす影響は極めで大きいからです。政策はどのように作り上げられるのか。政策は人々の暮らしや動向にいかなる影響を及ぼすのか。自治体間で異なる政策が生まれるのはなぜか。政策活動はどのように進められ、社会での運用を経てどう変貌を遂げていくのか。
これからの社会や生活を考えるにあたって、政治や政策の存在を無視して議論することは不可能です。「実証的な視点を用いて、世の中の動きや変化を理解する」ことを皆さんとともに目指していきたいと思います。
濵田愛 HAMADA, Megumi

【役職】 講師
【専門分野】 都市計画、都市デザイン、まちづくり
【研究テーマ】 都市・地域の生業と都市空間の関係、及びそれらを支える制度
【主な担当科目 】 地域文化論、文化政策論、地域づくりフィールドスタディ
- ►研究者総覧
- ►researchmap
►ホームページ -
MESSAGE 私たちが暮らしている身近な都市や地域の空間は、歴史や人々の活動、制度によって形成され、支えられています。
私はその中でも、生活と生業の関係性、特に都市において消費される「もの」の「生産・製造」、及びその「流通」を支える仕組みや、そのプロセスにより形成される都市空間の特徴について、調べています。何かを創り出し、製造するという機能は、分業化が進んだ現代の私たちの生活においては、消費や雇用の観点から欠かせない都市機能である一方で、生活空間とは切り離されている場合も多く、その都市空間における位置づけが重要です。
それぞれの場所にそれぞれの生活やルールが存在し、都市や地域を学ぶことは、様々な人々の暮らしを知り、体験させてもらうと同時に、自分のこれまでの都市や地域、文化の経験を相対化して再認識する機会にもなります。皆さんと一緒に、地域に向き合い、考えていけたらと思います。
言語文化系
地域文化創造系
- 地域文化・地域づくり領域
- 観光文化・観光まちづくり領域
- 現代法文化・生活法文化領域