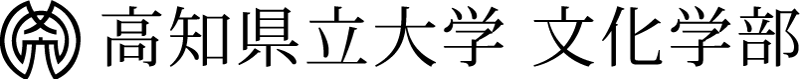言語文化系|英語学・国際文化領域|教員紹介
五百蔵高浩 IOROI, Takahiro

【役職】 教授
【専門分野】 英語学(音韻論・形態論・コーパス利用)・英語教育学
【研究テーマ】 英語学の理論研究から得られる知見が、英語習得論研究にどのように応用できるかという点を考えています
【主な担当科目 】 言語教育実践論Ⅰ、言語教育実践論Ⅱ、英語音声学、言語学概論、英語学概論
- ►研究者総覧
-
MESSAGE 私の専門とする領域は、英語の特質を明らかにする英語学という分野と、英語という外国語の習得と指導を関する様々な側面を考察していく英語教育という分野から成り立っています。基本的には“ことば”についてのあらゆることに興味を持っています。なので、英語に限るということはありません。卒業論文の作成に繋がっていく「課題研究ゼミ」では、“ことば”がキーワードです。それに関連するトピックを掘り下げたいと考えている人は皆歓迎します。ただし、お願いがあります。みなさん、外国語は少なくとも1つは汗をかいてみっちり学習しましょう。そうすると自分の母語もよく見えてきます。比較するという視点も芽生えてきます。その点で言うならば、中学校・高等学校で学んできた英語という言語は、好き・嫌いは別にして、これまで学習した成果として大事にしてほしと思います。やっておけば必ず「若い時にやっててよかった」と思うようになると思います。特に、読むことと書くことをしっかりと伸ばしていきましょう。しっかりとした幹ができれば、枝は自然に伸びてきます。面白いと思うことがあったら、それをとことん探究してみませんか。一緒に学びましょう。
金澤俊吾 KANAZAWA, Shungo

【役職】 教授
【専門分野】 英語学
【研究テーマ】 形式と意味との対応関係について 英語における形容詞の意味的特徴について
【主な担当科目 】 英語学概論、英語文法論、英語ライティングⅠ、英語学専門演習Ⅰ、言語学概論
- ►研究者総覧
- ►researchmap
-
MESSAGE 高校までの英語を勉強する中で、文法用語は覚えていても、肝心の単語や構文の使い方を覚えられないという経験があると思います。
授業を通じて、英語という言語がもともと持っている性質から、英語の構文の特徴を探っていきます。そして、この英語の特徴は、日常生活において、私たちの物事や場面の捉え方と密接に関わることを学んでいきます。例えば、John gave her an apple.とJohn gave an apple to her.は、学校文法では、相互に書き換えられ、同じ意味を表す構文として扱われます。しかし、実際には、その場面を捉えている人が、何に注意を当てるかによって、使い分けが決められています。
様々な言語現象について「なぜ」という疑問を持ち、それに対する答えを探ることで、言葉の面白さを感じていきましょう。私たち日本語話者であるからこそ気がつく、英語の面白さ、英語を学ぶからこそ気がつく、日本語の面白さに気づくはずです。
文化学部では、英語を学べる、触れられる環境が整っています。英語を学びながら、この一つひとつの「気づき」を大切にし、言語をしっかり観察し、使いこなせる力をつけていきませんか。
白岩英樹 SHIRAIWA, Hideki

【役職】 教授
【専門分野】 他者論、比較文学、比較芸術
【研究テーマ】 近代アメリカ文学における他者関係、表現とケアの問題、翻訳と文化受容
【主な担当科目 】 米文化・文学論、米文化・文学史、異文化理解、英語科教育法、国際文化専門演習、文化学課題研究ゼミナール
- ►研究者総覧
- ►researchmap
-
MESSAGE 若い友人たちへのエールを込めて!
Q1.文化学部はどのようなひとに向いていると思いますか?
A1.まず、特定の文化分野に強烈に魅かれているひと。それに加えて、ちょっとでも生きづらいなと感じたり、現行の社会や価値観になにかしらの違和を感じたりしているひとです。生きづらさは皆さんひとり一人に秘められた潜在的な力(ポテンシャル)の現れにほかなりませんし、違和感は社会の別の可能性(オルタナティヴ)を構想し、新たな価値観を創出する強大な推進力になるからです。Q2.文化学部ではどのようことが学べるのですか?
A2.ぼくの専門は詩や小説、写真や彫刻といった芸術分野です。それらはあくまで虚構にすぎません。が、だからこそ現実社会へのカウンターという、もっともラディカルな役割を担うことができるのです。すぐれた作品には、「いま・ここ」とはまったく別の「フレーム」が起爆装置のように組み込まれています。それらを内に取り込むことで、ぼくたちは現実のありようを”one of them”として相対化することができる。別の可能性(オルタナティヴ)の構想と実現という、社会の新たな枠組み形成(リフレーミング)はまさにそこから始まるのです。Q3.受験生へのメッセージをお願いします。
A3.今日、人類は地球規模の災害やパンデミックを経験し、現行の「フレーム」では太刀打ちしようのない危機に見舞われています。そろそろ、「いま・ここ」でしか通用しない価値観から脱け出す好機でしょう。皆さんがわずかなりとも感じている生きづらさや違和は、その時宜を察知している証なのです。人類の遺産たる多種多様な文化をベースに、皆さんと潜在的な力(ポテンシャル)を引き出し養いあい、大胆な新たな枠組み形成(リフレーミング)を試み、それぞれの別の可能性(オルタナティヴ)を創出する。そんな出逢いが実現することを愉しみにしています。
鳥飼真人 TORIKAI, Masato

【役職】 教授
【専門分野】 近現代イギリス文学、西洋文学理論
【研究テーマ】 イギリス文学と西洋思想の関係、文学を読むこと=解釈が社会に及ぼす影響
【主な担当科目 】 英文化・文学史、英文化・文学論、国際文化専門演習、異文化理解
- ►研究者総覧
- ►researchmap
-
MESSAGE 「文学研究が世界を平和に導く」―何とも大げさなフレーズだと思われるでしょうが、しかしこれは現在、世界の文学研究における最重要課題の一つと考えられています。文学作家が作品を書くということは、その作家がある一定の立場から、ある考えに基づいて作品を書くということを意味します。読者の中には、その立場や考えが理解できない人もいるでしょう。特にその作家とは異なる時代や文化を生きる人々にとってはなおさらのことです。しかしそれらを理解できないまま放っておいたり敵視したりするのではなく、何とか理解しようと努力する時、人(自己)と人(他者)との相互理解、または異文化間の理解への扉が開かれます。このことが、小さいながらも世界平和を実現するための第一歩となります。このように、文学は人と人をつなぐ手段となります。例えば皆さんが現在SNSを通じて人とつながることができるのは、皆さんに文学的センスが備わっているからだと言えるでしょう。また文学は、私たちと私たちを取り巻く世界をつなぐ手段でもあります。すなわちある時代にある地域で書かれた文学作品を読むことで、その時代、その地域で現実に起こっていた(または今起こっている)政治や経済、文化を知ることができるのです。
文学とは現実の世界を知ること、そして世界中の人々をつなぐことを目的とした「実用的」な学問だと私は信じています。イギリス文学はこのような研究の方法や理論を学ぶためにとても重要な役割を果たします。この大学で「実学」としての文学を学んでみませんか。
ヨース・ジョエル JOOS, Joel

【役職】 教授
【専門分野】 日本史・特に日本思想史・日本文化史
【研究テーマ】 近代歴史学、近代思想において、「自由」などの西洋的と思われる思想が、いかにして日本に入ってきたか、土着的な伝統とどのようにして結びつき、日本思想の一つになったか。
【主な担当科目 】 国際日本学Ⅰ、国際日本学Ⅱ、日本思想史、日本文化論
- ►研究者総覧
-
MESSAGE 大学で学ぶとは、大きく学ぶことです。大きく学ぶのには、手足を大きく広げて、大の字になって、未知の領域に飛び込む勇気が必要です。また、文化学部で学ぶのには、「大」から「文」へと、深呼吸をして肺を空気で満たすのと同じ様に、様々な分野から知見と視点を吸収して知識を取り入れることが肝心です。
文化学部では、教職免許を除いて、一定の職に直結する資格を取得することが目標とされていませんが、〈特技〉を身に付けることは、けっして不可能ではありません。それどころか、確実に出来ます。それは、あらゆる文化の根拠にある〈言葉〉という特技です。色々な科目が提供される文化学部では、多種多様な考え方と社会観に接して、それらを消化し、再び表現する訓練を繰り返します。言葉を型どおりに並べるだけでは済まない、創造的な眼差しが求められます。このように、一つの狭い分野や窮屈な専門用語に縛られず、視野の広さを確保し、言葉の真意を嗅ぎ取る感受性が芽生える学習環境を用意してくれるのが、文化学部です。
道があるから人が歩く、のではなく、人が歩くから道がある、という発想をもとに、大きな学びに挑戦していただきたい。
向井真樹子 MUKAI, Makiko

【役職】 准教授
【専門分野】 理論言語学・応用言語学・外国語教育(日本語・英語)
【研究テーマ】 日本語、英語、北欧諸言語、ロマンス諸言語の複合語の成り立ち方、文法、形態、意味
【主な担当科目 】 日本語Ⅱ、言語学概論、比較言語研究、対照言語学、英語スピーキングⅠ、英語学専門演習Ⅱ、言語教育実践論Ⅱ
- ►研究者総覧
-
MESSAGE ことばから世界を発見する?
文化学部では、多くのことを学びながら最終的に自分の調べたいテーマを絞っていくという、深くも幅広い視野で勉強をすることができる本当に恵まれた環境が整っています。
私のゼミでは、主に言葉について研究をします。その発端は、私自身が13歳の時から17年間イギリスに父の転勤で引っ越し、住んでいた時にことばほど大事なものはないと実感したからです。今でも自分自身、教えながら毎日が発見です。
日本語だけではなく、英語、デンマーク語、ノールウェイ語、スウェーデン語が私の専門なので、様々な言語を見、結局自分が興味を持っている言語はどういう言語なのかということを考えるのが目的です。一つの言語をみるだけではわからないようなことが、比較することでみえてきます。
今まで当たり前だと思っていた自分のことばが、新鮮にみえてきます。私自身、今2歳の子供がいますが、彼にとっては毎日が新しい発見のようで、毎日、必ず1つの単語をぽろっと発します。みなさんも自分が子供の時をお母さん、お父さんに聞いてみてください。そうすると、当たり前としてできていることができなかった、新しい発見をしていたことを教えてくれるはずです。そのように、みなさんもことばだけではなく、自分の周りのことに改めて気付いてみる、意識してみると新しい世界が開けるかもしれません。
言語文化系
- 英語学・国際文化領域
- 日本語学・日本文学領域