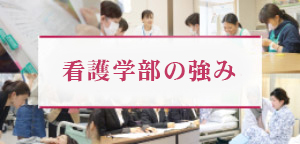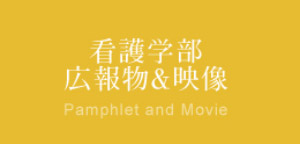本文
未来の看護を拓く教育、研究への取り組み
看護学部の教員は、新たな教育方法を開発するとともに、様々な視点から個人あるいはチームで研究を行い、これからの看護について社会に発信できるよう取り組み、日々の教育に活用しています。
教育活動の工夫の紹介
ディープアクティブラーニングの要素を取り入れた高齢者擬似体験
 2回生の「老人の健康と看護」では、高齢者擬似体験を実施しています。
2回生の「老人の健康と看護」では、高齢者擬似体験を実施しています。
高齢者擬似体験は、未だ学生が体験したことのない高齢者の世界を理解し、高齢者の生活上の工夫や課題を探求すること、体験を通して高齢者のケアの在り方を考え、新たな問いや疑問をもつことが目的です。なかでも大事にしている視点は、単なる体験に留まらず学生が擬似体験のプロセスを通して身近な高齢者を想起し、いかに考え、行動し、実践するかといったディープアクティブラーニングの要素を取り入れた能動的学習を重視していることです。
そのため、学生主体となるようにペアの学生がもう1人の学生に、体験場面ごとに問いを投げかけるデブリーフィングの考えを取り入れた“アクションカードの活用”や、個人の体験内容を深める“リフレクションシートの活用”、学生同士の相互作用による学びを深める“ピアインストラクション”の時間を設けるなど、教育手法に工夫を凝らしています。
広い視点で保健医療福祉システムを捉え、看護の専門性について考える看護管理実習
4回生の必修科目である「看護管理実習」は、システム思考を用いて保健医療福祉の専門職の取り組みを機能・本質という視点で分析・把握し、理解していく実習です。例えば「在宅への移行支援」「精神保健の自殺予防」「緩和ケア」「産科フロアとNICUの連携」について分析します。
実習では、そのシステムに関わる様々な専門職者にインタビューしたり、関連する資料から情報収集を行うなどして、システム思考を用いて情報を整理し、可視化していきます。その際、鳥の目で全体を俯瞰(ふかん)しつつ、虫の目でミクロに複眼的に捉え、魚の目で流れをみることを繰り返します。この体験を通して、多職種連携や多機関連携の特徴と看護の専門性、退院支援、医療と福祉の連携など、時代とともに変化するシステムを学ぶことができます。さらに、「何のため?」と確認したり、目の前にある現象を一歩引いて俯瞰して捉える姿勢を培ってほしいと思います。
実践力を高める教育 ~看護実践能力開発実習~
近年、入院期間の短縮や高度医療、患者の重症化、倫理的課題などにより、看護基礎教育の実習で経験できる看護技術が限られる傾向にあります。4年次の最後に、これまで習得してきた知識・技術・態度・行為を統合し看護実践能力を高めることを目標として、シミュレーション学習を取り入れた実習を行っています。
この実習では、新人看護師が臨床で対応を求められる機会が多い看護場面、臨地実習において学生が受け持つ機会が少ない患者の看護場面、複数の技術の組み合わせや工夫が必要な場面を通して、より実践に近い看護技術を磨き、実践力を高めていきます。
学生からは、「4年間の授業で学んだことや実習・演習で実践してきたことを総動員して事例を考えることができ、バラバラだった知識が少しずつ繋がった」、「今までの知識も使って考えられたので学んだ知識が使える知識になった」、「できる看護技術が増え、自信を持つことができた」等の声が聞かれます。
今後も、社会的要請や学生のニーズを捉えながら、学生の力を引き出す、そして、臨床実践と繋がった教育方法の工夫を続けていきたいと思います。
研究力の育成
批判的思考(Critical Thinking)を育む~データとの対話のすすめ
 看護研究をとおして、大切にしていることの一つが、理論や既存の知識体系を基盤としながら物事を論理的に捉え、判断する科学的思考を身に付けることです。そして、既存の知識や現象の捉えをそのまま受け入れるのでなく、本当にそうだろうか、どのような意味があるのだろうか、何を表しているのだろうかと問いを発し、自問しながらみる視方-批判的思考(Critical Thinking)を学んでいってほしいと思っています。
看護研究をとおして、大切にしていることの一つが、理論や既存の知識体系を基盤としながら物事を論理的に捉え、判断する科学的思考を身に付けることです。そして、既存の知識や現象の捉えをそのまま受け入れるのでなく、本当にそうだろうか、どのような意味があるのだろうか、何を表しているのだろうかと問いを発し、自問しながらみる視方-批判的思考(Critical Thinking)を学んでいってほしいと思っています。
批判的思考とは、物事を論理的に考えることであり、自分自身の思考を吟味することです。それには常に問い続ける姿勢、最新の情報を探索していく姿勢が大切だと考えます。自らの問いを立て看護研究に取り組む中で、様々な文献に示された知識体系や結果として導かれたデータと対話し、紐解きながらその意味を捉え、新たな見方を創っていってほしいと思っています。