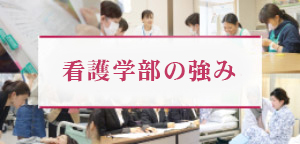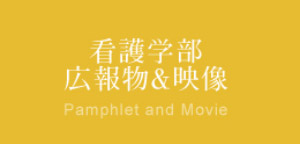本文
令和5年度 看護相談室 交流会
【テーマ】私と研究
【日時】令和6年2月12日(月曜日・祝日)13時30分~16時
【方法】オンライン会議(ZOOM)
【参加者】9名(大学院6名、教員3名)
【報告者】看護学研究科博士後期課程(看護学部 特任助教) 加藤昭尚
今年度の交流会は、梶谷氏(東京大学)の「哲学対話」(考えるとはどういうことか、幻冬舎、2018)を参考に「研究と自分」というテーマで自由に意見交換を行いました。
哲学対話とは、学校で子どもたちの思考力を育てるための方法として始まったものであり、「子どものための哲学」のスタイルとして知られています。そして、以下のようなルールをあげて対話が行われます(対話の目的などによってルールや進行の仕方は異なります)。
①何を言ってもいい。
②人の言うことに対して否定的な態度をとらない。
③発言せず、ただ聞いているだけでもいい。
④お互いに問いかけるだけでもいい。
⑤知識ではなく、自分の経験にそくして話す。
⑥話がまとまらなくてもいい。
⑦意見が変わってもいい。
⑧分からなくなってもいい。
話し合いでは、参加者が現在取り組んでいる研究の内容や、これまで研究を通して経験したこと、研究に取り組む理由・大切にしている事・ワクワクするところなどについてお互いに問いを投げかけながら対話を進めていきました。
参加者は、教員や在学生が多かったためある程度お互いを知っているつもりでしたが、普段なかなか聞けない研究への思い(動機、面白さ)や研究に取り組むことによる参加者の変化などについて知ることができたと思います。また、参加者がそれぞれ自身の研究への思いや向き合い方を語ったり、他の参加者へ問いかけることを通して、自身と研究との向き合い方を見つめなおす機会となったようでした。
最後は、それぞれが言いたいことを話せたことを確認し、交流会を終えました(哲学的対話は、最後にきれいにまとめようとはしません。それぞれがもやもやしたものを持ち帰ったり、それまでと違って視野が広がったような体験をして終わります)。普段の研究活動では、論理性・一貫性のある議論や文章を書くことが求められますが、時には「『考える』ことを楽しむ時間もいいな」と思える交流会でした。
令和5年度 第2回ケア検討会
【テーマ】ケア検討会
【日時】令和5年10月13日(金曜日)18:00~20:30
【方法】オンライン会議(ZOOM)
【参加者】23人(外部参加者13名、大学院生8名、教員2名)
【報告者】看護学研究科 看護管理学領域 博士前期課程 駒村 元貴
今年度第2回目のケア検討会は「臨床実習における学生指導のあり方」というテーマで開催しました。
事例提供者からは、教員として実習指導を行う中での困難について情報提供がありました。具体的には、学生に指導内容が伝わらなかったり、学生に振り回されたりなど、様々な困難がありました。学生にとって初めての実習を少しでも良いものにしたい、そして大変な状況下で学生を受け入れて頂いている実習施設に対しての感謝といった教員側の思いとは裏腹に、学生の実習態度には目に余る場面もあったようです。そして、そうした場面で指導をしても学生に変化はみられず、次第に教員の口調も強くなり、学生との関係性に影響を及ぼすなどの葛藤を抱えていました。その他、現場の実習指導者の評価と上記のような場面が影響した教員の評価が異なり、教員自身も混乱していたようです。
参加者からの質問により、事例の状況が浮き彫りになっていきました。特に、実習指導者と教員間で学生に対する評価にずれが生じた原因について意見交換がありました。その1つに、指導者と教員とで評価対象の場面に違いがあることが挙げられました。臨床の実習指導者が評価する場面は限られています。主に、学生が看護師とやり取りをする場面や患者さんへのケアにあたる場面などを中心に評価します。一方、教員は、様々な場面での学生の様子を評価の対象としてみています。学生の実習に対する態度(控室での様子も含めて)は適切か、主体的に望んでいるか、実習記録は予定通りに進んでいるかなど、細かい視点で評価しています。
2つ目の理由として、教育者としての価値観の違いが挙げられました。今回の事例提供者は、前述したように、実習施設に対する感謝、礼節に重きを置いていました。この考え方は教育者によって様々かもしれません。実習目標の中でも主観的な評価項目においては、教育者の価値観が影響し、そのことが評価のずれにつながっていたのではという意見も交わされました。
続いて、学習者に対する効果的な教育について意見交換が行われました。いくら指導しても伝わらない、行動変容が起きない相手に対する教育は、臨床現場で現任教育を行う参加者にとっても共通の課題です。参加者との意見交換の中で、「対象理解」という視点が重要ではという意見が出ました。看護の基本は対象理解というように、学生にも学生なりの考えがあり、行動には意図があります。実習における様々な場面での好ましくない行動や態度にも学生なりの理由があるかもしれません。臨床現場において、管理者側と価値観の違う若い世代の看護師を指導する時は、相手との対話を大切にしているという意見がありました。その他にも、ルールを守れていないとか、何か問題となる行動をしていた時には、その都度伝えるようにし、落ち着いたときに改めて振り返るようにしているという意見がありました。これらの意見を通して、重要なことは、学生の思いを尊重しつつ、学生との相互作用の中で共に解決策を考えることであると感じました。
はじめは、当時の実習指導が良くなかったのではないかという思いを抱いていた事例提供者も、参加者からの承認や共感を通して、自身の良かった面も認識することができていました。このようなプロセスがリフレクションの機会となり、参加者からのフィードバックから“気づき”につながるのだと感じました。最終的には、「気持ちが楽になりました、みなさんの意見から視野が広がったので、今後の自身の成長に繋げていきたいです。」との発言がみられ、笑顔で終えることができました。
(参加者のアンケート用紙より)
・実習指導での悩みが大学教員であれ、専門学校の教員であれ関わり方や学生理解に悩んでいるのだということがわかった。
・緊張の連続である臨地実習の場で、教員の役割や臨床側の指導者の役割は異なっていることも多い。いかに、その実習を効率的に効果的に目的目標が達成できるよう準備するのは、教員の役割でもあると思う。個々の学生のレディネスや学習課題等を臨床・学校側と情報交換し学びの多い臨地実習が行えるよう取り組まなければならないと感じた。
・私の経験について共感していただき、もやもやしていた気持ちが整理できたと思います。すぐには解決できないかもしれませんが、今後も学生指導に向き合っていきたいと思えました。
・さまざまな立場の方たちの考え、大切にしていることに触れ、自身について再考する機会になりました。
・学生指導は未経験の私でしたが、学生指導にあたっておられる先生方や実習担当者がどのような思いで関わっておられるか知るとてもいい経験になりました。また、新人教育を思い出し、自分の指導を振り返ることができました。
・それぞれが自分の意見を出し合えたこと、話題提供者への愛を感じたことが良かったです。

令和5年度 第1回ケア検討会
【テーマ】ジェネラリスト?スペシャリスト?人材育成のベストバランスを探る
【日時】令和5年6月9日(金曜日)18時~20時30分
【方法】ハイブリット開催(Zoom又はA219)
【参加者】28名(外部参加者18名、大学院生8名、教員2名)
【報告者】高知県立大学看護学研究科 博士前期課程 尾崎裕美
令和5年度1回目のケア検討会は、人材育成をメインテーマとして「ジェネラリスト?スペシャリスト?人材育成のベストバランスを探る」と題して、事例検討を行いました。
日本看護協会は、ジェネラリストを「経験と継続教育によって習得した暗黙知に基づき、その場に応じた知識・技術・能力が発揮できる者」と定義しています。一方、スペシャリストは、特定の分野に卓越した知識と技術を有した看護職と考えられています。
事例提供者の部署である手術室では、特定の診療科に特化したスペシャリストナースの育成を重視してきましたが、スタッフ間で手術件数にばらつきが生じることや、緊急時に入れるスタッフが限られてしまうなどの課題がありました。そこで、ジェネラリストとスペシャリストのバランスをどのようにとりながら人材育成していくことが大切なのか…こうした悩ましい状況が今回のケア検討会では議論されました。
参加者からは、それぞれの各現場での率直な困り事についての意見が挙げられました。管理者の交代に伴い人材育成の方法が変わることは、スタッフにどのように伝わっているのか?その新しい方法を定着させていくための戦略とは?スタッフが新しいやり方に主体的に取り組めるような仕組みづくりや具体的な工夫とは?等、自組織の手術室でも苦慮している具体的な問題についても共有しながら、多様な現場で看護管理実践を展開している参加者とも熱いディスカッションが行われました。ディスカッションをしていく中で、事例提供者は管理者としてスペシャリストとジェネラリストのバランスをコーディネートしながら、スタッフの声にも真摯に向かいあい変革を推進していく姿が見えてきました。
事例の内容とは別に、参加者から事例提供者に対して、スタッフの部署異動に関する対応についての質問が見られるなど、現場で悩みを感じている管理者が意見交換をすることでそれぞれの視野が広がっていく場になっていました。
最後に大学院生からは、事例に関連した「手術看護における経験年数別の看護実践に関する実態調査」「中堅の中間看護管理者がとらえる人材育成に関する問題」という2本の論文紹介があり、文献を踏まえての意見交換も行われました。
事例提供者が管理者として、目指す看護師像をスタッフに示し、熱い思いを持ち、人材育成や組織改革に取り組まれていることに刺激を受けた参加者にも良い波及効果が得られると期待しています。また、人材育成というテーマは、多くの管理者が、悩みながら、より質の高い看護を提供できる組織を目指して、その方法を模索している、永遠のテーマなのだと再認識する機会となりました。
【以下 アンケート結果一部紹介】
- この度は大変貴重で素晴らしい検討会に参加させて頂きまして、ありがとうございました。 今後、また検討会ありましたら、是非とも参加させて頂きたいと思います。
- 当院でも手術室看護師の育成は大きな課題になっています。「整形外科の器械だしをできる看護師が育っていない」と言われ、スペシャリスト育成と銘打ち、診療科別チーム制にしましたが思ったようには育たず、オールマイティ看護師も育成できず、今大変苦慮しています。病院の規模・機能に応じ、「どんな看護師を育成するのか」を考えることの重要性を再認識しました。
- 日頃、管理者として話せない悩み、事例を通じてケア検討を皆さんとすることで、悩みの共有や新たな気づき、発見に繋がります。気づきをきっかけにして、管理者として更に成長し、日々の仕事に繋がり、患者様が安心して療養出来る看護の提供に繋がっていく素敵なケア検討会だと思いました。