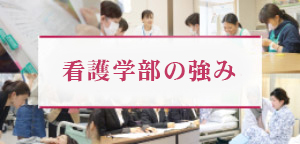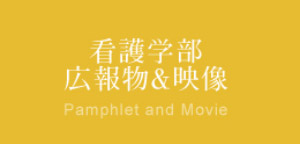本文
ケア検討会
第9回 リカレント教育(事例検討会)
【日時】令和6年2月16日(金)18時40分~20時40分
【方法】オンライン
【参加者】病院看護師7名(うち小児専門看護師1名、家族支援専門看護師4名)、訪問看護師2名、保健師1名、大学院生1名、教員4名
家族看護学領域ではコロナ禍でケア検討会の開催を見合わせていましたが、今年度より再開しました。ケア検討会は、様々な臨床の場におられる看護職の皆様と、臨床で出会うご家族へのケアについて学び合う機会として開催しています。
今回は、参加者の方から事例を提供していただき、検討しました。事例は、非代償性アルコール性肝硬変・肝不全の療養者家族で、入退院を繰り返し、徐々に身体機能が悪化しセルフケアの介助が必要となる中で、妹とその娘である姪が県外から療養者宅に移り住み、献身的に介護をして療養生活を支えている家族でした。
振り返りの焦点は、入院生活や自身が思い描く生活との乖離が深まりストレスを抱える療養者と、長期に及ぶ介護の疲れ、現状に即した療養法を模索しようとする妹との間で軋轢が生じ、妹(母親)をかばおうと姪も介護や情緒的に巻き込まれている状況に看護者としてどのような関りをもつかについてでした。まず、姉妹の関係性、そして療養者と妹と姪の三者関係について検討を行いました。療養者は、元来自由奔放な性格で、これまでも自分の意思を他者に表明してきたこと、その中で他者と軋轢が生じることもあったものの、療養者の個性と捉えて妹は見守ってきたという歴史から、姉妹が二人三脚で生きてきたことが推測されました。このような家族の歴史も踏まえて、姉妹間の軋轢が生じている背景についてさらに検討を深めました。療養者と妹には、終末期が近づいているという認識がありましたが、残された時間を自宅で身近な人へのお礼をする時間にしたい療養者と、現在の病状で自宅介護することの難しさ、経済的な問題により、姉の思い描く自宅療養の実現には限界があると感じている妹の間で過ごし方については共通認識がもてておらず、軋轢が生じていることを整理しました。また、療養者と妹との間の軋轢が、介護を共に行ってきた姪にも波及し、療養者と、妹・姪の間で対立構造が生じていると推測されました。
このような状況と、家族としての時間がもちにくい入院という環境下で、家族のみで関係の修復を図ることは難しいと考えられ、家族支援の必要性が示唆されました。看護の方向性として、療養者の高アンモニア血症などによる症状変化と徐々に低下する身体機能に合わせた過ごし方を家族で見出していくことを支援すること、そのためには、療養者の目標は何か、その目標達成が難しい場合にどのような方策があるのかを三者で話し合えるように支援することが必要と考えられました。
今回のケア検討会を通して、家族看護、在宅看護、地域看護、小児看護、成人看護など、様々な臨床経験をもつ方々の視点を含めて、家族員それぞれが置かれている状況に目をむけつつ、療養者を中心として家族内で生じている課題の焦点化と看護の方向性を見出すことにつながりました。今後も家族への支援が必要と示唆されるケースへの効果的な家族ケアを検討する機会として本ケア検討会を活用していただければ幸いです。
第8回 リカレント教育
【日時】令和6年1月19日(金)18時40分~20時40分
【方法】オンライン
【参加者】修了生3名、在学生1名、教員4名
家族看護学領域では、大学院修了生の研鑽の場として、毎月第3金曜日にWeb会議システムを活用したリカレント教育を開催しています。第8回は、「家族看護実践を豊かにするカンファレンス」というテーマでミニ講義とディスカッションを行いました。
まず、日頃、カンファレンスや事例検討会の運営や参加に関して難しいと感じることや気になっていることを出し合いました。参加者からはカンファレンスが思っているような方向性に進まない、働き方改革の流れによりカンファレンスの時間が削られ簡素化・形骸化している、カンファレンスの目的を見失わず着地点を探りながら進める難しさがある、限られた時間の中で結論を急ぐあまりプロセスを共有し楽しむということができない、などの意見が出されました。
このような課題を共有したうえで、実り多い事例検討会の条件や効果的なチームの特徴などについて文献をもとにミニ講義を行いました。今回のテーマである「実践を豊かにする」ために必要なこととして、カンファレンスや事例検討を通して新しい発見があること、そのようなディスカッションを行えるようなチームには、相互信頼や相互受容、感情レベルのコミュニケーション、目標やチームメンバーに対する強い関心などがあり、個人の目標をチームの目標に統合し自らルールを作っていくことができるといった特徴があることが示されています。
さらに、臨床心理学の領域で開発されたケースカンファレンスの手法であるPCAGIP(ピカジップ)法を紹介しました。PCAGIP法は、「事例提供者が簡単な事例資料を提供し、ファシリテーターと参加者が安全な雰囲気の中で、その相互作用を通じて参加者の力を最大限に引き出し、参加者の知恵と経験から、事例提供者に役立つ新しい取り組みの方向や具体策のヒントを見出していくプロセスをともにするグループ体験」であり、一定のルールに従ってカンファレンスを進めていく方法です。臨床の場では、ともすると、「あの時どうすればよかったのか?」「もっとできたことがあったのではないか」など、“反省会”のようになってしまいがちです。ケースの理解を深め、新しい取り組みの方策を見出すというカンファレンスの目的を明確にしてメンバー間で共有し、そのうえでメンバーの主体的な参加と相互作用を促進できるように、PCAGIP法を活用していけるのではないかと考えます。また、参加者からは、カンファレンスの場だけでなく、日頃から、「ざっそう=雑談と相談」のできるチームを作っておくことが重要という意見も出されました。
実践において、カンファレンスや事例検討会は、看護実践の質向上につながる重要な活動の一つです。忙しい中、貴重な時間を使って行うからこそ、参加してよかったと思えるようなカンファレンスであることが、最初に共有した課題の解決にもつながると考えます。今回紹介したチーム作りやカンファレンスの手法は、その一助となるのではないかと考えられました。
第7回 リカレント教育
【日時】令和5年12月15日(金)18時45分~20時30分
【方法】オンライン
【参加者】修了生2名、在学生1名、教員3名
家族看護学領域では、大学院修了生の研鑽の場として、毎月第3金曜日にWeb会議システムを活用したリカレント教育を開催しています。第7回は、小児科病棟において対応困難だった家族の事例について、ディスカッションを行いました。
初めに、事例の家族の状況を共有しました。家族には、入院している就学前の患児がおり、治療は順調に進み大きな合併症もなく経過していました。母親と父親は、交代で付き添いをしていましたが、父親は入院時から荒々しい言動がみられていました。そのため、事例提供者(家族支援専門看護師)は家族アセスメントに必要な情報収集に努めながら信頼関係を構築しようと、意図的なかかわりを行っていました。しかし、父親からの威圧的な言動やセクハラと感じられるような行動が続いていました。また、患児は、父親と同じような荒々しい言葉遣いをする様子が見られました。
父親の言動についてディスカッションした結果、父親自身の生育歴や職業、ストレス解消方法、家族の問題解決パターン、妻との勢力関係等が影響していた可能性が考えられました。そして、父親の威圧的な言動は、子どもの社会化や情緒面に悪影響をもたらす可能性もあるという意見がありました。また、小児科においては、子どもを守ろうとする保護者の行動が、時に過度な主張として医療者に映ることや、医療者は家族との関係性が壊れることを危惧し、セクハラと感じられる問題行動があっても拒否的な態度をとらない傾向にあることも父親の行動を助長させていたと推察されました。
以上を踏まえて、援助の方向性として、①威圧的な態度や過大な要求に対しては、医療者ができる事とできない事を明確に伝え、一貫した対応をすること、②スタッフはハラスメントへの対応を学び、場合によっては、組織として対応していくことも必要であることが見出されました。①については、事例提供者は実践しており、ロールモデルとなるグッドプラクティスであったと参加者より評価がありました。さらに、①の対応をとることで、一時的には家族との関係性がぎくしゃくしたとしても、長い目で見れば、患児の健康回復や成長発達の促進に向け、家族と協力しあえる関係づくりにつながる可能性があるという意見がありました。
しばしば医療者は、家族に「困った家族」というレッテルを貼ってしまうことがあります。しかし、それでは、家族の背景や家族の中で起こっていることには目が向かなくなってしまうのではないでしょうか。今回の事例からは、家族員の言動などの表面的なことにとらわれず、家族の中で起こっていることを探り、支援の方向性を検討していく重要性を再確認しました。
第4回 リカレント教育
【日時】令和5年8月18日(金)18時30分~20時40分
【方法】オンライン
【参加者】修了生5名、大学院生1名、教員4名
家族看護学領域では家族看護実践の向上を目指してリカレント教育として事例検討会を開催しています。今回は、エンドオブライフ期にあるがん患者とその家族のケアにおいて、看護師が患者の状態を判断してケアをしているにも関わらず、家族には母親をちゃんと看てくれていないと受け止められ対応困難が生じているケースについて検討しました。
まず、家族と医療者の認識について検討しました。家族は、母親の苦痛緩和を期待して入院を決めていました。しかし、コロナ禍の面会制限により、家族とスタッフが接する機会は洗濯物の受け渡し等の短い時間しかなく、家族は母親本人からの連絡で様子を知る状況にありました。このような状況下で母親からの「もうだめだ」との連絡を受けた家族は、動揺し、母親の苦痛が緩和されているのだろうかとの疑念をもち、看護師に説明を求める機会が増えていました。一方、看護師は、患者(母親)の状態を判断して疼痛コントロールや清潔ケアを調整しているにもかかわらず、ケアの意図が家族に伝わらず認識のずれが生じていました。
そこで、認識のずれが生じている背景を検討しました。一つ目は、コロナ禍の面会制限により、患者家族と医療者の間で患者に必要な医療の共通理解が十分にされず苦痛緩和について見解の相違が生じていること、二つ目は、患者の病状や今後の見通しについて家族内でどのように共有されているのか把握できないまま時間が過ぎていること、三つ目は、患者家族のケアに関する看護師のその時々の判断が他のスタッフに伝わっていないため、家族への一貫した説明が難しくなっていることなどの要因が重なっていることがわかりました。さらに、家族が現在の行動に至る背景の検討では、家族はがんの診断をうけて10年近くの治療経過を共にしており、今回の入院も症状緩和を目的としていることから、病状進行は避けられず母親の看取りが近づいていることを予期していると考えられました。死別が近づく中、家族にとって母親の苦痛緩和は最優先のニーズであるにもかかわらず、母親の言葉からは症状緩和が図られていない様子が見受けられ、医療者への不信感となり、家族に新たな苦悩が加わっているとアセスメントされました。
以上から、援助の方向性として、母親の苦痛緩和を図るために必要な治療・ケアの意図を家族と医療者で共有して家族のケア参画を促すことを見出しました。具体的には、面会制限下でも、電話、荷物の受け渡し時など意図的に家族と看護師で現状を共有して、家族が母親の様子を想定できる機会をもつこと、要所では家族が直接、母親のケアに関われるよう調整し、病状に応じて効果性を判断した上で家族の要望するケアを取り入れることなどが挙がりました。ケアの継続性では、看護師が気になった家族の言動を記録やカンファレンスなどを通して医療者間で共有して、ケアの意図を次の勤務者に引き継ぐ体制をつくることなどが挙がりました。
今回の事例検討では、患者の心身の苦痛とともに、家族が苦悩を抱えるエンドオブライフ期において、治療やケアの意図を家族と共有して援助関係を結び、限られる時間を家族として有意義に過ごすことを支える方策について学びました。検討内容が参加者それぞれの実践に応用されていくことを期待しています。
第3回 リカレント教育
【日時】令和5年7月14日(金)18時30分~20時40分
【方法】オンライン
【参加者】修了生6名、大学院生1名、教員4名
家族看護学領域では、大学院修了生を対象にリカレント教育を開催しています。第3回は、小児科病棟で、治療のため長期入院、入退院を繰り返すことを余儀なくされる子どもに付き添い、同じ病棟で過ごす母親同士の相互作用に焦点を当て、集団力学の考え方も取り入れて、相互作用の理解とアプローチ法について学び合いました。
まず、話題提供者より、子どもの付き添いをする母親の間では、互いに助け合い主体的に協働して療養に取り組む集団としてまとまりをもつ側面がある一方で、互いの心情を汲み取ることが難しくなり、葛藤や軋轢を生じる状況があることが紹介されました。そして、このような状況において、話題提供者が所属する部署では、部屋移動の要望についてのルール化、それぞれの母親への情緒的支援などにより葛藤や軋轢を緩和するアプローチが行われていました。
付き添いをする母親の集団は、子どもの病気の治療のために偶発的に同じ時期に同じ病室で過ごすことになった集団であり、家族や友人グループ、会社組織などとは異なる特性を持つ集団です。しかし、構成メンバー間には相互作用が存在するという点から一つの集団としてみなすことができ、集団力学の考え方を用いることで所属する母親たちの体験やそこで生じる葛藤や軋轢についての理解を深められるのではないかと考えました。そこで、集団力学の考え方について、集団の基本的特性、集団の次元性、集団過程、対人関係などを取り上げて教員によるミニ講義を行いながら、子どもに付き添う母親の集団について、検討していきました。
「集団過程」の視点からは、付き添いをする母親の集団にも規範や規則があり、母親にはその規範や規則に則った行動が求められ、その中で義務、役割を果たしていないメンバーがいると集団内に葛藤が生じると考えることができました。さらに、「集団の次元性」で考えると、メンバーの集団への所属願望や共通目標があると、集団の凝集性や斉一性が高まるとされています。しかし、付き添いをする母親の集団は、偶発的に形成されたものであり、“子どもの完治”という目標は同じですが、その目標達成に向けての取り組みは個々の家族のものであり、治療の効果や合併症の現れ方は個人差が大きいため、「同じ病室で子どもに付き添う母親集団」の共通目標とはなり得ません。このように、集団の凝集性や斉一性を高めて集団発達していくことの難しさがあり、葛藤や軋轢が生じやすい状況にあることが理解できました。
これらの理解をふまえて、付き添いをする母親へのアプローチとして、制限の多い病院環境の中でも、子どもが楽しく過ごすことを中心軸に共通目標を見出し協力し合い斉一性を促す、それぞれの母親の欲求を満たす情緒的支援を行う、母親の子育てについての考え方など価値観も含めて同室者を検討することで凝集性を高められるように働きかけるなど、集団過程上の軋轢や葛藤の緩和、対人関係を調整するアプローチが見出されました。
今回のリカレントでは、付き添いをする母親集団の相互作用に焦点を当てることで、集団の理解と集団へのアプローチを学ぶ機会となりました。今回の学びが、臨床でケアを発展させていく際の一助となることを願っています。
第2回 リカレント教育
【日時】令和5年6月16日(金曜日)18時30分~20時30分
【方法】Web会議システム
【参加者】修了生4名、大学院生1名、教員4名
家族看護学領域では、大学院修了生の研鑽の場として、毎月第3金曜日にWeb会議システムを活用したリカレント教育を開催しています。第2回は、修了生から提示された家族ケアの浸透における臨床での課題について、ディスカッションを行いました。
話題提供者は、緩和ケア病棟で家族支援専門看護師として勤務しており、家族看護を浸透させようと取り組んでいますが、勉強会などは開けそうにない状況です。病棟のスタッフは、「家族ケアは大事」だと思っていますが、家族全体に目を向ける余裕はなく、家族看護に積極的に取り組む様子はありません。話題提供者は、今後、どのように家族看護を浸透させていくべきか苦慮しているとのことでした。病棟では、対応が難しい家族の場合は、話題提供者や臨床心理士がその家族員を担当し、患者への対応は病棟のスタッフがすることもあります。そして、その時は、スタッフから「〇〇(話題提供者)さんが家族の対応をしてくれて助かった」と感謝されるのですが、話題提供者は、「これでいいのか」と疑問を感じています。このままでは、スタッフとCNSの看護が分業化してしまうのではないかと懸念し、今後どのようにスタッフを家族看護に巻き込んでいくかアドバイスを求めていました。
参加者からは、患者や看護師の様子、新型コロナウイルス感染症対応による影響、話題提供者のスタッフへのかかわり等について質問がありました。これらの質問に話題提供者が答えていく中で、病棟の看護師は、ベテランが多く、質の高い看護実践が行われていることがうかがわれました。さらに、病棟は、緩和ケア病棟であり、患者の特徴から、スタッフは言動に細心の注意を払って日々の看護に取り組んでいることなどが推察されました。すなわち、話題提供者の病棟では、スタッフはある程度の家族看護実践はしているが、できていることを意識化できていないと考えられました。
以上のやりとりを踏まえ、今後の取り組みとして、参加者からいくつか意見がありました。家族看護実践への意識化については、①日々のケアが家族看護につながっていることを伝える、②家族看護実践を継続することでスタッフの関心を高める、③事例検討でケアの振り返りを行う、といった取り組みが提案されました。また、病棟に家族看護を浸透させるための取り組みとしては、①病棟で影響力のあるスタッフを巻き込み、共に家族看護に取り組むスタッフを増やす、②部署で家族看護に取り組むグループを作ったり、病棟としての目標を立てて取り組んでいく、といった意見が挙がりました。
ディスカッションでは、話題提供者の「家族看護はプラスアルファなのか?」という問いかけが印象的でした。「家族看護は大切」というのは、家族看護を少しでも学んだ看護師であれば誰しも思うことだと思います。しかし、その思いを実践につなげることが難しかったり、すでに家族看護を実践しているにも関わらず、そのことに気づいていなかったりすることもあるのではないでしょうか。今回のテーマを通して、改めて家族看護の必要性やCNSの役割、家族看護を広めていく難しさについて考えさせられました。
お問い合わせ:
長戸研究室 Tel&Fax 088-847-8708 e-mail nagato-k★cc.u-kochi.ac.jp
e-mail送信時には★は@に変換をお願いします