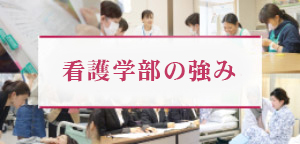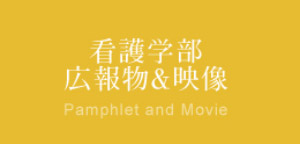本文
ケア検討会
第4回 ケア検討会(CNSの会)
日 時:令和6年3月21日(木)19:00~21:00
場 所:看護学部棟C326演習室、zoom開催
参加者:13名(精神看護専門看護師9名、小児看護専門看護師1名、教員3名)
令和5年度 第4回の精神看護学領域ケア検討会(CNSの会)を3月21日(木)にzoomで開催いたしました。今回は「CNSとしての役割開拓と実践力を高めていく方法」をテーマとし、意見交換を行いました。
まず、話題提供者(精神看護専門看護師)より、所属施設の概要と現在の活動内容について紹介がありました。話題提供者はフリーポジションのCNSではなく、一つの部署に所属しており、CNSとしての活動時間が限られた状況のなかでどのようにして所属部署での通常業務とバランスを取りながら役割を開拓していくのか、また、管理職のニーズと看護師のニーズとのずれがあることによる活動の難しさなどが語られました。
ディスカッションでは、「所属部署での活動を通して、組織の力量や状況、ニーズを把握できる」「委員会活動や看護実践にCNSが参入することの意図をチームに発信していくことが重要」などといった意見がありました。フリーポジションではなく、所属部署があることは個別ケースに対する直接ケアを展開する【実践力】を高めることや、チームの力量や組織の特徴、ニーズを捉える【アセスメント力】を高めることができる強みにもなり、CNSとしての活動の基盤となることを再確認しました。特に重要なのは、CNSにとってのクライアントは誰なのかを見定め、組織全体のニーズや看護師の力量を捉える【組織分析力】であり、クライアントとなる人とCNSとの間で目標やビジョンをすり合わせ、明確にするためには【対話力、コミュニケーション力】が重要であることがディスカッションのなかから見えてきました。そして、CNSが介入することの効果や成果を数値で見せることや、クライアントのニーズに即した成果を見せることなどといった【戦略的な成果の見せ方、成果の可視化】の重要性について確認しました。また、所属部署内での活動から、組織横断的な活動へと、活動の場を拡大するための取り組みとして、リソースナース間での連携や、各部署のキーパーソンとなる人とのつながり【協働・連携する力】についても話し合いました。
今回の参加者はCNSとしての経験年数も幅広く、組織横断的に活動されている方、所属部署を起点に活動の場を拡大されている方がおり、活動の場の違いや専門領域の違いもありました。それぞれの場でそれぞれのミッションやビジョンをもって役割開拓を行い、実践力を高めるための具体的な取り組みが語りのなかから明らかとなりました。
2024年度も精神看護学領域ケア検討会(CNSの会)は4回の開催を予定しております。精神看護専門看護師の皆様、精神看護に関心のある皆様、卒業生・修了生の皆様のご参加をお待ちしております。

第3回 ケア検討会(CNSの会)
日 時:令和5年12月21日(木)19:00~21:00
場 所:zoom開催
参加者:12名(精神看護専門看護師9名、他大学教員1名、教員2名)
令和5年度 第3回の精神看護学領域ケア検討会(CNSの会)を12月21日(木)にzoomで開催いたしました。
今回は「治療方針をめぐる倫理的葛藤への倫理調整」をテーマとし、事例を通して意見交換を行いました。専従CNSとして1年が経過したという話題提供者からは、組織の中での位置づけの変遷や、病棟や看護師との関係を構築しつつ、組織への周知を図ってきた経過について報告がありました。師長会で実践報告や問題提起をしたり、病棟別に介入目的や件数などを可視化し介入ニーズの現状分析を行った、という内容は、活動を始めたばかりの参加者にとっても、組織の中でCNSとしての周知を図っていく方策として、多くのヒントがあったのではないかと感じました。
事例は、患者や看護師が主治医と治療方針について十分な議論ができていないことにより、看護師が患者の意向が尊重されていないという倫理的葛藤を抱いている事例でした。患者は身体的な違和感により受診をし、突然末期がんと診断され、化学療法を開始したものの、せん妄を発症し化学療法が中止となり、緩和医療に移行されていました。また、せん妄症状のコントロールが困難となり、抗精神病薬による静穏化や身体拘束の指示が出、話題提供者はせん妄対応に関する相談を受ける中で、看護師の倫理的葛藤をとらえていました。
検討会では、主治医のインフォームドコンセント不足や「家に帰りたい」という患者の意向を尊重できていないと感じている看護師の倫理的葛藤(誠実や自律尊重の原則に反している)について、CNSとしてどのような介入ができるかディスカッションが行われました。
病棟に所属せず、組織を横断的に活動するCNSが、活動を始めたばかりの段階においては、看護師の力量やキーパーソンとなりうるスタッフの特定などの医療スタッフに関する情報が不十分であったり、関係性が未構築である場合があります。関係性が未構築である主治医への介入は状況をさらに複雑にする可能性もあり、まずは患者の意向に焦点を当て、看護師とともに取り組むことで、より患者や看護師との関係性の深まりにつながるという意見がありました。看護師が患者のアドボケイトとなり、患者の意向を主治医や家族に伝え、主治医からの説明を依頼したり、患者の意向の実現に向けて取り組むなど、看護師の誠実や自律尊重の原則に沿ったかかわりへの支援など、倫理的課題の解決に向けた介入について、意見交換がなされました。
今回の話題はリエゾン精神看護領域の事象でしたが、治療方針に関する調整や看護師との関係性の構築、力量の見極めなどは、CNSとして共通する課題であり、あらためて各自の倫理調整機能について振り返る機会となりました。

第2回 ケア検討会(CNSの会)
日 時:令和5年9月21日(木曜日)19時00分~21時00分
場 所:看護学部棟C326演習室、zoom開催
参加者:13名(本学大学院生1名、本学大学院修了生2名、精神看護専門看護師6名、教員4名)
令和5年度 第2回の精神看護学領域ケア検討会(CNSの会)を9月21日(木曜日)にzoomで開催いたしました。今回は「若年層の自殺企図者への介入と看護師への支援」をテーマに、CNSの役割について検討しました。
まず、話題提供者(リエゾン精神看護専門看護師)より、所属施設の紹介と若年層の自殺企図者の現状、介入した事例の紹介がありました。身体科に救急搬送されてくる自殺企図者では、若年層が増加傾向にあり、過量服薬での自殺企図も多いことから、自殺手段へのアクセスのしやすさや、自殺企図をする若者の逃げ場が少ない現状が共有されました。検討した事例も自殺企図を繰り返す若年層の患者で、患者の状態像への理解を深めるとともに、家族関係や家族内の葛藤についても着目した介入の必要性について議論しました。組織への働きかけに関しては、自殺企図を繰り返す患者に対応している救命救急の現場の看護師への支援についてディスカッションをしました。短期間の関りのなかでは患者の精神状態に著明な変化が生じないことに看護師は焦りの気持ちをもつことや、自殺企図が繰り返されることにより無力感や陰性感情が生じている現状が明らかとなりました。
以上をふまえ、自殺企図者および対応するスタッフへの支援として、以下のようなCNSの役割が検討されました。①患者が自分の思いや気持ちを表現できる相手がいることを確認し、「患者が安心できる人や場をつなぐ」役割、②自殺企図者の病理を分析し看護スタッフに伝え、対象理解を促す「現象と病理をつなぐ」役割、③医師や心理士等と情報共有し協働する「多職種につなぐ」役割、④地域の支援センターの活動や地域における仕組み作りに参画する「切れ目のない支援につなぐ」役割。これらは、専門看護師が実践のなかで展開しているLiaison(つなぐ、連携する、橋渡しをする)機能であると考えます。
その他、救急医療に携わる看護師ならではの視点や実践している看護ケアの意味を見出し保証することによって、スタッフが安心して患者に働きかけ続けることができるよう支援することも専門看護師の重要な役割の一つであることを改めて振り返る機会となりました。
次回の精神看護学領域ケア検討会(CNSの会)は12月に開催予定です。精神看護専門看護師の皆様、精神看護に関心のある皆様、卒業生・修了生の皆様のご参加をお待ちしております。

第1回 ケア検討会(C N Sの会)
日 時:令和5年6月22日(木曜日)19時00分~21時00分
場 所:看護学部棟C326演習室、zoom開催
参加者:15名(本学大学院修了生7名、他大学院修了生4名、教員4名)
令和5年度 第1回の精神看護学領域ケア検討会(C N Sの会)を6月22日(木曜日)にzoomで開催いたしました。この春、大学院を修了したC N S候補生たちも参加くださり、それぞれの場所でC N Sとしての視点を持ちながらスタートを切った様子について報告もあり、とても心強く感じました。
今回は「精神科領域における人生最終段階の意思決定支援」をテーマとし、事例や組織の取り組みについてご紹介いただき、意見交換を行いました。
まず、初めに、近年の精神病院では入院が短縮化し、外来通院で精神症状を維持しながら地域で暮らす患者が増えている一方で、入院が長期化している患者は高齢化し、身体疾患を合併し、何らかの身体的な治療を受けながら療養している患者が増えている状況があることが共有されました。そして、精神科病院では身体治療を十分に行える物理的な環境や人的環境がなく、医療者も「本当にここで患者さんが療養していていいのか」というジレンマを抱えていること、また、気がつくと患者は人生の最終段階となり、患者や家族にD N A R(Do Not Attempt Resuscitation:終末期医療において心肺停止状態になったときに、二次心肺蘇生措置を行わないこと)について考えたり、意思表示をしていただくタイミングをのがしてしまいがちであること、医療者間でもD N A Rの認識が異なること、多職種で介入していくシステムが確立されていないこと、などが語られました。その中で、C N Sはチーム内や多職種間の調整を図りながら、関わる人達の意見の集約をする役割も取っていました。
ディスカッションでは、家族、患者、医療者を含め、倫理的テーマに潜む本音と建前が見え隠れするコミュニケーションの難しさや、組織によって提供可能な医療の違いなどについて意見交換が行われました。
参加者の経験もC N S候補生から10年以上の経験者までと幅広くありましたが、倫理調整の基本的な介入ステップの再確認となったや、看取りなどは体験したことはなかったが、徐々に自組織にもそうした課題が迫ってくる可能性があり、考えるよい機会となったなどの感想をいただきました。精神科医療においても、身体的医療や終末期ケアが無関係ではなくなっている状況について、再認識する機会となりました。
今年度もWeb開催で行っていきます。本学の卒業生だけでなく、C N S同士のつながりでネットワークも拡がり、活性化しています。次回は9月に開催予定です。精神看護専門看護師の皆様、精神看護専門看護師を目指そうと考えている方、卒業生・修了生の皆様のご参加を心よりお待ちしています。