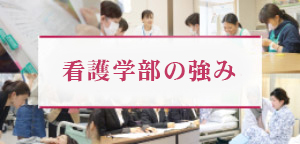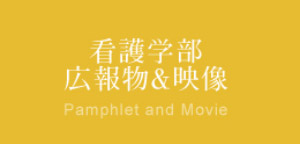本文
令和6年度 リカレント&交流会
【テーマ】キャリア・プラトーって悪者?
【日時】 令和7年2月9日(日曜日)13時30分~15時30分
【方法】 Web会議システム
【参加者】参加者13名:修了生6名、大学院生4名 教員3名
今年度のリカレント教育では、「キャリア・プラトーって悪者?」をテーマに開催しました。
話題提供者は、看護管理領域の大学院院生で4日後に控えたEAFONS2025(http://eafons.org/)で発表する一般演題「The Relationship Between Career Plateau and Career Self-Reliance Among Mid-Career Nurses(キャリア中期看護師のキャリア・プラトーとキャリア自律の関係)」を紹介することから議論が始まりました。
この研究における看護職のキャリア・プラトーとは、「組織内において、現在以上の職業的発達が困難であると自覚している状態」と定義されていますが、キャリア・プラトーには、ポジティブな側面もあるのではという問いを明らかにすることを目指した研究です。
話題提供者からは「看護の魅力を見出すための具体的な支援はどのようなものがあるか?」、「キャリア・プラトーをきっかけに自律的に行動する可能性が実証されたが、実践現場でキャリア・プラトーに直面している看護師にどのような関わりをしたらよいか?」の2点について、修了生や先輩に助言が求められました。現場の看護管理者の立場にいる先輩からは、多様な働き方を支援、活用できる福利厚生等の支援制度を紹介、看護スタッフの将来を見据えた役割を付与、スタッフ一人ひとりの強みを引き出し信頼すること等、キャリア支援制度における透明性と公平性のバランスをとった運用について、具体的な示唆に富む議論が交わされました。参加者ひとり一人が自分自身の経験をふりかえり「キャリア・プラトー」と向かい合う貴重な機会となりました。
私自身も過去に看護師として勤務を継続していく中で、キャリア・プラトーを感じた時、「そろそろ後輩や新人育成に力を注いでほしい」と上司より頼りにされたことで、仕事や看護の学びに意欲的に取り組めたことをこのリカレント教育の場で想起しました。今回初めての参加でしたが、明日からの看護の実践現場に活かせられる意見交換の場であったことを実感しました。
報告者:安岡 愛(高知県立大学看護学研究科)

令和6年度 第2回ケア検討会
【テーマ】プラチナナースがイキイキと 働き続けられるための体制づくり
【日時】令和6年10月18日(金曜日)18時〜20時15分
【方法】ハイブリット(対面・オンライン会議)
【参加者】参加者19名:医療関係者12名、大学院生5名、教員3名
(医療関係者のうち1名は大学院生と重複)
本年度2回目のケア検討会は「プラチナナースがイキイキと 働き続けられるための体制づくり」というテーマで、管理職で定年を迎えた後、一般職として継続勤務をすることの難しさについて事例提供者からの現状の報告から議論が始まりました。
まず、管理職が定年後に一般職員として働き続ける中での役割葛藤やモチベーションの低下の原因について様々な質疑応答がありました。本人の思いとは別のところで、組織や社会制度を基盤とした病院のルール(処遇や配置等)に従って、就業を継続していることと同時に、定年後に評価される機会が減少することも要因の一つではないかという意見が交わされました。
また、管理職のプラチナナースが一スタッフとして働く場合には、患者対応には問題がなくとも技術面に不安があることも多く、個々のナースの資格やスキルを活かした部署に配属できる配慮やプラチナナースを支える周囲のスタッフの理解やお互いに協力し合える職場風土を育むことの重要性について意見が出されました。その他、ディスカッションの中では、管理職としてのスキルを活かして、次世代の管理者の育成という役割を付与することやプラチナナースのメンタルケアの場としてプラチナナース同士が語り合い、研修する場を設けることが必要では?という意見もありました。そして、今後は更に労働力人口減少が見込まれる医療現場において、誰もがいずれプラチナナースになるという視点をもち、早い段階から準備を進める必要性についても確認されました。
最後に、事例提供者から、今回の検討会を通して、他施設でも同じような悩みを抱えていることが共有でき、個々のナースのモチベーションを保つためのヒントやこれからプラチナナースがイキイキと働き続けるための体制づくりに向けた一助となったことが共有され、修了となりました。
【参加者のアンケート用紙より】
・同じような課題を持つ他施設の状況や体制を知ることができ、とても参考となった 。
・プラチナナースの悩みやプラチナナースを支援する管理者の話が直接聞けたことがとても貴重な経験になった。
・今後、更に増え続けるプラチナ世代。活躍促進における場の提供や活躍を活かす側と活かされる側の現実問題をどこも抱えている事を知ることができました。また、セカンドキャリアだけを考えるのではなく、定年を迎えた後の再就職における労務管理や賃金等具体的に考えて行動しなくてはいけない事も学ばせて頂きました。
・事例提供のお話を頂き、参加させていただきました。自施設での課題に対して、他施設の状況や取り組み、また文献のご提示を頂き、大変参考になりました。

令和6年度 第1回ケア検討会
【テーマ】病棟再編における中間管理職のジレンマ〜職務満足度、患者満足度の高い部署を目指した取り組み〜
【日時】令和6年6月14日(金曜日)18時〜20時30分
【方法】オンライン会議(ZOOM)
【参加者】参加者32名(外部参加者23名、大学院生6名、教員3名)
【報告者】看護研究科 看護管理領域 博士前期課程 佐條 萌梨
「病棟再編における中間管理職のジレンマ」というテーマで開催しました。
今年度から病棟が再編されたことによる中間管理職が抱えるジレンマについての情報提供がありました。話題提供者は、スタッフから中間管理職に昇進と同時に現在の病棟へ異動しています。その病棟はCOVID-19への対応を行った病棟です。異動当初はCOVID-19専門病棟として未曽有の事態に向き合ったスタッフの話を、傾聴することに努めています。スタッフと丁寧に関わろうと意識してコミュニケーションを取るようにしていました。今年度、病棟再編により、当該診療科に対応した部署作りが行われています。しかし、その過程で患者・家族を中心に考えるのではなく、看護師が動きやすいことを最優先にする傾向や関わりが難しい患者さんを避けようとするスタッフの発言が気になりました。スタッフは以前の病棟と比較する発言が目立ち、環境の変化に気持ちがついていけていないように感じていることが語られました。このような状況において、経験豊富なスタッフの強みを活かした看護が提供され、患者満足度の高い部署へ変革していくにはどのような対応をしたら良いのかについて検討していきました。
COVID-19という未曾有の事態の中、当該病棟に配属となった看護師が経験した心理状態や看護の特徴について共有しました。スタッフはCOVID-19の最前線で働くことへのプライドや誇りを持って看護をしていたこと、そして管理者が前面に立って可能な範囲で配慮が行われていた一方で、COVID-19専門病棟へ行く、COVID-19専門病棟から離れることに衝撃を感じる看護師がいたことなどが共有されました。COVID-19 専門病棟における看護師の体験の理解は、看護師同士であっても簡単な事ではないことが共有されました。現在は、病棟再編や診療科の再編により様々な変革が求められており、COVID-19 専門病棟での未曽有の事態への対応から絶え間ない変革が続いているとも考えられます。また、ベテラン看護師のスキルを活かすことができるよう、どのように環境を整え支援することができるのかについても議論されました。変化や変革に不安や抵抗感を持つのは当たり前のことであり、その不安や反論を受けとめつつ、誰のための変革なのかについて気づくことができるように関わることが必要という意見がでました。
話題提供者からは、これまでの経験を前向きに捉え、今後のスタッフへの関わり方についてヒントを得ることができたという意見が聞かれました。参加者は、コロナ対応のため調整を行った経験、コロナ対応を行ったスタッフへの対応を行った経験、あるいは何らかの変革を推進した経験を振り返ることができたという意見が聞かれました。また、今後経験するであろう病棟再編や変革について、スタッフ支援についていろいろな方の意見を聞くことができ、共通する意見や異なる意見から学ぶ経験になったという感想が聞かれました。また、日頃研修に参加するには1日がかりになりがちだが、オンラインでつながる場があることが有意義なことであるという声も届けられました。