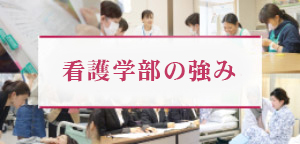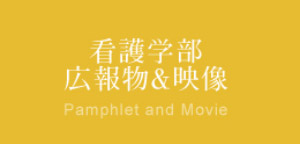本文
ケア検討会
第4回 ケア検討会(CNSの会)
日時:令和7年3月13日(木)19:00~21:00
方法: Web開催
参加者:11名(精神看護専門看護師7名、小児看護専門看護師1名、本学教員3名)
令和6年度 第4回の精神看護学領域ケア検討会(CNSの会)を開催しました。テーマは「精神看護CNSの救急病床における役割開発を考える〜認定から1年を振り返って〜」とし、専門看護師認定から一年が経過した修了生に話題提供をいただきました。
話題提供者は、リエゾン精神看護専門看護師として救命救急病棟のなかで活動をしていました。それまでフィールドとしていた精神科とは優先順位や時間の流れも異なる救命救急病棟のなかで、病棟業務を行いながらCNS活動を展開することは、自身が想像していた専門看護師像とは必ずしも一致しておらず、葛藤を抱きながらの実践であったのかもしれません。しかし、参加者間でのディスカッションでは、救命救急病棟のスタッフが話題提供者に自身の怒りやストレスの蓄積を吐露するようになっていること自体がスタッフに対する情緒的支援であり、相談先としてのリソースになっていることを確認しました。また、過酷な現場のなかでも患者・家族との対話を重ね対象理解を深めようとするスタッフの力や強みを話題提供者は捉えていました。そうした現場の力を個々のスタッフにフィードバックしていくことが、チームの力の底上げにつながっているようでした。こうした協働のための土台作りを丁寧に行うことがチーム・ビルディングにつながり、スタッフのモチベーションを維持・向上するうえで重要な役割を果たしているとも捉えられました。また、救命救急病棟という身体ケアが主体となる場においても精神ケアは展開されており、日常看護業務を通してCNSの実践を可視化することで、モデリングの役割を果たし、スタッフへの教育的効果や倫理調整等につながることを再確認する機会となりました。
精神看護学領域ケア検討会(CNSの会)は令和7年度も6月、9月、12月、3月の計4回の開催を予定しております。実践事例を客観的に分析し、CNSの役割機能を捉え直すことや、組織分析を行いケアの可能性を検討することなどを通して、参加者の皆様とともに精神看護について考える機会としていきたいです。
専門看護師の皆様、精神看護に関心のある皆様、卒業生・修了生の皆様、領域を問わずご参加をお待ちしております。

第3回 ケア検討会(CNSの会)
日時:令和6年12月19日(木)19:00~21:00
方法: Web開催
参加者:12名(精神看護専門看護師8名、本学修了生1名、本学教員3名)
令和6年度 第3回の精神看護学領域ケア検討会(CNSの会)は、「CNSの抱える陰性感情にどう向き合うか」をテーマに参加者間で意見交換しました。
CNSとして、組織と協働していく中では、CNSと依頼者(個人あるいは組織)との間で、価値観の相違や期待のずれが生じ、互いの意向がかみ合わない中で、時に陰性感情が生じることがあります。今回はCNSが陰性感情を抱いた場面に関する話題を提供していただき、参加者間で場面を振り返り、組織とCNSとの中で起こっていたことを紐解いていきました。
ディスカッションを通して、組織の状況や組織とCNSの関係性、CNSに対する組織の期待など、客観的な視点で対象組織をアセスメントすることができ、陰性感情を超えて、組織に参入する方策について建設的な議論を交わすことができました。また、組織のなかでのCNSの立ち位置や役割を明確にすること、変革推進者(Change agent)としてのCNSのあり方について考える機会となりました。
次回の精神看護学領域ケア検討会(CNSの会)は令和7年3月に開催予定です。精神看護専門看護師の皆様、精神看護に関心のある皆様、卒業生・修了生の皆様のご参加をお待ちしております。

第2回 ケア検討会(CNSの会)
日 時:令和6年9月19日(木曜日)19時00分~21時00分
方法: Web開催
参加者:16名(本学大学院生1名、本学大学院修了生1名、精神看護専門看護師10名、他大学教員1名、本学教員3名)
令和6年度 第2回の精神看護学領域ケア検討会(CNSの会)は、精神科病院の外部コンサルタントとして活動している精神看護専門看護師から、「外部のリソースとしてCNS活動を実践する」をテーマに話題提供いただき、CNSの役割について参加者で検討しました。
活動当初は、外部のCNSが入ることに対する抵抗もあり、スタッフからの直接的な依頼は少なく、病棟管理者からの依頼に応える形で役割を展開していました。具体的な活動の一例として、感情コントロールの難しい発達障害をもつ患者への実践が紹介されました。CNS として患者本人の状況、家族の状況、医師や病棟看護師といった患者を取り巻く医療チームの状況を分析的に捉え、患者との直接的な対話を通して見えてきた反応や、患者の語りを看護チームに投げ返すことでチームの対象理解を促すとともに、看護チームが患者への関りに関心を向けられるよう支援したことが語られました。また、患者の転棟に伴い、CNSが介入する病棟が変わると、CNSに対する病棟スタッフの受け入れや反応が異なり、CNSが外部リソースとしての活動を展開するうえで、病棟管理者の考え方やチームの力動が推進力にも抵抗力にもなることを改めて理解することができました。
ディスカッションの後半では、外部リソースとして組織に参入する際の配慮について情報交換を行いました。例えば、病棟内のパワーバランスを考慮し、CNSの見立ての伝え方を意識すること、依頼者を特定したうえで依頼者とともに目標の共有化・明確化をはかり成果を示すこと、病棟スタッフの困りごとに対応しながら関係性をつくり、活動の裾野を広げていくことなど、様々な取り組みを行っていることが分かりました。参加者それぞれの臨床現場での取り組みや、部署を超えて横断的に働きかける際の難しさや工夫点などが意見交換され、実践的な学びを得る機会となりました。皆様、ご参加ありがとうございました。
次回の精神看護学領域ケア検討会(CNSの会)は12月に開催予定です。精神看護専門看護師の皆様、精神看護に関心のある皆様、卒業生・修了生の皆様のご参加をお待ちしております。

第1回 ケア検討会(C N Sの会)
日 時:令和6年6月20日(木曜日)19時00分~21時00分
場 所:zoom開催
参加者:11名(精神看護CNS・修了生・卒業生9名、教員2名)
県内・県外から精神看護CNS、修了生、卒業生など11名(うち本学教員2名)が参加し、修了生が現在取り組んでいる「精神科クリニカルパス(セルフケアOATユニット)」について検討を行いました。「精神科クリニカルパス(セルフケアOATユニット)」は、一般的なクリニカルパスのように時間と行動によって統制される形式ではありません。看護の視点を可視化し、患者のケアに活用しようとする試みです。具体的には、普遍的セルフケア要件に焦点をあて、それぞれのレベルに基づいたケアを遂行できるようなツールを目指し、取り組んでいるものです。普遍的セルフケア要件は、アンダーウッドモデルの5要件に「病気とのつきあい」をプラスし、5段階のレベルそれぞれに「定義」「アウトカム(O)」「アセスメント(A)」「タスク(T)」が設定されております。また、「安全を守る力」については、入院時に把握する他のチェックリスト(転倒・転落、自殺、誤嚥など)と齟齬が生じないように、別途3段階のレベルで評価できるように工夫されています。
本日は、「精神科クリニカルパス(セルフケアOATユニット)」の開発の経緯を踏まえ、臨床現場に導入するにあたっての課題について検討(プログラム中心のコンサルテーション)を行いました。それぞれのCNSが自身の実践事例を想定しながら、またこれまで新たなプログラム導入時に学んできた経験を擦り合わせながら、検討を進めていきました。話題をご提供いただいた修了生やCNSからは、本会での検討内容を踏まえて見えてきたいくつかの課題に取り組み、精神科救急病棟での導入に向けてチャレンジしていきたいという気持ちが高まったようです。
高知県立大学精神看護学領域では、今年度もCNSの会を開催します(9月・12月・3月)。今年度も実践事例の検討、CNS教育、プログラム導入の検討など様々な課題に取り組んで参ります。ぜひ、みなさまのご参加をお待ちしております。

※ はじめて参加をご希望される方は、田井研究室(taim@cc.u-kochi.ac.jp)までご連絡ください。
高知県立大学看護学部精神看護学領域一同
交流会
令和6年度 精神看護学領域交流会を開催しました。
日 時:令和6年6月1日(土曜日)19時00分~21時00分
場 所:国際医療福祉大学成田キャンパス(千葉県成田市)
参加者:7名
2024年6月1日から2日間にわたり、日本精神保健看護学会第34回学術集会が国際医療福祉大学成田キャンパス(千葉県成田市)で開催されました。学会では、本学の修了生や教員によるシンポジウムやワークショップも開催され、精神科臨床における看護外来の専門性について参加者とともに考えました。
1日目の夜には精神看護学領域の交流会を開催しました。対面での交流会は数年ぶりの開催となり、少人数ながら近況を報告しあい、楽しい時間を過ごしました。