本文
【研究者情報】 白岩 英樹
| 職位 | 教授 | |
| 役職 | ||
| 所属 | 文化学部 文化学科、大学院 人間生活学研究科 | |
| 教員紹介 | 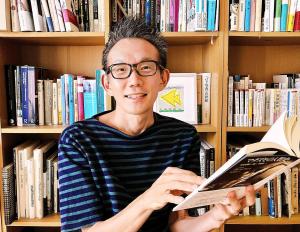 |
若い友人たちへのエールを込めて! Q1.文化学部はどのようなひとに向いていると思いますか? A1.まず、特定の文化分野に強烈に魅かれているひと。それに加えて、ちょっとでも生きづらいなと感じたり、現行の社会や価値観になにかしらの違和を感じたりしているひとです。生きづらさは皆さんひとり一人に秘められた潜在的な力(ポテンシャル)の現れにほかなりませんし、違和感は社会の別の可能性(オルタナティヴ)を構想し、新たな価値観を創出する強大な推進力になるからです。 Q2.文化学部ではどのようことが学べるのですか? A2.ぼくの専門は詩や小説、写真や彫刻といった芸術分野です。それらはあくまで虚構にすぎません。が、だからこそ現実社会へのカウンターという、もっともラディカルな役割を担うことができるのです。すぐれた作品には、「いま・ここ」とはまったく別の「フレーム」が起爆装置のように組み込まれています。それらを内に取り込むことで、ぼくたちは現実のありようを”one of them”として相対化することができる。別の可能性(オルタナティヴ)の構想と実現という、社会の新たな枠組み形成(リフレーミング)はまさにそこから始まるのです。 Q3.受験生へのメッセージをお願いします。 A3.今日、人類は地球規模の災害やパンデミックを経験し、現行の「フレーム」では太刀打ちしようのない危機に見舞われています。そろそろ、「いま・ここ」でしか通用しない価値観から脱け出す好機でしょう。皆さんがわずかなりとも感じている生きづらさや違和は、その時宜を察知している証なのです。人類の遺産たる多種多様な文化をベースに、皆さんと潜在的な力(ポテンシャル)を引き出し養いあい、大胆な新たな枠組み形成(リフレーミング)を試み、それぞれの別の可能性(オルタナティヴ)を創出する。そんな出逢いが実現することを愉しみにしています。 |
| 学位 | 博士(芸術文化学)(大阪芸術大学、2011年) 学士(文学)(早稲田大学、1999年) |
| 学歴・職歴 |
【学歴】 【職歴】 |
| 専門分野 | 比較思想、比較文学、比較芸術 |
| 所属学会 |
日本アメリカ文学会 |
研究SEEDS
研究テーマ
・コロニアリズム/ポストコロニアリズム
・脱植民地化におけるシティズンシップと市民的抵抗
・ジェンダー・スタディーズ
研究概要
「アメリカ文学の父」と評されながら、人間の弱さ/脆さを徹底して見つめたS. アンダーソン、「超越主義(Transcendentalism)」を提唱し、自ら「アメリカの学者」となったR. W. エマソンや、自らの存在を賭して「市民的抵抗」を実践したH. D. ソロー、エマソンの思想を「国民的詩人」として表現したW. ホイットマンへの関心を起点に、自他の関係性やケアの研究、翻訳を始めました。
現在は以下の1-5の問題をアメリカにまつわる思想・文学的な観点から考察しつつ、それらを表現するのに相応しい様式の創出を試みています。
1.この世界にはなぜ不条理な痛苦が存在するのか
2.そうした苦境がいかに社会構造化されているのか
3.いかにしてそれらの窮境から脱却しうるか
4.逃れえない痛苦とどのように共生しうるか
5.3と4とのあいだに横たわる埋めがたい溝をどう見きわめるか
相談可能な領域
以下の1-3の問題を、アメリカの思想や文芸の観点から共考することが可能です
(最近は土佐の文人・思想家たちへの関心がますます強まっています)。
1.国家/共同体/個人および人為的なカテゴリー間における支配/被支配の構造
2.人権の回復や「自由」の獲得における市民の役割および不服従の手段と意義
3.ジェンダーにまつわる差別と抵抗運動
キーワード
植民地主義、市民的抵抗、自他、差別、非人間化、アイデンティティ、声、相互扶助、アナキズム、表現、ケア
関連SDGs (関連性の高い順)




しかしながら、以下への視座を養うことが人文学の務めだと考えています。
1.SDGsがどのようないきさつで、いかなる人物や組織によって、いまの枠組みに収められたのか。
2.実際に効果が生じている分野と、まったく奏功していない領域は、どこにあるのか。
3.SDGsでは変えようのない「悲劇」はどこに潜在するのか。また、それを回避するにはどうすればよいのか。
研究業績
主要研究論文等
(2021年以降)
【論文】
・「本の名刺:『ぼくらの「アメリカ論」』 」、『群像』 80(1)、講談社、pp. 258-260(2024年12月6日)
・「仔猫も家も大学も」、『群像』 79(10)、講談社、 pp. 273-275(2024年9月6日)
・「今日を生きるおまじない」、『ユリイカ』 56(9)、青土社、pp. 63-73 (2024年7月31日)
・「散歩する詩人たち」、『ユリイカ』 56(7)、青土社、pp. 137-148(2024年5月27日)
・「解説:ヘイトの時代を生きた「立体的人物」たち 」、ビル・ブライソン『アメリカを変えた夏 1927年』伊藤真訳、白水社、pp. 583-587 (2024年8月30日)
・「書評:革命の始源(佐峰存『雲の名前』) 」、『現代詩手帖 』67(1)、思潮社、p. 129( 2024年1月)
・「シンポジウムの重さは測れるか?――Smokeを手がかりに」、『地域創造学研究(奈良県立大学研究季報-34-2)』、pp. 50-54 (2023年10月31日)
・「民主主義の種火――フレデリック・ワイズマン『ボストン市庁舎』をアメリカ思想から読む」、『人文×社会』第8号、
pp. 229-243 (2022年)
・「アメリカのかそけき声を聴くための20冊――自他の脆弱性を手がかりに」、『文化の思索』、高知県立大学文化学部、pp. 109-134 (2021年12月25日)
主な著書
(2020年以降)
・共著『ぼくらの「アメリカ論」』 、青木真兵/光嶋裕介/白岩英樹、夕書房、京都( 2024年10月23日)
・単著『講義 アメリカの思想と文学――分断を乗り越える「声」を聴く』、白水社、東京(2023年)
・分担執筆『Clinical Scenes』、Cengage Learning、東京-Boston, U. S. (2020年)
・単訳:キャスリーン・マシューズ、アリソン・デクスター、『祝福の種:新しい時代の創世神話』、作品社、東京(2020年)
主な受賞歴・特許など
・・2025年3月:第34回(2024年)高知出版学術賞 特別賞, 『ぼくらの「アメリカ論」』夕書房, 公益財団法人高知市文化振興事業団 (青木真兵, 光嶋裕介, 白岩英樹)
主な社会貢献
・2025年1月 『ぼくらの「アメリカ論」』(夕書房)刊行記念:僕らにとって「アメリカ」とはなんなのか? (白岩英樹, 光嶋裕介, 青木真兵, 平川克美)於 東京・隣町珈琲
・2024年11月 高大連携事業:高知県立清水高等学校「人間はなぜ生きるのか 」
・2024年10月 『ぼくらの「アメリカ論」』(夕書房)刊行記念トークイベント:「『ぼくらの「アメリカ論」』をめぐって 」青木真兵, 光嶋裕介, 白岩英樹, 高松夕佳(於 南国市:食事と図書 雨風食堂)
・2024年8月 高知近代史研究会-第118回研究会:講演「土佐の民権、米国の「革命」 」於 高知近代史研究会・高知市立自由民権記念館
・2023年12月 夜學2023:本山町・高知県立大学 公開講座「人間はなぜ生きるのか」
・2023年12月 高知工科大学 理工学群「理工学のフロンティア」講演「異端精神の系譜――土佐からアメリカへ」
・2023年10月 高知市民の大学「アナキズムを問い直す――土佐からアメリカへ」
・2023年 7月 高大連携事業:土佐中学校「われわれはなぜ「読む」のか、「学ぶ」のか」
・2023年 5月 高知 蔦屋書店 × NPO地域文化計画 トークイベント 「声」と「土着」をめぐって(『講義 アメリカの思想と文学』出版記念 対談:白岩英樹 × 青木真兵)
・2022年10月 高大連携事業:高知県立春野高等学校「われわれはなぜ「読む」のか、 「学ぶ」のか?」
・2022年 5月 高知 蔦屋書店 × NPO地域文化計画 トークイベント 「アメリカ思想から読む『ボストン市庁舎』」
・2021年11月 高大連携事業:高知県立高知国際中学校「『自分自身』の探し方――ポートレート写真に見るアイデンティティ」
・2021年 8月 教員免許状更新講習(英語)
・2021年 5月 夜學2021:本山町・高知県立大学 公開講座「われわれはなぜ「読む」のか、 「学ぶ」のか?」
・2020年10月 高大連携事業:高知県立安芸高等学校「コロナの時代に大学で学ぶこと:文化学的観点から」













