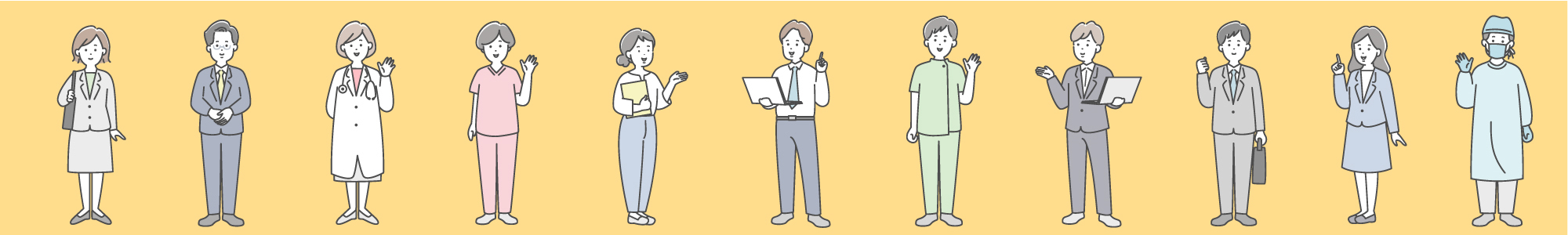本文
過ごした時間はかけがえのない宝物、 自分にとって高知は、第二の故郷!
長屋春香さんは、社会福祉を学ぶために北海道から高知県立大学へ。人との出会いに感謝しながら過ごした高知での4年間は、かけがえのないものだったと話します。現在は、社会福祉の知識を活かして、地元・札幌でソーシャルワーカーとして働いています。

【Profile】
長屋 春香 さん
勤医協札幌病院 医療連携・患者支援センター ソーシャルワーカー
2020年 高知県立大学社会福祉学部社会福祉学科卒業
Q1 本学に進学を決めた理由を教えてください。
親元を離れて生活がしてみたいと思い、学びたい分野の条件も合った高知県立大学へ進学しました。
地元・札幌で高校生活を送り、卒業後の進路は“大学に行く”ということは決めていたものの、何がやりたいのかが定まらず、両親から一年、進路について考える時間をもらいました。
まず自分のなかで第一条件だったのが、“親元を離れて生活すること”。ずっと住んでいた札幌は、便利なものに溢れている都市なので、そうではない場所で自立した生活を送ってみたい、という希望がありました。
その上で、何について学ぼうかと検討しながら過ごしていると、浪人生活も半年を過ぎたある日、ついにそのテーマに出会ったんです。
きっかけは、偶然観ていた身体障害者に密着するというT V番組。それは、実際に目の当たりにしたことのなかった世界で、「障害のある方はどうやって生活をしているのか」「周りにいる人たちはどういう人たちなのか」そんな疑問を感じたのが、今思えば社会福祉の道への入り口でした。芽生えた疑問に対して、自分で調べたり、医療関係者だった家族と話し合っているうちに“社会福祉”を学びたい、もっと知りたい!という思いが次第に大きくなりました。社会福祉を学べる学校、を求めて見つけた高知県立大学。札幌からだと乗り継ぎしないと行けない不便さが、求めていた条件に合っていて、行ったこともなく、自分のことを誰も知らない土地へ飛び込んでみたいと思い、選びました。
Q2 どんな学生生活でしたか?
札幌に戻った今も、もっとやりたかった!と思えるあっという間の4年間でした。
同期の学生は高知県出身が多く、四国の他県、九州、関西、関東と各地から集まっていました。北海道からはもちろん私だけで、知り合いが誰一人いない状況での人間関係作りは新鮮なことばかり。自分が住んだことのない土地の文化や方言に触れ、まさに異文化交流的な毎日が本当に楽しかったです。大きい大学と違い県立大学は少人数制だったので、担任ではない先生も学生の名前を一人一人覚えてくれていて、相談しやすい雰囲気で誰とでも挨拶ができる、そんなアットホームな空間がとても好きでした。
大学ではボランティア団体や防災サークルなどで活動していました。アルバイトも塾講師、放課後等デイサービス、ホテル、花屋など様々な経験をし、対人関係など学ぶものもありました。ここで言い切れないものもたくさんで、興味のあることはとことんやってみようと挑戦した4年間でしたね。

(写真)学生時代、4年間一緒に過ごした仲間と仁淀川にて。
―印象に残っていることはなんですか。
“人との出会い”が一番です!
初めて高知に足を踏み入れた入試の時、感じたのは「人が温かい」というのが第一印象でしたが、それは最後まで変わることはなかったです。
高知で最初に友達になったのは、新生活を始める上で必要だった家具を買いに行ったお店のおばちゃん。一度家具を購入しただけでしたが、それからも親交が続いて、手作り料理を振舞ってくれたりと卒業まで気にかけてくれました。「おせっかいやきね」と笑って言っていましたが、人とのつながり自体が希薄になってきているなかで、そのように嬉しいおせっかいをかけてくれること自体が初めての経験で、とても嬉しかったことを今でも覚えています。同じアパートのおんちゃん(高知の方言でおじさんの意味)も素敵な人で、わざわざ窓を開けて声をかけてくれたりと、高知で出会った方々の温かさを感じ続け、高知県が大好きになった理由の一つです。今となっては会いたい人が沢山います。高知は私の第二の故郷だなあと思っています!
Q3 なぜ、札幌でソーシャルワーカーをしようと思ったのですか?
高知での就職も考えましたが、“ただいま”を言ってくれる家族の住む札幌で、自分の力を試してみたいと思いました。
就職を考えたとき、どう働きたいかがまだ決められていなかったんですが、3回生の時の実習前にそのことをゼミの先生に相談すると「病院実習だと様々な機能や役割を学べる、急性期では多忙と言われているけど、今後に役立つ経験になると思うよ」と言葉をもらったので、実習は救命救急のある大きな病院に行きました。実習は辛いこともありましたが、ソーシャルワーカーの立ち位置や役割を知ることができ、まずはソーシャルワーカーとして病院で働こうと決心しました。
高知での就職も視野には入れましたが、4年間高知で生活した中で「おかえり」と言われないことがすごく寂しいと実感してしまいました。就職してもっと多忙になったときに同じ状況だと、自分は潰れちゃうかも知れないと思い、札幌に帰ることにしました。それにソーシャルワーカーとして働くことを考えたとき、社会資源が多い場所で、自分がどのように考え、力を発揮できるのか確かめたかったというのも札幌に帰った理由の一つです。今働いている病院は、法人が大事にしているものと、ソーシャルワーカーの倫理綱領がとても近く、実際に見学に行った際にも働きやすさを感じたため、就職を決めました。
Q4 現在のお仕事について教えてください。
回復期病棟で入院している患者さん一人一人が安心して日常生活に戻れるように、多職種と連携して退院支援を行っています。
就職して今年ではや5年。途中、部署異動もありましたが、今は回復期病棟専従のソーシャルワーカーとして2年目を迎えました。病棟業務としては、急性期から回復期に移動してきた患者さんが、安心して在宅に戻れるように一人一人に寄り添った退院支援を行っています。患者さん自身とお話しすることも多いですが、高齢で認知症のある方や意思疎通が難しい方もなかにはいるので、ご家族の方とコミュニケーションをとることも多いです。この仕事は患者さんやそのご家族との関係構築が不可欠ですが、一人のクライエントに対して多職種と連携することで支援も展開されていきます。大学の先生に言われた言葉で今でも覚えているものがあって、「今やっていること、考えていることの“その先”には何があるのか、ちゃんと見えているのか?」という問いかけ。関係性を築いたり、他職種との集まりでソーシャルワーカーとしての意見を共有する過程では、たくさん悩むこともあります。ただ、私の言動の先には患者さんの生活があることを忘れてはならないこと、大学で教わったことは今でも大切にしています。そのおかげで、他職種とコミュニケーションをとることは入社当時から臆せず行っています。大学で経験していなかったら今の自分はいないだろうな、と思うことが、仕事をしていてたくさんありますね。
大学で取り組んだ研究が、病院を変えていく活動につながっています。
今働いている勤医協札幌病院は「無差別平等の医療と福祉」の実現を掲げる全日本民医連という全国に組織する一病院です。数年前、道外のある病院の医師がLGBTQ当事者として声をあげ、誰もが安心して受診でき働くことのできる医療機関作りを目指そうと啓発活動をされていることを知りました。
私は大学の卒業研究で、当時理解を深めたかった“LGBTQ”について研究をしていました。就職活動の際に、病院の受付の人の制服や医療従事者の制服に違和感を抱きましたが、就職直後は業務を覚えるのに手一杯となってしまい、自分から声をあげることはできませんでした。ですが、同じように問題意識をもつ他職種の仲間がいたことが分かり「一緒にやろう!」と私たちのできる活動を始めました。LGBTQ+を学ぶ上では一人ひとりが自分事として考えることができるようSOGIE※の視点を大切に、まずは知ることから学習会を開いたり、関連イベントに参加することもしています。そういった活動の背景にある、自分の知見や知識、知るということを大学では自分らしく深めることができ、本当に良かったと振り返っています。
※SOGIE:多様な性のあり方を考える4つの視点(出生時に割り当てられた性;Sex Assigned at Birth、性的指向;Sexual Orientation、性自認;Gender Identity、性表現;Gender Expression)のうち、性的指向・性自認・性表現の英語表記の頭文字などを合わせた、誰もがもつ性の要素のこと。

(写真)札幌レインボープライドパレードに参加したときの様子。
後輩のみんなにエール!
ソーシャルワーカーという仕事が、みんなの選択肢の一つになってほしい!
ソーシャルワーカーという仕事自体、以前より知られてはきましたが、まだまだ認知度が低い職種だと思います。私も社会福祉を学びたい!と思って大学に入ったので、ソーシャルワーカーになるとは思ってもみませんでしたが、今はソーシャルワーカーの視点で人と関わる面白さや日々の仕事にやりがいも感じられ、周りからは「天職じゃない?」と言われることもあります。
世の中にはいろんな仕事がありますが、ソーシャルワーカーのように人の人生に寄り添い関わることは、そう多くない職業ではないかと思います。自分自身が社会資源になって、誰かの人生の一翼を担える。その人らしい生活が送れるお手伝いができるのはやりがいもあり、人のために何かができる素敵な仕事だと思います。
ソーシャルワーカーという仕事が、一人でも多くの人に伝わると嬉しいです!
※所属・職名等は掲載時点のものです。