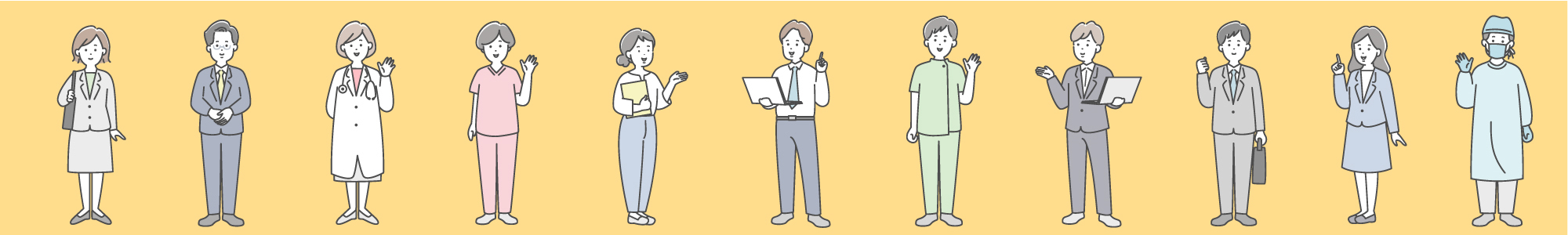本文
大学で出会った人々の あたたかい声掛けで結び続ける未来。
高橋美由紀さんは、3年次編入で高知女子大学(現・高知県立大学)へ入学。卒業研究のテーマを探す際に恩師と出会い、『源氏物語』に出会えました。大学院にも進学し、修了後の今も『源氏物語』の“いち研究者”として活動を続けています。

【Profile】
高橋 美由紀 さん
音楽教室 経営
高知女子大学保育短期大学部卒業
2008年 高知女子大学文化学部文化学科3年次編入
2010年 高知女子大学文化学部文化学科卒業
2016年 高知県立大学大学院人間生活学研究科博士前課程修了
Q1 本学に進学するまでのことを教えてください。
社会人入学で保育短期大学部に入学。後にもう少し勉強がしたいと思い、3年次編入を使って高知女子大学に入学しました。
幼い頃から音楽教室に通い、エレクトーンをずっと続けていて、高校卒業後はヤマハ音楽教室で講師をしていました。結婚後は夫が転勤族のため県外を転々としていましたが、4年目くらいのときに、夫婦で実家のある高知に移住することに。ヤマハは全国規模の会社なので、高知でも同じように働こうと思っていましたが、越してきたときには講師の空きがない状態でした。別の仕事をする気はなかったので、どうしようとかと思っていた矢先、ちょうど手にした冊子に、高知女子大学保育短期大学部(現在は廃止)の社会人入試について書いてあったのが目に留まりました。ヤマハでも幼児教育に携わっていたことと、元々小学校の先生になりたかったという夢もあったので、子どもと関わる仕事がしたいと思い入学。しかし、1年目の終わりに妊娠が分かり、休学して出産、慣れない子育てが始まりました。子育てをしながら復学は無理だ、と半ば諦めていたところ、当時の同級生や事務長、先生方が「帰っておいで」と、あたたかい言葉をかけてくださったことが大きな励みとなり、子どもを預けながら復学することに。卒業まで4年かかりましたが、あの言葉がなければ卒業できなかったと今でも思います。
それから2年ほど保育士として働きましたが、自分のライフスタイルと合わず、自宅で音楽教室を開き、保育園で働いていたときの先生の子どもさんや、息子のお友だちなど数人の生徒から始まり、ご縁がつながって今まで30年ほど音楽教室を続けることが出来ています。
 ―3年次編入で大学に入り直したのは何故ですか?
―3年次編入で大学に入り直したのは何故ですか?
子どもが中学生になって、少しずつ手がかからなくなってきた頃から、もう少し勉強したいなという気持ちが湧いていました。保育短期大学部が発展的解消して母校はすでになくなっていましたが、母校から高知女子大学の教員におられた先生方も多く「もっと勉強したくなったら大学にきてください」と、私たち保育短期大学部の卒業時に声をかけていただいていたこと、それが心に残っていて、子どもが高校入学のころ3年次編入の募集要項を目にした時、これは縁だと思い進学を決意しました。
私が入学した年は、母校の音楽の先生がおられたので、その先生のもとで卒業研究を、と考えていましたが、その年が教育者としての最後の年だったことから、研究生は取らないと言われてしまい、この時は本当に困りました。3年次編入なので、すぐに卒業に向け研究を始めないといけないため、入学してすぐの4月は多くの先生の講義を受けました。
そこで研究室に快く受け入れてくださったのが、恩師である東原先生(退職)だったのです。東原先生は『源氏物語』の研究者で、このことが私が『源氏物語』に出会ったきっかけです。
研究室に入ると研究生たちで原文を読み、注釈書、論文を読み、研究を発表しあったりというのがメイン。私は古文や文学系が元々苦手だったため、本当にゼロからのことで、きっと先生はどうなることやらと思われていたでしょう。
私にとっての古文は、高校の時に習った細かな助詞の変化をただ覚えることと試験の◯×でしかなく、点数をもらうために覚えていた記憶でしたが、ここでは覚えなくていいと言われたことにまず驚きました。原文も、現代文も、注釈もあるから調べたらいいと、原文の読み方を教わり、机いっぱいに本を広げて読みましたが、それが新鮮でとても楽しかったのです。研究者である先生の話を聞くと、さらに楽しくなって。今まで触れてきた現代文の光源氏の物語ではなく、昔から読まれ続けた古文の『源氏物語』を読み解き、その考えを研究室の皆で共有。多くの研究者の論は読む人によって、視点や読み解き方も全く違ってきます。実はずっと続けている音楽も同じで、同じ楽譜でも弾く人が違えば、全く違う聞こえ方になる。思えばその共通の面白さに、私は惹かれたのかもしれません。編入後の2年間は、とにかく新しい発見の2年間で、無我夢中で源氏物語の世界にのめり込んでいきました。
Q2 大学卒業後の変化について教えてください。
毎週研究室に通うようになり、もっと研究がしたいと大学院で研究を続けました。
大学卒業後は達成感もあり、一つ自分の中で区切りがついていたので、元の生活に戻っていました。卒業を見送ってくれた在学中の研究生とはたまに連絡も取っていて、卒業後1年が経った頃に「また研究室に遊びにおいでよ」と言ってもらったんです。その言葉がきっかけで、東原先生もいいよ、と言って下さり毎週火曜日に研究室に行き、後ろに座って研究生たちの発表を聞かせてもらうようになりました。厚かましいかなとは思ったんですが、研究の発表をきくことは毎回とても快い時間でした。
『源氏物語』は長い物語なので、私が在学した2年間では研究できていないところがまだまだたくさん。深掘っていない部分について、研究室で他の人の研究が聞けるのはとても刺激的で、それが毎週の楽しみになり、夏合宿や2年に1回の研究旅行にも同行させていただきました。その生活が続くと「私はまだ源氏物語の狭い範囲しか知らないから、もう少し研究がしたい」と思うようになり、大学院を視野に入れるようになりました。東原先生に相談したところ「一回受けてみたら」と言ってもらえたので思い切って受験し、2014年に大学院へ入学。大学院は、論文に始まり、論文に終わると言った感じで、原文に、参考文献にと、とにかく本を読みました。大学の図書館によく通い、あっという間に時間が過ぎていました。
Q3 現在の活動について教えてください。
本のお手伝いをさせてもらい、そこからのご縁で講座の準備に取り掛かっています。
 大学院を修了して、いつもの日常に戻っていたある日、お友だちと牧野植物園でランチをしていたときでした。それは東原先生からの電話で、どうしたことかと出てみると「源氏物語についての本を書くから、一緒に書いてください」という依頼。目から鱗の話に、自分なんかがと思いましたが、間髪入れず恩師に「今まで研究を続けてきたことを、皆さまにお返しするつもりで書かないと」との言葉をいただき、それが、2024年4月に武蔵野書院から出版された『光源氏の物語 Q&Aハンドブック』です。約260ぺージにわたり『源氏物語』をより深く楽しめる内容で、私も微力ながら著者の一人として携わらせていただきました。
大学院を修了して、いつもの日常に戻っていたある日、お友だちと牧野植物園でランチをしていたときでした。それは東原先生からの電話で、どうしたことかと出てみると「源氏物語についての本を書くから、一緒に書いてください」という依頼。目から鱗の話に、自分なんかがと思いましたが、間髪入れず恩師に「今まで研究を続けてきたことを、皆さまにお返しするつもりで書かないと」との言葉をいただき、それが、2024年4月に武蔵野書院から出版された『光源氏の物語 Q&Aハンドブック』です。約260ぺージにわたり『源氏物語』をより深く楽しめる内容で、私も微力ながら著者の一人として携わらせていただきました。
これだけでも私にとってはものすごいことなのですが、この本がきっかけで高知市の職員の方からご連絡をいただき、2025年度の講座でお話をする機会をいただいています。本の解説というわけではなく、大学でどんな研究をしているのか、研究の仕方を話してもらいたいということだったので、それならと思い承諾しました。実際蓋を開けると、県立大学の先生や歴史館の館長など、そうそうたるメンバーの名前が並んでいて、私は恐ろしいことを始めたなと、今さらながら実感が湧いてきています。今はその準備のために、また大学の図書館を利用させていただいています。心配はありますが、これをご縁にまた大学に足を運ぶきっかけをもらえたような気がして、とても嬉しいです。『源氏物語』の原文を読み、こんなところに面白みがある、ということを私なりに伝えたいなと思っています。
― 一歩踏み出して、知らない世界を知ることは本当に素晴らしいことです!
現在私は音楽教室以外にも、小学校の長期休みの間の放課後支援員や、幼稚園の発表会の伴奏者など、いろんな方面から子どもたちに関わらせてもらっています。あとバンドを組んで、県内の高齢者施設や地域のお祭りやイベントでの演奏もさせてもらっていて、昔以上に音楽が生活の中心になっています。ですが、大学に行ってなければ、きっとこんな風に発展することはなかったなと。大学に入って、いろんなことに挑戦して、いろんなことを考えて、いろんな人と関わり合うことで、一歩踏み出すことが怖くなくなったことが大きかったと思います。大学で得た知識がすべて直結しているとは言えませんが、一歩踏み出して挑戦する力は、私の生活の中心である“音楽”という部分の発展につながってくれています。
今、新しく挑戦しようとしていることとして、子育ての手助けをする“ファミリーサポート”という活動にも登録しました。自分が若い頃に助けてもらってきた分を、今度は少しでも返していきたいと思っています。これからも『源氏物語』を生活の身近におきながら、いろんなことへ挑戦していきたいです!
後輩のみんなにエール!
県立大学は気持ちよく勉強ができて、私にとって“しあわせな空間”です!

社会に出ると制約もあるし、社会人としての責任も伴います。ですが、大学の間は卒業論文を目標に頑張れば、あとは何をやっても自由。自分の好きなもの、興味があるものに没頭できる、それが学生の特権だと思います。
「幸せの神様には前髪はあるけど、後ろ髪はない。通り過ぎてしまうと、いくら手を伸ばしても止められない、だから気になったことには手を伸ばして掴んだらいい」これは、大学へ入学したときに文化学部の学部長がおっしゃった言葉です。今思うと私は、この言葉を信じてここまで来たのかもしれません。
もし、大学入学の時に興味のあることがなければ、その何かを探す場所にすればいいんじゃないかな。思わぬ発見がある!大学は好きなものにのめり込んでいい時間なので、その時間を大事に過ごしてほしいと思います。
※所属・職名等は掲載時点のものです。