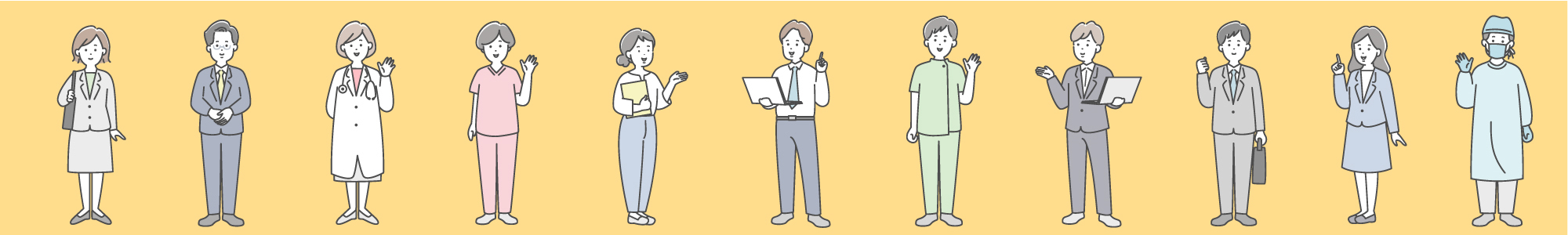本文
海外で通用する力を与えてくれた学び舎。
所和香子さんは、高校時代に出会った看護師に憧れ看護の道へ。高知女子大学(現・高知県立大学)卒業後、臨床で3年間働きましたが、自分は看護師に向いていないと退職。休養のために行ったカナダで、縁あって看護師の再スタートを切りました。現在はナースプラクティショナーとしてカナダで活躍しながら、母校にて博士号取得のため研究に取り組んでいます。

【Profile】
所 和香子 さん
Island Health(Royal Jubilee Hospital)
1998年 高知女子大学家政学部看護学科卒業
2024年 高知県立大学大学院看護学研究科博士後期課程入学
Q1 本学に進学を決めた理由を教えてください。
高校時代の入院経験をきっかけに、歴史と伝統のある高知女子大で看護の道を目指そうと思いました。
私は高校時代に入院経験があり、そのときに出会った看護師さんが看護の道を目指すきっかけになりました。元々違う進路を考えていたため、看護のことは視野に入っていませんでしたが、実際に自分が患者の立場になり、初めて看護という仕事の存在を知りました。身体的なことはもちろん、当時学校にも行けず、友達と会えないことで社会との疎外感を感じていた私を、精神的にも看護師さんが大きく支えてくれました。私だけでなく、他の方々にも優しく接している姿を見て、こういうことが出来る人は素敵だな、と心の底から思いました。高校に復帰し、進路はこの道だ!とすぐさま学校を検索。その頃、全国的に看護師をめざせる学校が少ないなか、日本で一番初めに4年制看護学科を設立し、卒業生が各地で活躍している歴史あるこの大学に惹かれ、進学を決めました。
Q2 どんな学生生活でしたか?
大学時代は看護の勉強と並行して、社会問題についても積極的に学んでいました。
 大きな声で言えませんが、授業にあまり出ていない学生でした(笑)どちらかというと当時は、課外活動の方に時間を使っていて。社会問題について興味のある人たちの集まりに入り浸っていました。東京に行って薬害エイズのことを調べたり、みんなで集まって核実験のことを調べたり、政府の予算の使い方について話し合ったりと、ややハードな内容を、看護と並行して勉強していましたね。そのため「学校で勉強する気はあるの?」なんて先生に言われたこともありました。
大きな声で言えませんが、授業にあまり出ていない学生でした(笑)どちらかというと当時は、課外活動の方に時間を使っていて。社会問題について興味のある人たちの集まりに入り浸っていました。東京に行って薬害エイズのことを調べたり、みんなで集まって核実験のことを調べたり、政府の予算の使い方について話し合ったりと、ややハードな内容を、看護と並行して勉強していましたね。そのため「学校で勉強する気はあるの?」なんて先生に言われたこともありました。
臨地実習は、大変ながらも楽しかった記憶があります。例えば、胃がんで手術をした方を受け持ったときは、食生活のメニューや、これからの生活を考えてパンフレットを作成したことを今でも鮮明に覚えています。実習中に出会った患者さんのことは忘れられません。グループワークも多かったので、みんなで一緒に一人の人の看護について考える時間は、今思えばとても貴重な体験でした。
―印象に残っていることはなんですか。
カナダに行って初めて気づいたのは、大学で学んだ看護哲学や理論は国内だけでなく、国外に行っても十二分に通用することです。修士課程はカナダの大学に通いましたが、カナダの大学生は、哲学や理論の授業でとても苦戦していました。カナダの大学での教育は実践重視で、日本からすぐに看護師として現場に行こうと思うと、苦労するかもしれません。ですが、日本は大学から“看護学とは何か”という学術的な部分を重んじているので、修士課程で私はその点は苦労せずに済みました。大学で看護の根本的な部分を学び、看護師としての基盤ができていたので、海外でもそれが通用したんです。このときは「高知女子大ってすごかったんだな」って衝撃でした。
Q3 卒業後、ナースプラクティショナーになるまでの流れについて教えてください。
3年間臨床で経験し、一旦看護と距離を置こうとしましたが、縁あってカナダで看護師として働くことになりました。
卒業後の進路として、緩和ケアに興味がありましたが、最初からそこに絞らないほうがいいと先生の助言もあり、東京の病院に就職しました。看護教育も充実し、自分で受け持ちを持てる“プライマリ・ケア”を実践している病院で、当時はそういった病院があまりなかったのです。大学の実習で患者さんとの密な関わりを通して、自分で責任を持って深く関われるところがいいなと思い志望しました。大学で学んだことを生かしつつ、伸ばしていける環境ではありましたが、自分の中で腑に落ちない部分もあって。例えば、その病院は一律で患者さんに“がんの告知をしない”という方針だったのですが、一律にそうしてしまうのは違うのではないかと思った私は、診療部長に直接自分の考えを伝えに行きました。そうすると1年目の看護師に何が分かる、と取り合ってもらえず。思ったことをはっきり口にしてしまう自分には、看護師は向いていないのではないかと思い、3年で病院を退職しました。
看護から距離を取るための休養を名目に、行ってみたかったカナダへ。まずはカナダの医療機関をこの目で見てみたいという気持ちがあったので、病院にボランティアの面接に行きました。すると、日本で看護師をしていたなら看護助手で働いたら?と声を掛けていただき、看護助手としての仕事を始めました。看護助手には私のように他国から来た看護師たちがいて、一緒に頑張って看護師になろうとお互い励まし合って。なんとか、カナダに来て3年後に看護師の免許を取得することができました。それからずっとカナダが拠点で、日本に帰ろうという気持ちは全く湧きませんでした。確かに英語で苦労はしましたが、カナダの医療現場はいい意味で言いたいことが言える環境。先輩後輩関係なく、働き始めた1日目からみな同僚、そしてスタッフがおかしいと思うことは皆で話し合う、という風潮が私に合っていたのだと思います。
―それからナースプラクティショナーになったのは、どんなきっかけがありましたか?
カナダの生活にもすっかり慣れた頃、看護協会の雑誌の表紙が目に留まったんです。そこに書かれた“ナースプラクティショナー(以下N P)”という文字が気になり、思わず手に取りました。特集には、医療と看護の両方を担い、カナダの僻地で活躍する看護師のことが書かれていて、その存在が当時の自分の心に響きました。修士課程に進めばN Pになれるというのは調べて分かったものの、すぐに行こうという気にはなれず。なぜなら、それまでに一度カナダで認定看護師になるために学校に通ったことがありましたが、レポートを書くのに苦戦したんです。より専門性の高いN Pを目指すとなると、今の英語力では到底無理だと考え、一旦その思いに蓋をしました。
それから月日が経った2011年の東日本大震災発生時、私はボランティアに行きたいと志願し、カナダの医療団の一員として石巻市に行きました。そこでたくさんの方々の救助や支援にあたり、混乱のなか診断や薬に困っている方々に直面。ああしたらいいかも、こうしたら、と考えは浮かんでくるにもかかわらず、実際には出来ないことも多く、自分にN Pの知識があればもっと出来ることがあったのではないのかと痛感しました。これが大きなきっかけとなり、翌年2012年にN Pになるためカナダの大学院へ進学しました。
Q4 現在の状況について教えてください。
カナダでナースプラクティショナーを続けながら、2024年から県立大で博士号取得を目指し、学び直しています。
 N Pになるため、カナダの修士課程のある大学へ入学。先ほどの話にも出てきましたが、女子大学での、学びの基盤があったので看護学の授業自体はあまり苦労せず、一番大変だったのは事前の不安通り英語でした。特に小児領域での実習は大変でした。
N Pになるため、カナダの修士課程のある大学へ入学。先ほどの話にも出てきましたが、女子大学での、学びの基盤があったので看護学の授業自体はあまり苦労せず、一番大変だったのは事前の不安通り英語でした。特に小児領域での実習は大変でした。
無事修士課程を修了してからは、それまでと同じ急性期病棟にN Pとして就職。働き出して改めて感じたのは、看護師とN Pの仕事は全くもって違うものということです。修士の2年では学びきれなかったものを自分で働きながら知見を積み、知識に技術にと補填していく感じなので、N Pになりたての頃はとにかく仕事に慣れるのが大変でした。
それからN Pとして働き慣れた頃に、以前から頭の隅にあったことについて向き合うことにしました。これまで看護の実践ばかりをやってきて、自分には研究力がないという自覚がありました。研究について自分で学ぶことにも限界があるし、カナダでの臨床は一通り経験したので、今度は次のステップへ、と進学を決意。カナダで学んだことを日本に返していくにはどうすれば良いのかということも考えながら、2024年春から県立大の博士後期課程で学んでいます。
まだ博士号取得後のことは決めていませんが、ゆっくり考えていこうと思っています。
日本にもN Pは増えてきている反面、現行では民間団体が発行している免許。今はまだ看護協会や国が出しているものという訳ではないため、海外のN Pに比べてその権限は制限されています。また、N Pは日本で“診療看護師”と呼ばれていますが、その“診療”という言葉がつけられていることに私自身はしっくりきていないんです。どうしても“診療”と表すと、診療行為が全面的に出てくるイメージがあるので、カナダで現場を経験している分、やはり看護という部分が前に出るのが最適だと考えています。今日本でのN Pの在り方について、少しずつ動きが見られていますので、これから日本の看護やN Pがどうなっていくのか、将来的には何らかの形で関わりを持てたらと思っています。この3年間で、私に何ができるかをゆっくり考えていきたいです。
私は今もカナダで仕事を続けていますが、仕事とは別で“クオリティーインプルーブメント(以下Q I)”という質を改善するプロジェクトを継続的に行っています。実際医療者が“患者さんはここが大事と思っている”と考えることと、患者さんが実際に思っていることは外れていることもあり、思い込みって多いんだろうなと考えることがよくありました。そこで、必ずプロジェクトには患者さんにも入ってもらい、患者さんが大事にしていることは何かを直接聞き、データとして表すようにしています。そのプロジェクトや結果についても、県立大で学生さんたちに話をさせてもらう機会が何度かあり、自分自身の学びにもつながっています。
 これからもN Pとしての仕事、Q Iの活動、そして大学院での研究。似ているようで似ていない、性質の異なる3つのことに楽しみながら向き合っていきたいと思います。
これからもN Pとしての仕事、Q Iの活動、そして大学院での研究。似ているようで似ていない、性質の異なる3つのことに楽しみながら向き合っていきたいと思います。
後輩のみんなにエール!
高知県立大学での学びは、世界に通用します!

県立大に入って本当に良かったです。国内、国外と臨床を通して、大学時代の学びを実感することが数えきれないほどありました。あの頃社会問題に向き合っていたことは、もちろん糧になっていて意味のあることでしたが、もう少し看護の学びも大事にしていたらもっと道は広がっていたかも、と振り返ることもあります。なので、学生の方々は今大学でしか学べないことを学んでください、とお伝えしたいです。
元々カナダで看護師になろうとは思っていませんでしたが、カナダに行ったことで自分の新しい可能性に出会えました。最初の一歩さえ踏みだせれば、自分が思っているよりずっと可能性は秘められています。自分の可能性を自分で決め切らないで、挑戦していってください。
※所属・職名等は掲載時点のものです。