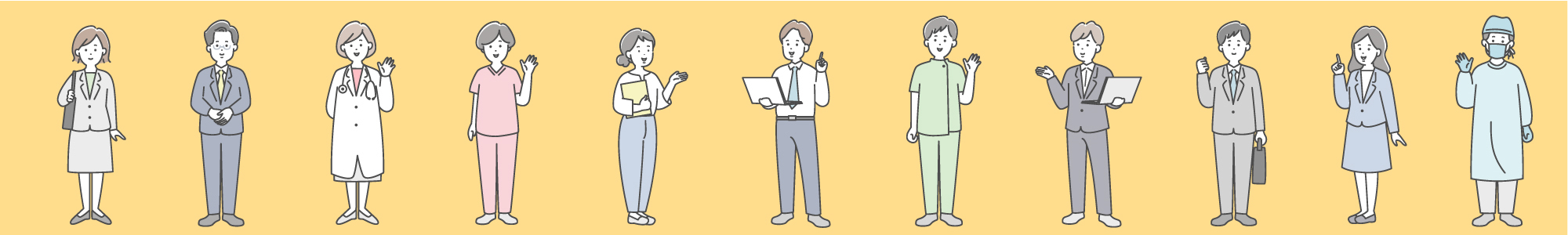本文
憧れの背中を追って、 夢だった養護教諭の道へ。
松村晶子さんは中学時代に出会った先生に憧れ、同じ養護教諭の道を目指し、高知女子大学(現・高知県立大学)へ入学。看護師・保健師・養護教諭の3つの資格を取得するために4年間勉学に励みました。卒業後、夢への気持ちは変わることなく、確実に段階を踏み、長年の夢だった養護教諭として11年間、小学校に勤務しています。

【Profile】
松村 晶子 さん
高知大学教育学部附属小学校 養護教諭
2004年 高知女子大学看護学部看護学科卒業
2014年 高知県立大学大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程修了
Q1 本学に進学を決めた理由を教えてください。
看護師、保健師、養護教諭の3つの資格取得を目指すことができ、伝統のあるこの大学で専門性を学びたいと思いました。
中学時代の養護教諭がとても素敵な先生で、その先生に憧れて養護教諭になりたいと思っていました。受験を意識し始めた高校2年の頃に、当時の高校の養護教諭にそのことを相談すると「養護学校(今でいう特別支援学校)の先生にも話を聞いておいで」とつなげてくれることに。紹介してくれた先生は大阪の循環器病院で看護師として数年働いた後、養護教諭になった方で、当時の私に「看護師を経験していたら様々な判断をする時に自信になると思うよ」というアドバイスをくれました。加えて、そんなベテランの先生でも、学校の廊下をバタバタと走ってくる音が聞こえたら緊急事態かと思ってドキッとすることがある、という現実も教えてくれて。その話を聞くまでは、教育学部の養護教諭養成課程に進学しようかと思っていましたが、看護の専門知識を身に付けた養護教諭になりたいと思い、看護学部への進学を目指すことにしました。
全国規模で大学を探しましたが、看護師・保健師・養護教諭の3つの資格取得を目指すことができて、かつ全国各地に活躍している先輩方が多い伝統のある学校に魅力を感じたため、高知女子大学で専門性を学んでいきたいと思い、受験しました。
Q2 どんな学生生活でしたか?
夢に向かって挑んだ高知での生活は大変なこともありましたが、たくさん経験して成長することができたと思います。
期待に胸を膨らませ、とにかく頑張ろう!と思って臨んだ大学生活当初は、空きコマもない講義や演習の毎日。あの頃は本当に忙しかったなぁと思い出すことがいまだにあります。地元・宮崎県から単身で高知に来て初めての一人暮らし。加えて、1年目はアルバイトも始めたので、日々をこなすことに精一杯でしたが、2年目からは少し余裕も出てきて、遊びやボランティアなど、いろんなことにチャレンジしました。せっかく高知に来たので…と、よさこいも1度だけですが踊りましたよ。親元を離れて高知に来ての生活は初めてのことばかりで、もちろん楽しいことだけじゃなく、失敗したこともたくさんありましたが、いろんな人に出会い、一つ一つ経験しながら、人としても成長することができたんじゃないかなと思います。
―学生生活で印象に残っていることはなんですか。
 私が在学していた頃は1回生から3回生までが40人、4回生は25人編成だったので、とてもアットホームな雰囲気でした。4回生の卒業研究はその中の6人でグループを組み、1年かけて家族看護についての研究に取り組みました。研究のために、実際に生活しているご家族にインタビューをするため、県内あちこちに行ったことがすごく記憶に残っています。
私が在学していた頃は1回生から3回生までが40人、4回生は25人編成だったので、とてもアットホームな雰囲気でした。4回生の卒業研究はその中の6人でグループを組み、1年かけて家族看護についての研究に取り組みました。研究のために、実際に生活しているご家族にインタビューをするため、県内あちこちに行ったことがすごく記憶に残っています。
なかでも覚えているのが、物部よりもっと奥に住むご夫婦を訪問した時のこと。地域の保健師さんの車の後ろを追って向かったのですが、家まで車で行けないため、途中の道に車を置いて山を登って夫婦の住む家へ。そこはさながら山深くにあるポツンと一軒家のようでした。認知症の奥さんを介護している旦那さんに、老老介護についてのお話を聞かせてもらったのですが、その実際の生活を見て、衝撃を受けたことはいまだに忘れられませんね。
Q3 卒業後、養護教諭になるまではどのような過程をたどりましたか?
看護師、保健師と経験し、いろんな現場を見てきましたが、養護教諭になりたいという気持ちは揺るがなかったですね。
 大学卒業後すぐに結婚して、その後出産を経験し、産後2ヶ月から看護師として県内の病院で働き始めました。託児所のある病院だったので、当時は授乳しながら仕事をしていて…今では考えられないですね(笑)
大学卒業後すぐに結婚して、その後出産を経験し、産後2ヶ月から看護師として県内の病院で働き始めました。託児所のある病院だったので、当時は授乳しながら仕事をしていて…今では考えられないですね(笑)
ですが、ありがたいことに周りの方が良い方ばかりで、仕事も育児も支えてもらっていました。病院で慢性期・急性期と、幅広くいろんなことを経験した後、健診センターで保健師として数年勤務。それから、縁あって大学当時お世話になった女子大の先生に声をかけていただき、高知学園短期大学の看護学科の助手として、教育現場でも働きました。学内演習や実習の引率などを通して学生さんと関わることで、看護についてより深くそして多角的に考える機会になりましたね。ただ、助手の立場だとできることも限られます。修士で学び、看護をさらに深めて仕事の幅を拡げたいと思い、大学院へ進学しました。この時正直、大学院なんて大それたこと…と迷ってもいましたが、大学時代、卒業研究の担当教員だった池添先生に「大丈夫、やっていけるよ」と言ってもらえたことが、大学院進学への決め手となりました。先生は大学時代から現在まで、何かあったらすぐに相談に乗ってくれ、優しく導いてくれる、私にとってかけがえのない存在です。大学院での専攻は、地域保健学領域の学校保健分野。それまで看護師、保健師と働いてきましたが、やはり最終的には養護教諭になりたい、という気持ちは揺るぎませんでしたね。
Q4 現在のお仕事について教えてください。
小学校の養護教諭として日々、子どもたち、先生たちの心と身体の健康を守るための取り組みをしています。
修士1年目の間に、高知大学採用の養護教諭の試験を受け合格。それから11年間、ここ高知大学附属の小学校で養護教諭として働いています。
仕事内容としては、約630人の児童と、約50人の先生の心と身体の健康を守るために、さまざまな取り組みをしています。規模の大きい学校ですので、具合の悪い子の対応や登校中や学校内でのけがの処置など日々の来室者は大変多いです。健康診断の日程調整から実施・事後措置や個別指導はもちろん、校内の環境整備も行っています。毎回の発育測定では、ミニ保健指導を行っており、子どもたちが楽しみながら自分の健康観をしっかり育めるように意識しています。また、発達や学習に課題を抱える児童の把握、教育相談の役割も担っているので、スクールカウンセラーや医療機関など関係機関との橋渡し役もしています。細かくいうとまだまだ業務は多岐にわたるので、とてもじゃないけど身体が一つじゃ足りません(笑)
着任当初、こちらからは本当に些細に思えるような理由で来室する子どもたちと関わり、小学生はこんなことでも保健室に来るのか…と戸惑いの連続でした。ですが、どんなに些細に見えることでも、子どもたちの来室の真意をつかむことが、大切な私の役割だと日々実感するようになりました。子どもの動きや考えって本当に読めないし、発達段階的にも自分の様子をうまく他者に伝えることができないので、言っていることだけでなく、教室での様子を担任に確認したり、患部の観察やバイタルサインをとったりして、より多くの情報から本当の心身の状況を判断していかないといけません。子どもたちは養護教諭=お医者さんと思っているようなので(笑)、できるだけ迅速に適切な対応ができるように心がけています。
看護師としての現場の経験があったからこそ、ここまでは様子を見て大丈夫、という判断ができることは、養護教諭をする上でとても力になりました。資格を取るだけじゃなくて、医療現場も経験していて本当によかったと思います。
一人職なので大変なことも多いですが、子どもたちの笑顔や言葉にパワーをもらっています!
保健室にいると日々子どもたちの可愛い言動に出会えます。もじもじしながら「…おじゃましました。」と言って退室する子どもや「先生ひまやろー。遊びにきてやったで」と声をかけていく子ども、時々コンコンダッシュをする人もいますが…。そんなコミュニケーションを通して、癒され、元気をもらっています。学童期は、これまでの家庭中心の生活から子どもの社会が大きく拡がり、劇的に成長していく時期です。子どもたちが見た目も中身もぐんぐん成長していく様子を間近で見届けることができることが、自分のやりがいにもなっています。
なかには、将来私みたいに養護教諭になりたいと言ってくれる子もいて。子どもたちが卒業していく度に、人の人生に関わっている場所であり、仕事であるということを深く実感し、頑張ってよかったなと思えますね。
県立大学は学年の人数も少なく、アットホームな学校だったので、先生は学生に対して大勢の学生の一人ではなく、一人一人と丁寧に向き合ってくれていました。今、私自身どれだけ忙しくても、一人一人の子どもの言葉を聴こうと思って接しているので、大学での先生方の姿が、今の自分の子どもたちとの関わりにつながっているような気がしますね。
後輩のみんなにエール!
自分にしかない自分色の人生を作り上げていってほしい!
 今までを振り返ると、いろんな経験をしてきた中で、失敗もたくさんしたし、人に迷惑もかけてきました。私も実際そうでしたが、若い時ってその嫌な出来事がとても大きなことに感じてしまいます。ですが、時が経ってみると、あのときは辛かったけど、あの出来事がなかったら今のこの考えに至ってないな、なんて思うこともあるんですよね。あれは自分の人生に必要なことだったんだなって。今、辛いとか、絶望に思うことも必ず意味のあることで、将来の自分をつくる大事な要素の一つだと思ったら、いろんなことにチャレンジしていける気がしませんか?優しく見守ってくれる先生方が多い県立大学で、人と人とのつながりを感じながらたくさんチャレンジして、人生の経験値を増やしていってほしいです!
今までを振り返ると、いろんな経験をしてきた中で、失敗もたくさんしたし、人に迷惑もかけてきました。私も実際そうでしたが、若い時ってその嫌な出来事がとても大きなことに感じてしまいます。ですが、時が経ってみると、あのときは辛かったけど、あの出来事がなかったら今のこの考えに至ってないな、なんて思うこともあるんですよね。あれは自分の人生に必要なことだったんだなって。今、辛いとか、絶望に思うことも必ず意味のあることで、将来の自分をつくる大事な要素の一つだと思ったら、いろんなことにチャレンジしていける気がしませんか?優しく見守ってくれる先生方が多い県立大学で、人と人とのつながりを感じながらたくさんチャレンジして、人生の経験値を増やしていってほしいです!
※所属・職名等は掲載時点のものです。