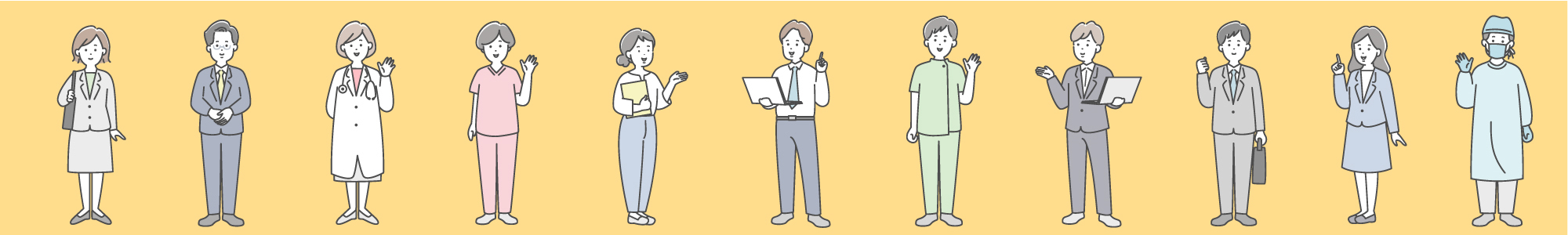本文
小さい頃から日常にあった違和感を胸にもう一度挑戦へ。 自分のなかの大切なことを確かめられた学びの時間。
社会人経験を経て、興味があった“福祉分野”を改めて学ぼうと大学入試を決めた出原千恵さん。卒業後、2年半の海外生活を経験して、現在は地元・高知で訪問介護員をしています。

【Profile】
出原 千恵 さん
合同会社ステラ 訪問介護事業所わらふく 訪問介護員
2020年 高知県立大学社会福祉学部社会福祉学科卒業
Q1 本学に進学を決めた理由を教えてください。
2年半、市役所での障害のある方々との関わりを通じ、元々興味があった福祉分野に足を踏み入れることを決めました。
高校を卒業して、大阪の看護系大学に進学しましたが、肌に合わず1年ほどで高知に帰ってきました。それから2年半、縁あって高知市役所で働くことに。その時働いていた部署は、障害のある方の免税手続きをお手伝いする機会もあり、障害のある市民やその家族と関わることがありました。幼少期、私には車椅子に乗っていた友人がいて、当時その子を取り巻く環境や差別を小さいながらに感じていました。その原体験がずっと心に残っていたので、市役所での経験を通し、福祉の分野で仕事をしたい、と思うようになったんです。同時に海外にも興味があったので、ワーキングホリデーなども検討しましたが、いろいろと調べていくうちに、高知県立大学の社会人入試を発見。出願の条件を満たしていましたので、まずは学べる知識を、と大学受験を決めました。
Q2 どんな学生生活でしたか?
社会人入学でしたが、思った以上に周りとの壁はなく、楽しい学生生活を送れました。
社会人入学なので、周りはほとんどが3.4歳下の子ばかり。最初はうまくやっていけるか不安もありましたが、あだ名をつけてくれたり、遊びに行ったりと、すぐに打ち解けることができ、思った以上に楽しい学生生活を過ごすことができました。歳はみんなより上でしたが、末っ子みたいな感じでしたね(笑)実習が始まった頃は、授業で学んだことと現場とのギャップを感じることが多く、行き場のない葛藤を抱えていましたが、そんな時は同じ実習先の子と語り合って、指導者のところに一緒に行ったりして、お互いの気持ちを共有し合いました。そのおかげで、実習を通して仲良くなった子もいましたよ。元々福祉分野に興味があったこともあって、大学の授業はとても面白かったです。いろいろな知識を得られるのは、やはり大学じゃないと、と思いました。
Q3 なぜ卒業後、海外へ行こうと思ったのですか?
「日本の外を見てみたい!」という気持ちが抑えられず、コロナ禍でしたが単身でスウェーデンへ。海外の福祉の在り方をこの身で体感してきました。
 福祉の学びを深めながらも、 “日本の外を見てみたい”という気持ちもずっとあったので、在学中は毎年、海外旅行にも行きました。その体験も含め、海外福祉の現状も知りたかったので、卒業後は「ワーキングホリデーに行こう!」と息巻いていたのですが、在学途中から世間はコロナ禍真っ只中に。周りにそのことを話すと、もちろん反対されました。そんななか、所属していた“国際福祉分野”のゼミの先生が、唯一背中を押してくれたんです。先生の応援もあって、卒業後は元々の知り合いがいるスウェーデンへ。コロナ禍で当時は、現地の人でさえ仕事がない状況。自由に動けない部分も多かったのですが、元々得意だった書道を教えるボランティアをすることで、現地の人と関わりを持つことができました。
福祉の学びを深めながらも、 “日本の外を見てみたい”という気持ちもずっとあったので、在学中は毎年、海外旅行にも行きました。その体験も含め、海外福祉の現状も知りたかったので、卒業後は「ワーキングホリデーに行こう!」と息巻いていたのですが、在学途中から世間はコロナ禍真っ只中に。周りにそのことを話すと、もちろん反対されました。そんななか、所属していた“国際福祉分野”のゼミの先生が、唯一背中を押してくれたんです。先生の応援もあって、卒業後は元々の知り合いがいるスウェーデンへ。コロナ禍で当時は、現地の人でさえ仕事がない状況。自由に動けない部分も多かったのですが、元々得意だった書道を教えるボランティアをすることで、現地の人と関わりを持つことができました。
私は在学中に“スウェーデンと日本のインクルーシブ教育の比較”について卒業論文を書いていたのですが、実際は思った以上に障害も移民も性別も関係なく、みな一緒に学ぶのが当たり前。スウェーデンは福祉に対する考え方が全く違っていて、それを直に体感できたのは本当に良い経験です。
―印象に残っている出来事はなんですか。
スウェーデンに1年滞在した後、デンマークの学校に1年通いました。そこは少し特殊な学校で、200名超の定員に対し、何かしら身体や知的に障害を持つ生徒が4割。入学前に障害を持つ人が、入学希望の障害を持たない人を面接して、在学中のサポートをしてくれる人を選びます。すると、障害を持つ人は雇用関係を結んでボスとなり、選ばれた人は介助者兼学生として入学することができます。これはパーソナルアシスタント制度に基づいたものですが、残念ながらまだ日本ではそう馴染みがないものです。
 介助者として選ばれた人は、ボスの日常生活のケアを全面的に行いますが、いち生徒でもあるので、授業中は自分が取りたい授業を選択し、集まった仲間と一緒に授業を受けることが出来ます。授業中に何か介助が必要なことがあると、生徒みんなで考え、みんなでサポートをしました。足の不自由な人をアウトドア用の車椅子に乗せて、山登りとキャンプに挑戦したこともあります。車椅子だから登らない、ではなくて、どう登るかを考え、この時はみんなで車椅子を担いで登りました。大変さももちろんありましたが、それ以上に笑って助け合って、かけがえのない思い出です。
介助者として選ばれた人は、ボスの日常生活のケアを全面的に行いますが、いち生徒でもあるので、授業中は自分が取りたい授業を選択し、集まった仲間と一緒に授業を受けることが出来ます。授業中に何か介助が必要なことがあると、生徒みんなで考え、みんなでサポートをしました。足の不自由な人をアウトドア用の車椅子に乗せて、山登りとキャンプに挑戦したこともあります。車椅子だから登らない、ではなくて、どう登るかを考え、この時はみんなで車椅子を担いで登りました。大変さももちろんありましたが、それ以上に笑って助け合って、かけがえのない思い出です。
日本だと障害のある方が、迷惑をかけてしまうから、と諦める場面が多いですが、あそこではみな平等で、誰でも手を挙げていい環境。これが日本との大きな違いでした。諦めてしまう人を見るより、一緒に登れて、一緒に挑戦できて良かった、と喜ぶ姿を見られた方が、やっぱりやりがいがあるし、嬉しいですよね。みんな遠慮しない、諦めない、応援する、その雰囲気がとても好きでした。
(写真)アウトドア授業による5日間のノルウェー登山にて。
Q4 現在のお仕事について教えてください。
現在は、友人の事業所で訪問介護員として、利用者さん一人一人に沿った日常生活の補助をしています。
2年半の海外生活を経て、高知へ帰省。海外で学び、興味のあったパーソナルアシスタント制度は、日本でも導入されてきていて、高知にも数件ですが、希望している利用者さんがいました。しかし、私自身が思う制度の在り方と、利用者さんが思う在り方との差を感じ、一旦考え直すことに。そんな時、訪問介護事業所を開いた友人の話を聞く機会が訪れました。働くなら障害者分野、と思っていたので、正直、高齢者分野は全く考えていなかったのですが、友人の話を聞くなかで、本人が望む生活実現のお手伝いができたらいいなという私自身の気持ちは変わらないかもしれない、と挑戦のような気持ちが沸き、入職を決めました。
介護福祉士の資格は持っていなかったので、研修を受け、訪問介護員(ホームヘルパー)として、利用者さんの家に出向き、掃除や買い物、入浴介助等、身の回りの補助をしています。昨年の1月に入社したので、まだ1年と少ししか経っていませんが、思っていた印象より現場での仕事は楽しく、やりがいがあります。補助に入っているのに、気遣ってくれたり、孫のようだと良くしてくれたり、優しい利用者さんもたくさんいます。「掃除の人やろ?」と言われることも多いのですが、私自身はそうは思っていなくて。掃除だけではなく、高齢の方が住み慣れた自宅で生活をし続けられるようにできないことを補助することを大事にしていて、立派な仕事だと思っています。その気持ちを大事にしていると、コミュニケーションを重ねて、少しずつ信頼してもらえ、利用者さんも、家族さんも変わっていきます。信頼関係を築いていくと、ありがとう、と言ってもらえることも増え、空気に変化が見えてきます。その少しの変化を楽しみに、今、仕事ができています。
多様な人々が集える場所を作りたいです。
仕事以外で挑戦したいと思っているのが、四国八十八ヶ所の歩き遍路。デンマークの学校を出た後、同じ学校に通っていたデンマーク人の車椅子の子が、“カミーノ・デ・サンティアゴ”と呼ばれる世界遺産の巡礼路、フランスからスペインの果てまで約800キロの巡礼に挑戦するため、サポートしてくれる人を募っていたので、迷わず手を挙げました。元々私の夢でもあったし、海外生活の集大成だなと思って。1ヶ月半の旅では、毎日安い宿に泊まるんですが、そこでいろんな人と出会って、話して、ご飯を囲んで、とても居心地の良いものでした。
その旅で出会った世界の人たちのなかに四国遍路をした人もいて、高知に帰ったら絶対に行こうと決めました。四国遍路も世界遺産登録を目指す動きがあるので、まずは自分で挑戦してみて、そのなかで遍路宿のような多様な人たちが集まれる居場所を作りたい。今まで自分がいろんな場所で受け入れてもらったように、私も人と人との出会いの場に関わって、サポートしていきたいなと思っています。


(写真)カミーノ巡礼1日目 ピレネー山脈を越えフランスからスペインへ。
 (写真)800km42日かけてゴールした仲間とサンティアゴ大聖堂前にて。
(写真)800km42日かけてゴールした仲間とサンティアゴ大聖堂前にて。
後輩のみんなにエール!
障害のあるなし関係なく、挑戦する権利は誰にでもある!
今ではすっかり行動派の私ですが、昔からではありません。大学を含め、さまざまな場所でいろんな人との出会いを通し、今のような考え方を持つことができました。デンマークの学校で常に言われた「行動しながら考えろ」という言葉が、今でも胸に残っています。挑戦する権利は誰にでもあると思うので、勇気を持っていける人が増えたらいいなと思います。コロナ禍真っ只中、私の挑戦に背中を押してくれた教授や友人、家族には本当に感謝しています。これから挑戦しようとしている方にはぜひ恐れず挑戦してもらいたいし、サポートできることがあれば、私もサポートしたいです!一緒に挑戦しましょう!

(写真)海外への挑戦に背中を押してくれた長澤先生と。久しぶりの再会に笑顔が溢れました。
※所属・職名等は掲載時点のものです。