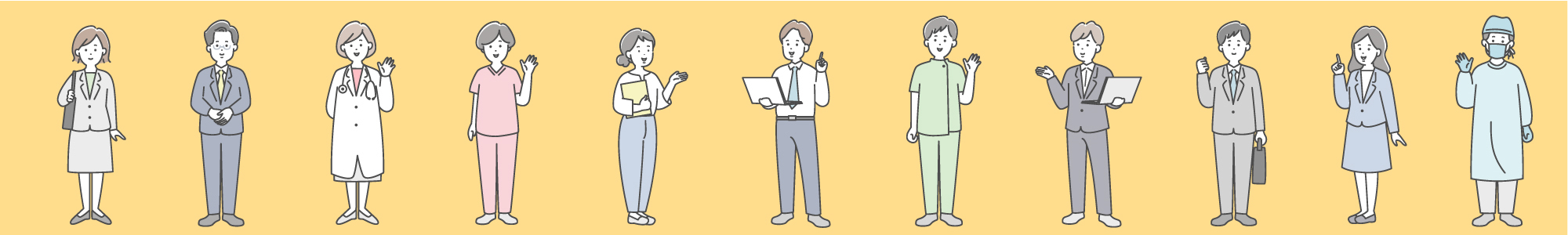本文
やってみようかな、好奇心の連鎖で研究者の道に。
大学時代、真面目とは言えない学生だったと語る岩本幸大さんは、卒業後4年間病院で勤務し、大学院へ進学。現在は博士号取得のために京都大学大学院にて、臨床での経験を元に看護支援システムの開発に挑戦しています。

【Profile】
岩本 幸大 さん
京都大学大学院 情報学研究科 社会情報学コース 博士後期課程
2017年 高知県立大学看護学部看護学科卒業
2023年 高知県立大学大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程共創看護学領域修了
Q1 本学に進学を決めた理由を教えてください。
医療系に進もうと思い、公立大学である高知県立大学を受験しました。
高校時代は理系のコースに在籍していましたが、工学的な部分にあまり惹かれず、人と関わる方が自分に合っていると感じていました。将来を考えたときに、対象は“人”が良いと思っていたことと、母親が看護師である影響もあって、医療系の大学への進学を決めました。4人兄弟の長男だったこともあり、国公立大学という選択肢しかなく、いろいろと検討した結果、高知県立大学の看護学部へ進学することになりました。
Q2 どんな学生生活でしたか?
勉強はほどほどでしたが、充実した学生生活を過ごしていました。
現在は、博士号の取得に向けて大学院に進学していますが、大学生の頃は自分で言うのもなんですが、ひどかったと思います(笑)講義の出席もほどほどで、バイトをたくさん入れて、バイト先の人たちと飲みに行って、行く先々で顔見知りができて、毎日楽しく過ごしてはいました。同級生はきっと私のことを“酒飲み”としか思っていなかったと思います(笑)
そういった学生生活だったので、同級生ほど勉強に打ち込んではいませんでしたが、立志社中プロジェクトの“健援隊”では、代表をさせてもらいました。この活動は地域の方の健康意識向上を目指した様々な活動をする団体で、例えば市民の方々へAEDの使い方や心臓マッサージの方法を普及することや、大学生向けに不妊治療の話をしていました。よさこい祭りでは、熱中症の予防法をプリントしたうちわを配ったりもしました。当時、60−70人のメンバーがいたので、その大所帯を統率して色々と活動していたことは今も記憶に残っています。
―印象に残っていることはありますか?
様々な看護実習を通して、患者さんと関わりながら人の役に立つことのできるこの分野は楽しいと感じていました。実際の臨床現場では、複数の患者さんを一度にみる必要があるのですが、実習で一人の患者さんと密に関わる機会があったことは、良い経験だったと思い返します。
勉強には取り組んでいなかったと言いつつも、いろんなことに挑戦したい性格だったので、看護師、保健師に加えて養護教諭の資格も取得しました。そのため、養護教諭の実習では3週間ほど片道1時間かけて小学校に通っていましたが、子どもたちとプールに入ったり、遊んだり、本当に楽しい実習でした。実は、私が県立大で初めて養護教諭の資格を取った男子学生だったのですが、後に養護教諭を目指す男子学生から「岩本さんがいたから、私も挑戦することができた」と言われ、嬉しかったことを覚えています。当時の私の実習態度が評価されたみたいで、以後も受け入れしやすかったそうです。現在、養護教諭の道に進んでいるわけではありませんが、貴重な前例として誰かの背中を押せる存在になれて良かったと思います。
Q3 大学卒業後の進路のことを教えてください。
東京の循環器専門の病院へ就職。4年間I C Uで働いた後、大学院へ進学しました。
就職を考える段階で、頭の片隅に「まだ就職したくない」「できるだけ先延ばしにしたい」という気持ちの芽生えがありました。いわゆるモラトリアムというやつです。通常では4回生の4月頃に就職活動を行いますが、私はその頃に実習が重なっていたことも関係して、積極的に就職活動を行っていませんでした。夏が過ぎて一度応募書類を出しましたが、既に枠が埋まっていて決まりませんでした。その後も、先延ばしにしているとあっという間に冬になり、周囲から急かされながら悩んだ末に、「東京に行きたい」という気持ちを優先し、東京での就職を決めました。
特に働く分野にこだわりはなかったので、当時募集の出ていた中から循環器専門の病院を選び、配属先はICU(集中治療室)を希望しました。現場に出て1年目は、慣れない環境と知識や経験不足で、毎日悔しい思いもしましたが、良い先輩や友人にも巡り会えました。
働き出して3年目くらいに、在学中からとても親しくしていた県立大の先生から「そろそろ大学院に来る?」と一本の連絡がありました。ちょうど共創看護学領域ができた年だったので興味はありましたが、引っ越ししたばかりの時期で、経済的にも不安定だったこともあり「来年行きます」と返事をしました。臨床も楽しかったですが、大学院での研究も楽しそうだと思ったので、次の年に大学院へ挑戦しました。
Q4 現在のことについて教えてください。
大学院で2年間研究をした後、博士号取得のために京都大学大学院へ進学しました。
修士論文のテーマを考えているとき、VR技術を利用した災害関連のプロジェクトに参加することになり、そこでの体験を通じて、表情分析AIを使用した研究に取り組むことを決めました。修士論文の研究では、既存のAIプログラムを使いましたが、プログラムを一から作る側もやってみたいと少しずつ感じるようになりました。VRのプロジェクトで出会った方々に、医療と情報技術を使用した研究に詳しい方がいないか尋ね、大阪大学、京都大学の先生へとつなげてもらいました。それと並行して、東京大学でAIの研究に携わった経験のある先生と話をした際に「研究者を志すなら“博士号”は必要だ」と言われ、博士課程への進学を悩んでいましたが、博士号取得のため京都大学の大学院に進学することにしました。
博士後期課程は3年間で、もうすぐ2年が経ちます。体感的にどの経験よりも一番忙しい日々で、常に何かに追われている感じで心臓に悪いですね(笑)
人生は一度きりなので、いろんなことに挑戦し続けることを大事にしています。
現在は、看護師の意思決定を支援するシステムの開発を目指しています。看護師の仕事は多様な業務を複数の患者に実施し、目まぐるしく変わる環境の中で優先順位を決めて仕事をしているのですが、そういった判断は個人に委ねられています。なので、ベテランの看護師は効率的にできても、入ったばかりの新人看護師ではそうもいきません。私も看護師1年目の時に、次に何をしたらいいか分からないと、よく棒立ちになっちゃってたんですよね。そこで、業務の優先度を決めるルールを基にアルゴリズムを開発することで、その悩みを解決できるシステムが作れるんじゃないかと思っています。“次の業務はこれ”といった感じで、業務の順番を指示してあげる。例えで言えば、カーナビみたいなものですかね。現在は、インタビュー調査からアルゴリズムの開発を目指している段階で、在学中にどこまで作れるか分かりませんが、できる限り努めたいと思っています。
京都大学では国際学会での発表が卒業要件にあり、英会話を最近始めました。英語が障壁にならなければ、海外で働きたいと考えています。この先、看護師として臨床現場で働く可能性は少ないですが、臨床現場の感覚を持った研究者になりたいと思います。修士課程の時から考えていますが、臨床現場に貢献できる研究をこれからもしていきたいと思います。
後輩のみんなにエール!
どこで自分が活躍するか、のビジョンは持って。
以前、“風立ちぬ”という映画を見て、とても感銘を受けました。特に心に残ったのは「創造的人生の持ち時間は10年だ。設計家も芸術家も同じだ。君の10年を、力を尽くして生きなさい」という言葉。人の寿命は伸びてきていますが、どんなにすごい人でも年齢とともに衰えがあることを日々感じています。私はまだ研究者として卵にすらなれていない成長過程ですが、例えば海外での研究活動やいろんな体験を経て、成熟させた自分の知識や経験を研究に活かせるのは40歳頃かなと予想しています。そこから10年、15年を自分のピークに持っていきたいと思うと、そこに向けてやることは自然と見えてきます。基本的には、行き当たりばったりな私ですが、そんなベースプランもありつつ、その時々で出会う人との偶然を楽しめたらと思って、いつも過ごしています。高校生の皆さんも、先は長いと思っているかもしれませんが、看護師になったその先どうするのか、自分自身のピークをどこに持っていくのか考えていくことも重要だと思います。どこに所属するか、どこで働くかよりも、“自分が何をしたいか”で動いた方が楽しい人生が送れるのではないかと私は思います。
※所属・職名等は掲載時点のものです。