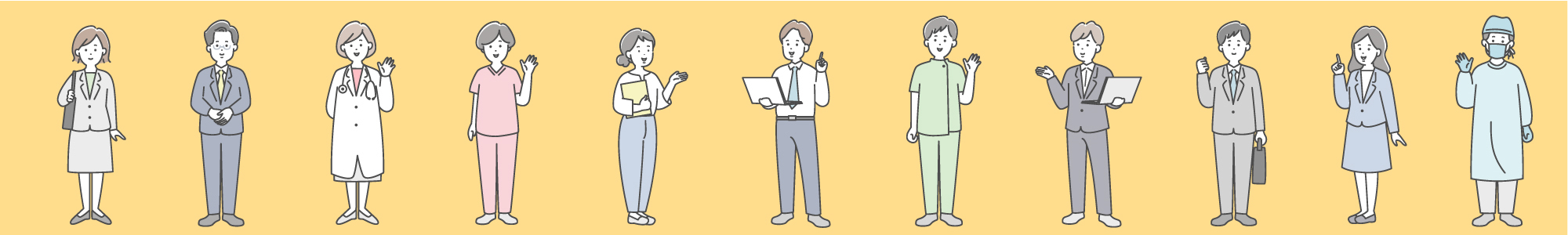本文
後悔しないように、アクションを起こし続けて自分で選んだ道。
高校の先生に勧められ、福祉を学ぶため高知女子大学(現・高知県立大学)へ入学した早川佐紀さん。臨地実習で訪れた今の職場の雰囲気に惹かれ、実習先への就職を目指しました。卒業後から現在まで、障がい福祉の分野で、利用者さんに寄り添いながら楽しく働いています。

【Profile】
早川 佐紀 さん
土佐希望の家 医療福祉センター 生活支援員
2014年 高知県立大学社会福祉学部社会福祉学科卒業
Q1 本学に進学を決めた理由を教えてください。
先生に勧めてもらい興味を持った福祉の道を目指すために、県立大へ入学しました。
高校時代、進路を考えるタイミングには明確にこれになりたい、というものが当時の私にはなく、どうするか迷っていました。担任の先生と進路相談で話していくうちに、先生から「早川さんは福祉系が向いているんじゃない?」と言われ、福祉系の仕事について自分で調べることに。思っていた以上に仕事の種類がありましたが、当時たまたまテレビで見かけたのが、養護施設で働く職員さんにスポットをあてたニュース。それを見てやりがいがありそうだと感じ、養護施設など児童系の福祉の仕事に就きたいなと思ったのがきっかけでした。福祉の勉強をするために、私立の大学なども検討しましたが、先生から高知県立大学を勧めてもらったので、ここを目指すことにしました。
Q2 どんな学生生活でしたか?
ほどよく息抜きもしつつ、色々な経験もできた学生生活でした。
大学時代は、勉強はほどほどに頑張っていたかな(笑)友だちには一分一秒も無駄に出来ない、と全集中している子もいましたが、私は国家試験直前まで割と遊んでいた方だと思います。バイトもしていたし、そのバイト代を全て注ぎ込んで、たくさん県外へ旅行に行きました。リフレッシュしながら何事にも臨んでいたのが、逆に良かったのかもって思いますね。
サークルとかには入っていませんでしたが、その代わりいろんなボランティア活動に参加していました。医療センターで入院中の子どもに本を読んだり、養護学校のプールのボランティアをしたり。実習で行った先でも、実習後に度々ボランティアの声かけをしてもらっていました。年末に友人たちと浴衣を持参し、四苦八苦しながら着て、利用者さんたちとお餅をついて丸めたのはいい思い出ですね。
―印象に残っていることはなんですか。
大学の授業を受けていくなかで、高齢者分野に進みたいと思うようになっていた頃、実習先の希望を出す機会がありました。私たちの学年では、実習先として高齢者施設が圧倒的に人気だったため、第3希望まで出すようにと言われ、第1、第2は高齢者施設、第3希望で今働いている“土佐希望の家”を記入しました。大体皆、第1、第2で決まることが多いなか、私はまさかの第3希望が通ってしまって。その時は驚きましたが、今となってはこれが良い決断だったと自負しています。
土佐希望の家では、職員と利用者の間に流れる空気感や、和気あいあいとした雰囲気がとても素敵で、実習が純粋に楽しかったんですよね。10カ所以上の実習先に行きましたが、これは他の実習先では感じなかった気持ちだったんです。ここの実習に行く前は、障がい者分野にはさほど興味がなく高齢者分野に、と思っていたはずでしたが、実習を終える頃にはすっかり気持ちが変わってしまっていて。それほどに土佐希望の家での関わりは、私にとって心地の良いものだったんだと思います。
Q3 ここに就職するまでの流れについて教えてください。
実習の楽しかった経験から“土佐希望の家”で働きたい!と思ったので、自分からアクションを起こし続けました。
 全ての実習を終える頃には、ここ“土佐希望の家”で働きたいなと思っていたので、ことあるごとにアクションをしていました。ちょうど一個上の先輩がここで身体障がいのある方へのボランティアをしているのを耳にしたので、私もしたいと思い、月に1回程度通わせてもらっていました。
全ての実習を終える頃には、ここ“土佐希望の家”で働きたいなと思っていたので、ことあるごとにアクションをしていました。ちょうど一個上の先輩がここで身体障がいのある方へのボランティアをしているのを耳にしたので、私もしたいと思い、月に1回程度通わせてもらっていました。
卒業論文では、重症心身障がいの子どもに携わる内容にしたい、と土佐希望の家で働く方々にインタビューもさせてもらったり、それこそ当時の部長さんに「ここで働きたいです!」って話してみたり。もちろんその時は緊張もしたし、恥ずかしい気持ちもありましたけど、この気持ちを我慢して、後悔するのは絶対嫌だったので、アクションを続けていた感じです。職員募集自体、毎年必ず出ていた訳ではなかったので、もし募集が出なかった場合はどうしようかと他の就職先も見ていました。ですが、幸いなことに支援員の募集が出たので、すぐに応募し無事、就職することが出来たという訳です。今思えば私の行動、すごかったですね(笑)
Q4 現在のお仕事について教えてください。
土佐希望の家で、障がいのある方へのケアを行っています。
2014年の春からずっと、ここ“土佐希望の家”で働いています。支援員の配置部署としては、重症心身障がいの方が多い1病棟と2病棟、身体障がいのある方の多い3病棟、そして在宅から利用者さんが通ってくる通所ケア、の4つの部署があります。私は入職して7年間3病棟に配属され、その後3年間通所ケアへ。2024年の春からは、また3病棟に戻ってきました。基本的にはどの部署も日々の利用者さんへのケアや関わりは変わりありませんが、一度通所に配属されたおかげで、今のケアにも磨きがかかったような気がしています。
通所では、朝晩と利用者さんの送迎があるため、必ず家族の方とお話しする機会があります。他の病棟では定期的に面会はあっても、通所のように必ず家族の方にお会いできるという訳ではないので、そこが大きな違いでした。病棟では見えなかった家族の悩みや背景、思いを直接知ることが出来ますし、良くも悪くもすぐに自分たちのケアへの反応が分かることは日々の励みにつながります。
通所に移ってすぐは、信頼関係も築けていないため、必要以上に話してくれなかったご家族が、毎日顔を合わせ、少しずつ打ち解けていくと、他愛のない話や普段聞けない話なども話してくれるようになりました。3年経って、信頼関係が築けてきたと手応えを感じてきたところの異動だったので、少し残念ではありましたが、より一層一つ一つのケアを、その人にとって良いものにしたいと心掛けるようになりました。利用者さんたちの安全が一番ですが、少しでも楽しい気持ちで日々を過ごせてもらえるように援助していきたいですね。
ふと昔の自分に触れて、大学に行ってよかったなと思うことがあります。
県立大や他の学校から実習生も来るので、実習日誌に目を通すことがあります。読む立場になって、改めて実家に残している自分のかつての提出物などに手を伸ばしてみたところ、当時の自分が意外にもしっかり書けていたことに驚いて、今はこんなに書けないかもな、なんて思っちゃって(笑)在学中、どの授業でも先生から「それはどうして?」という質問が多く、感想ではなく、考察をすることを心掛けて行動していました。大学ならではの「考えなさい」というスタンスのおかげで、考える癖がつきましたね。それにあの頃はディスカッションの授業も多く、私はそれが苦手でしたが、自分の意見を出し合って、みんなの意見を一つにまとめるという経験は、今まさに現場で生かされています。大学のおかげで、そういう力は身に付いていったんだなぁと、不意に思い返すことがありますね。
後輩のみんなにエール!
大学生の間は浅く広くいっぱい挑戦してみてほしい!
 すでにこの道に行きたい!って決めている子もなかにはいると思うけど、就職してしまったら他を見る機会は本当に少なくなるので、分野関係なくいろんなものを見てほしいです。ボランティアをするから偉い、とかじゃなくて、なんでも楽しむ感覚で一歩踏み出せたら、つながりもできるし、新しい発見もあるし。勉強だけでなく遊びも、時間のある学生のうちにいっぱい経験して、楽しんでください。気になる就職先には、私みたいに自分からどんどんアクションをかけるのもお勧めしますよ!
すでにこの道に行きたい!って決めている子もなかにはいると思うけど、就職してしまったら他を見る機会は本当に少なくなるので、分野関係なくいろんなものを見てほしいです。ボランティアをするから偉い、とかじゃなくて、なんでも楽しむ感覚で一歩踏み出せたら、つながりもできるし、新しい発見もあるし。勉強だけでなく遊びも、時間のある学生のうちにいっぱい経験して、楽しんでください。気になる就職先には、私みたいに自分からどんどんアクションをかけるのもお勧めしますよ!
障がいのある方に関わる分野は、大変なこともありますがやりがいはあるし、やっぱり純粋に楽しい分野かなと私は今でもそう感じています。土佐希望の家には、通所も、病棟もあって一つの施設でいろいろな経験ができるので、選択肢の一つとして考えてみてほしいですね。
※所属・職名等は掲載時点のものです。