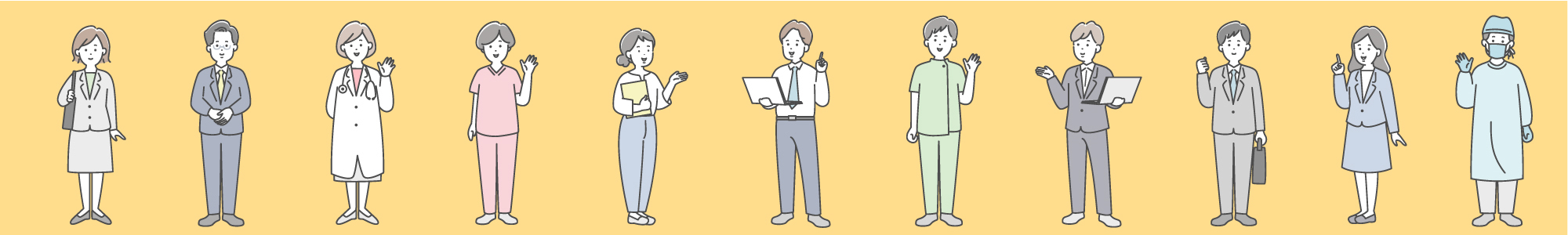本文
一つのことを皆でつくり上げた、あのかけがえのない経験。 今の自分につながった大学での課外活動。
自分が住んでいる高知のことを知りたいと選んだ大学進学。小笠原知美さんは、大学での活動を通し、地域づくりに興味を持ちました。一般企業に就職するも、忘れられなかった地域づくりの道へ。現在は津野町で、地域の方に寄り添う仕事をしています。

【Profile】
小笠原 知美 さん
津野町役場 まちづくり推進課 地域コーディネーター
2016年 高知県立大学文化学部文化学科卒業
Q1 本学に進学を決めた理由を教えてください。
自分が住んでいる高知県のことを深く知ろうと思い、参加したオープンキャンパスで、実際に学んでいる先輩たちに出会い、この大学に進学したいと思いました。
高知に生まれ、今まで出会ったたくさんの人たちに育ててもらったという感覚が高校生ながらにあったので、高知県が元気で在り続けていくことに携わっていけたらいいなという思いが心にはありました。「そのためには一体何をしたらいいんだろう」と進学を決める時期に、“高知県は課題先進県”という内容の新聞記事を見つけました。その時、自分の住む土地は実は危ないのかもしれない、と危機を感じたのを今でも覚えています。
まずは、高知県のことを深く学べる大学に行こうと思い、県内の大学を調べ、姉が通っていた県立大学のオープンキャンパスに参加。ただ漠然と、高知のことを学びたい!と言っていた私に対しても、先輩たちは皆、快く話を聞いてくれ、その姿はとても楽しそうでキラキラして見えました。こんな大学で高知について学べたらいいなと思ったのが、受験を決めた理由です。
Q2 どんな学生生活でしたか?
育ってきた環境の違ういろんな人たちが集まって、それぞれがやりたいことに向かって頑張っている輪に自分もいることがとても嬉しかったです。
大学には全国各地から学生が集まっているので、話す言葉は違うし、育ってきた環境も違えば、考え方も違っていて、「地域活性化」というテーマ一つでも、正反対のような意見も飛び交いました。ですが、どれも間違いじゃないということを先生は授業できちんと教えてくれて、そのことについて深掘って議論していく。高知で生まれ育った私にとって、今までの環境と180度違う大学での生活は、新鮮なことばかりでした。
元々私は人に伝えたり、人前で話したりすることがすごく苦手だったんですが、授業やゼミなど、いろんな場所で話す機会や場数をたくさん踏ませてもらって、高校時代と比べて性格も変わったように思います。今でももちろん緊張はしますが、自分の意見をはっきり言える先輩たちに出会い「あんな風に私もなりたい」そう思ったことが、今の自分に変わるきっかけだったと思います。
―印象に残っている学びはなんですか。
私が大学にいるときは、ゼミや一時期代表も務めていた“活輝創生実行委員会”※の活動などを通じて、地域に出て行くことは多かったです。一番思い出に残っているのは、佐川町尾川地区での活動のこと。それまで行ったことがなかった尾川地区へメンバーと実際に足を運び、地域の魅力探しとして、元々あった地域新聞を復活させたり、昔から住んでいる人に話を聞き、地区の歴史をまとめたりと、少しずつ活動を増やしていきました。なかでも一番力を入れたのが、“おがわ桜まつり”というイベントの立ち上げです。
※活輝創生実行委員会:2011年に発足した学生団体。実際に地域に足を運び、地域の方と一緒に、地域の活気づくりについて考える活動をしている。
尾川地区に流れる川沿いには、とても綺麗な桜並木があります。そこは地域の方が長年整備し守っていた場所でしたので、この地域の宝を活かしてもっと地区内外の方々がつながれるように祭りをしてはどうかと、学生から提案をしました。今思えば稚拙な企画書だったかもしれませんが、それを地域の方々が見てくれ、一緒にやってみようかと動き出してくれました。準備のために何度も尾川地区へ通い、地域の方と桜並木にぼんぼりをつけたり、ステージ企画を考えたり、地域の方と学生でアイデアを出し合いながら一から祭りをつくりあげました。
祭り当日は点灯式も行いました。皆でクラッカーを持って、3、2、1で、ぼんぼりに火を灯して。その光景を前に「いち学生でもこんなことができるんだ」と感極まって号泣したのも良い思い出です。今でも地域の方と親交は続いていて、当時の関係者や私たち卒業生が集まれる大事な場所になっています。


(写真)尾川地区の活動で地域の方へのヒアリングと、“おがわ桜まつり”点灯の様子。
Q3 なぜ、津野町で働くことを決めたのですか?
学生時代に地域づくりを経験したことが忘れられず、地域と近い仕事がしたいと津野町の地域おこし協力隊に志願しました。
 大学卒業後は、地域に近い場所で働きたいと思い、当時の求人の中で一番希望にあった調剤薬局に事務職として就職しました。
大学卒業後は、地域に近い場所で働きたいと思い、当時の求人の中で一番希望にあった調剤薬局に事務職として就職しました。
地域に密着した薬局でしたが、実際に働いてみると、事務職だとどうしてもできることの幅が狭く、自分のやりたいこととは違うような気がして、モヤモヤとした2年間を過ごしました。
自分がやりたかったことってなんだろう、と考えたときに、大学時代の活動が自分の中でとても大きかったことに気づかされましたね。いろんな人と関わって一つのことをやり遂げた実感や、仲間が一緒に動いてくれていた思い出がどうしても忘れられなかったんです。そんなことを思っていた矢先に、大学の先生から津野町の地域おこし協力隊の募集があることを教えてもらいました。当時は、津野町白石地区の集落活動センターが立ちあがろうとしていた時期で、そこに常駐して地域づくりに取り組む支援員を募集していました。実はこの白石地区は、大学時代の“活輝創生実行委員会”の活動で後輩が行っていた地域で、私も何度か足を運んだことがありました。白石地区の方々は長年にわたり、地域の人々のつながりを深めながら地域の元気づくりに取り組まれてきた地域です。地域を想う人々がいて、母校が関わっていて、後輩が活動を引き継いでいるこの地域なら、地域の方と考えながら一緒に地域づくりができるんじゃないかと思い、2018年から地域おこし協力隊として、白石地区の支援員に着任することになったんです。
Q4 現在のお仕事について教えてください。
津野町での地域おこし協力隊を経て、現在は地域の活気づくりをサポートする地域コーディネーターという仕事をしています。
地域おこし協力隊に着任してすぐに白石地区の集落活動センターができましたが、「集落活動センターってなに?」というくらい、地域の方も、私も分からなかったので、目の前のことに挑戦していく日々でしたね。元々大事にしていた閉校した学校を集落活動センターとして蘇らせたので、地域の人と掃除をすることから始め、地域の人が集まれるように簡単にコーヒーが飲める場所を作ったり、耕作放棄地を無くしていこうとお米を作って売ったり、地域外からも人に来てもらえるように体験プログラムを作ったりと様々なことに取り組みました。地域の課題ややりたいこと、思いを聞いて、それを負担が少なく、かつ実現できるように地域の方とともに形にしていきました。私は専門家ではありませんが、自分の視点で何ができるかを考えて挑戦していった日々でした。そのなかで、地域づくりと、課題に向き合った3年間の姿を見てくれていた方がいて、白石地区だけではなく、津野町内の活気づくりのための人材募集があり、4年間、津野町で“地域コーディネーター”として働いています。
人が集まって暮らしていける地域づくりをこれからも考えていきたいです。
今、津野町には3つの集落活動センターがありますが、センターのない地域もまだたくさんあります。そんな地域の活気づくりのために、日々地域に足を運び、地域の方のお話を聞き、そこで暮らす人々がどんな地域にしていきたいかを一緒に考え活動していく役割を担っています。
現在力を入れているのは、ある地区の地域文化を記録し魅力を伝えること。今まで受け継いできた地域文化や風景をできる限り今のままで後世へ残していきたいと想いを持っている人々がいます。津野町には学芸員さんもいるので、その方にも協力してもらい、手探り状態ではありますが、まずは一緒にやってみようと新しい挑戦を始めています。
いろんな背景、立場の人と関わることが多いので、それぞれの背景や生き方を知った上で話をしていくこと、寄り添うことは大学時代の体験が今に活きています。この地域でも尊敬する方や、大事な場所が出来たので、できる限り問題解決に携わっていけたらと思っています。
後輩のみんなにエール!
できることならもう一回大学に通いたいくらい楽しかった!
 大学での4年間を振り返ると、あの頃は何をするにも必死で、とにかくがむしゃらに取り組んでいましたが、あの頃の仲間と当時を思い出しながら「もう一回大学行きたいね!」なんていまだに盛り上がることがあります。もし今戻れるなら、もっと授業を受けて、もっと本を読んで、もっとできたことがたくさんあるかもなんて思ったり。
大学での4年間を振り返ると、あの頃は何をするにも必死で、とにかくがむしゃらに取り組んでいましたが、あの頃の仲間と当時を思い出しながら「もう一回大学行きたいね!」なんていまだに盛り上がることがあります。もし今戻れるなら、もっと授業を受けて、もっと本を読んで、もっとできたことがたくさんあるかもなんて思ったり。
大人になって出会った方と大学の話で盛り上がった時に「県立大学は寄り添ってくれる大学ながやね」なんて言われたことがあって、当たり前に感じていた大学の環境の良さに気付かされることもありました。あの頃はただ、高知のことを学びたい!と思って入学しましたが、尊敬できる先輩、同級生、後輩、親身になってくれる先生方に出会えて、県立大学を選んで本当によかったです!
在学生に伝えたいのは、今の自分で、飾らなくていいので、まずは一歩踏み出してチャレンジをしてほしいということ。応援してくださる方はたくさんいます。
※所属・職名等は掲載時点のものです。