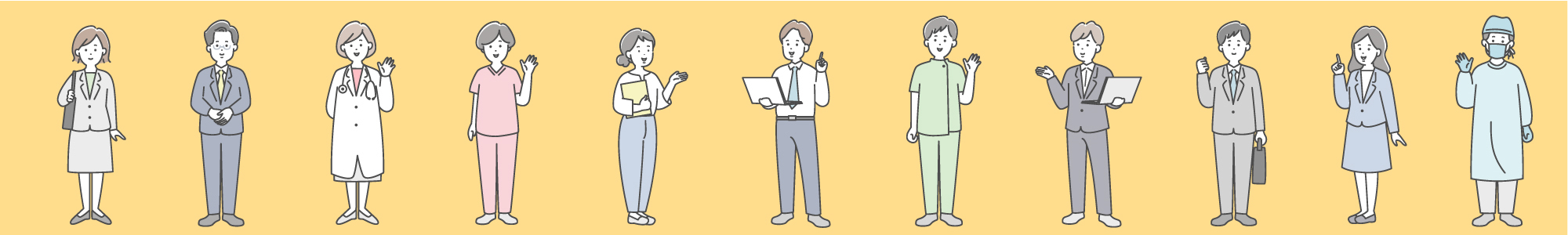本文
母国の社会問題に目を向け、仕事を辞めて日本へ留学。 “この人から学びたい!”恩師と出会い、さらなる高みへ。
李傑さんは、母国・中国で社会人として働くなか、中国の高齢化問題に直面。予測される未来を視野に入れ、福祉の知識を得るため日本への留学を決意。大学、大学院と進学し、現在は、博士号を取得すべく広島の大学院に所属しながら介護福祉士として最前線で働いています。

【Profile】
李 傑 さん
京都府 小規模多機能居宅介護事業所
2019年 高知県立大学社会福祉学部社会福祉学科卒業
2021年 高知県立大学人間生活学研究科博士前期課程修了
広島大学大学院医系科学研究科博士課程後期課程 在学中
Q1 本学に進学を決めた理由を教えてください。
中国の起こりうる未来を見据え、福祉の勉強をするために留学を決めました。
母国・中国で大学卒業後、上海で福祉とは関係のない分野で働いていました。社会人として働くなかで、中国も高齢化社会になりつつあることを日常的に感じることも多く、今後もっと高齢化社会に対するサービスが必要になるのではないか、と考えるように。そう遠くない社会問題を前に、高齢者福祉の最先端である日本の福祉を学ぼう!と、日本への留学を決めました。
外国人が留学をする場合、まず日本語学校に通わなければ大学に入学することができません。そのため、まず岡山の日本語学校に行き、日本語を学ぶことにしました。
福祉を学びたいと思い、日本各地の大学を調べましたが、高知県立大学が“社会福祉士”と“介護福祉士”のどちらの資格も取得でき、さらに精神保健福祉など関連する勉強も幅広くできることが私にとって大きな決め手となりました。
それに加えて、日本語を勉強しているときに日本のドラマや映画をたくさん観ましたが、そのなかでも「県庁おもてなし課」や「遅咲きのヒマワリ」といった高知が舞台の映像をみて、「高知っていいところだな」と印象がとても良かったことも、高知県立大学を選んだ理由の一つです。
Q2 どんな学生生活でしたか?
大学の勉強に日本語の勉強と、ハードな生活でしたが、単位もたくさん取れ、楽しい学生生活でした。
講義の予習復習に加えて日本語も、となると勉強することが盛りだくさんな生活でしたが、当時、外国からの学生は私だけでしたので、先生も友人も皆がとても優しくしてくれました。介護コースの学生は高知出身の方が多く、勉強だけでなく遊びにも、とにかく情熱がある方が多かったです。バスケ部にも所属していましたが、そこで出会った先輩方も優しく、車で県内各地、いろんなところに連れていってもらいましたね。
もちろん初めは、疎外感というものは多少なりともありました。ですが、徐々に日本の暮らしに慣れ、日本語で物事を考えるようになるにつれて、疎外感も薄まり、高知に所属しているという気持ちが芽生えてきましたし、周りの助けもあって大学院までの6年間、充実した生活を送ることができました。
―印象に残っていることはなんですか。
恩師である横井先生との出会いですね。
元々計画としては、4年間福祉を学び、その後は国に帰って仕事をするつもりでしたが、横井先生との出会いで考えが変わりました。私は1回生のときから、実習などを通して“認知症”について考えることが多く、文章も書いていたのですが、3回生の時に着任された横井先生が、初めての授業で言語哲学の視点から認知症の人の世界を理解するという講義を行いました。それを聞いた瞬間、「この先生からいろんなことを学びたい」と思ったのを今でも覚えています。それがきっかけにもなり、そのまま大学院に進学しました。
横井先生とのエピソードはたくさんあるのですが、なかでも覚えているのが、京都の学会発表に行った時のこと。横井先生と2人で京都に向かい、到着したその足で観光に向かってしまいました。大きなスーツケースと重い荷物を持ったまま嵐山まで電車に乗って、山道を登って。それを見た観光客の方に「すごいな」と声をかけられました(笑)
今思うとなんで?と思う笑い話ですが、先生と山道を歩きながら、考えを出し合って、すごくいい時間だったなと思います。今でもあの頃を振り返るたびに、先生への感謝の気持ちでいっぱいになります。


Q3 なぜ、今の道へ進もうと思ったのですか?
博士号を取得するため、働きながら大学院へ。
現場での経験が知見を広げてくれ、それがまた実際の仕事へのパワーになっています。
県立大の大学院修了後は、博士号を取得するために広島の大学院へ進学。研究のデータが必要だったので、博士課程1年目から認知症対応型のグループホームで2年半ほど働いていました。
その時は「これから研究者の道を歩んでいこうかな、あるいは学校の先生になろうかな」なんてぼんやり考えていましたが、今年の頭に縁あって、現在働いている京都の会社の社長に声をかけて頂き、そちらで介護福祉士として働いています。
大学での学び・実習を経て、広島で2年半、そして今は京都で、どちらも現場の最前線で働いていますが、幼少期から祖母に育てられたこともあって、高齢者の方々と関わるのは好きです。
現場で仕事をしているのがメインですが、全く研究などをしなくなった訳でもなく、時々論文を書いたりもします。元々私はいろんな哲学書や専門書を読む方で、昔は分からなかったことも、介護現場での経験を通して、なるほどな、と思うことが増えてきました。この感覚が、介護の仕事に対するエネルギーになっているかもしれませんね。
Q4 現在のお仕事について教えてください。
現場だけでなく、中国へ日本の福祉を伝えるパイプ役も担っています。
 現在は、デイサービスや訪問看護・訪問介護など小規模多機能居宅介護のサービスを行う京都の会社で働いています。最近、会社の事業が拡大して、新しい認知症グループホームが開設されました。私は管理者として仕事をしています。
現在は、デイサービスや訪問看護・訪問介護など小規模多機能居宅介護のサービスを行う京都の会社で働いています。最近、会社の事業が拡大して、新しい認知症グループホームが開設されました。私は管理者として仕事をしています。
この会社は中国との関わりもあり、日本式の介護のノウハウを中国の方々に伝えていたのが、入職を決めた大きな理由でもありました。今は自分がその役割を担っていて、出張として定期的に中国へ行き、中国の大学で講義をしたり、現場の担当者と話し合ったり、新しいビジネスの可能性を探ったりと、中国とのパイプ役になっています。元々、中国の起こりうる未来を考えて日本に学びに来た身として、今こうやって母国である中国との関係も築きつつ、仕事ができているのはとても感慨深く、県立大学での学びがあったからこそです。私が県立大学でいろんな学びができたように、県立大学の良さを中国の大学にも知ってもらえたらと思っています。文化の違いなどで現実的に難しい部分ももちろんありますが、“日本で福祉を学ぶ”という選択肢がもっと増えてほしいですね。
大学で学んだことは今の職場でも役立っています。
 今の職場には、高校卒業後すぐに就職した方、別の仕事から転職してきた方など、介護や福祉を学んだことがない方も数名在籍しています。介護士は、利用者一人ひとりにその人に合った介護プランを立てる必要がありますが、介護や福祉を学んでいないとプラン自体立てることができません。そんな方々に向けて、プランの立て方、考え方を教えてくれないかと管理者から依頼を頂き、会社内で研修を行うこともありました。県立大学で学んだ理論や知識、実習中に得た経験を活かしながら、実際に今関わっている利用者さんの介護プランを作り、それを使って講義をしました。その研修後からは、私の作った見本を見ながら、他の職員も介護プランを作ることができるようになりました。こんな風に、大学での学びを実感する瞬間は、今もたくさんあります。
今の職場には、高校卒業後すぐに就職した方、別の仕事から転職してきた方など、介護や福祉を学んだことがない方も数名在籍しています。介護士は、利用者一人ひとりにその人に合った介護プランを立てる必要がありますが、介護や福祉を学んでいないとプラン自体立てることができません。そんな方々に向けて、プランの立て方、考え方を教えてくれないかと管理者から依頼を頂き、会社内で研修を行うこともありました。県立大学で学んだ理論や知識、実習中に得た経験を活かしながら、実際に今関わっている利用者さんの介護プランを作り、それを使って講義をしました。その研修後からは、私の作った見本を見ながら、他の職員も介護プランを作ることができるようになりました。こんな風に、大学での学びを実感する瞬間は、今もたくさんあります。
後輩のみんなにエール!
本をたくさん読み、その上で考えて行動することを今も大切にしています。
横井先生が県立大学に着任されて、一番初めに挨拶で言った「とにかくいろんな本を読んで考えなさい」という言葉と、研究や仕事がうまくいかないときにかけてくれた「うまくいってないということが、すでにうまくいっている証拠」という言葉が、今もふいに頭をよぎることがあります。その素敵な言葉を、これから同じ道を目指すかもしれない方々に届けたいです。もちろん横井先生だけでなく、県立大学で出会った先生方には在学中、たくさん指導してもらったので、本当に感謝していて、中国に出張に行く前には高知に戻り、大学に近況報告を兼ねて挨拶に行くようにしています。親身になってくれた先生方や、大学で出会い今もなお交流の続いている友人たち、皆に出会わせてくれた県立大学の良さがもっと多くの人に伝わればいいなと思います!
※所属・職名等は掲載時点のものです。