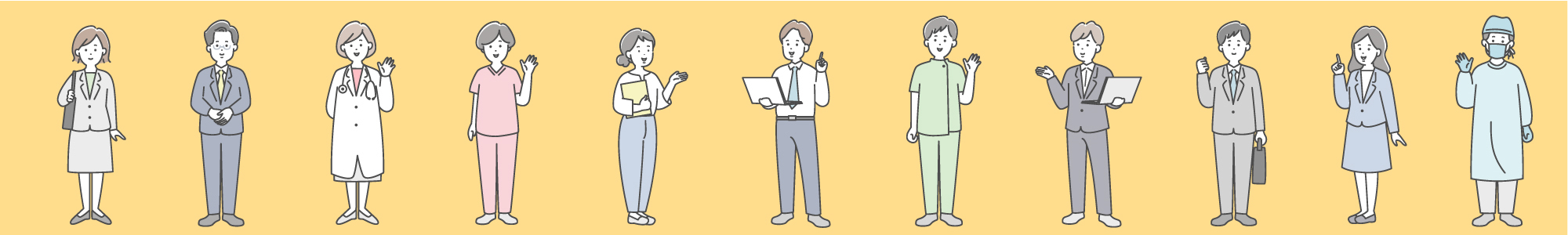本文
もっと学びたいと思える何かを探して 夜のキャンパスに通った日々。
森田吹生さんは、文化学部文化学科文化総合系で学びました。卒業後、選んだ職場が高知県立大学。現在、母校の職員として学生や地域と向き合う森田さんの歩みを聞きました。
【Profile】
森田 吹生 さん
高知県公立大学法人 高知県立大学 地域連携部企画調整課
2021年 高知県立大学文化学部文化学科卒業
Q1 本学に進学を決めた理由を教えてください。
自分の将来についてじっくり考える4年間にしたいと思いました。
高校生の時、大学でこれを学びたい、というものが決まっていませんでした。文化学部ならさまざまな分野を学べることが分かり、興味がわいて調べてみると、主に夕方から夜にかけて授業を受ける夜間主コースがあることを知りました。昼間、自由に時間が使えるので、将来について4年間かけて考えることができるし、しかも学費が安い!高校までは義務的な感じがあるのですが、大学はより学びたい人が進む場所。だったら自分で学費を払いたいと思い、夜間主ならばそれをかなえることができると考え、進学しました。
Q2 どんな学生生活でしたか?
昼はバイト、夜は講義で充実の毎日を送っていました。

―印象に残っている学びは何ですか。
地域学実習Ⅰで、大学で深く学びたいと思うテーマ、「防災」に出会うことができました。南海トラフ巨大地震の発生が予測される高知に生まれ、中学生の時には東日本大震災の被災映像に衝撃を受けたことから、防災に漠然と関心を寄せていました。それを講義で学ぶことができると知り、授業を担当していた大村先生(退職)のほかの講義も受け、4回生でゼミにも所属しました。ゼミでは防災士の資格取得を推奨していたので、同じく防災に興味があった母と受験し、2人そろって資格を取ることができました。
大村先生とは偶然、天体という共通の趣味もあり、いろいろな話をさせていただきました。講義の合間、永国寺キャンパスの広場で衛星の通過を一緒に眺めたのもいい思い出です。
Q3 なぜ、大学職員を目指そうと思ったのですか?
悩みに悩んだ就活で見えた、憧れの仕事が「大学職員」でした。
 就職活動では、本当に悩みました。地元高知で何か人の役に立てる仕事に就きたいと思っていたのですが、具体的に何をしたいのかは決まっていませんでした。迷って、悩んで、大村先生にも話を聞いていただいて…。そんな時、私の漠然とした悩みに対して、親身になってアドバイスしてくれたのが大学の学生・就職支援課(現在は教務・学生支援課)の方でした。こんな風に人を助け、支えることができる仕事もあるんだと気づき、大学職員が憧れの職業になったのです。調べたら高知県公立大学法人の職員採用募集が出ていたので、思い切って応募しました。
就職活動では、本当に悩みました。地元高知で何か人の役に立てる仕事に就きたいと思っていたのですが、具体的に何をしたいのかは決まっていませんでした。迷って、悩んで、大村先生にも話を聞いていただいて…。そんな時、私の漠然とした悩みに対して、親身になってアドバイスしてくれたのが大学の学生・就職支援課(現在は教務・学生支援課)の方でした。こんな風に人を助け、支えることができる仕事もあるんだと気づき、大学職員が憧れの職業になったのです。調べたら高知県公立大学法人の職員採用募集が出ていたので、思い切って応募しました。
Q4 現在のお仕事について教えてください。
大学職員として、今年で4年目。
「県民の健康長寿を促進すること」を目的に掲げ、教職協働で取り組んでいます。
入職して1年目は、学生・就職支援課で学生対応の窓口業務からスタートしました。奨学金やサークル活動の申請などを受け持ったのですが、自身にはそれらの経験がなく、私が目指していた大学職員のようなアドバイスがなかなかできない。自分の未熟さを痛感した1年でした。
一方で、看護学部、社会福祉学部、健康栄養学部の池3学部の雰囲気は文化学部とは違うので、とても新鮮でした。
2年目からは、健康長寿センター(現・健康長寿研究センター)で事務を担当し、今年で入職4年目です。健康長寿研究センターは、平成22年に池キャンパスに看護学部・社会福祉学部・健康栄養学部の3学部が集結したことをきっかけに「県民の健康長寿を促進すること」を目的に設置されました。県内の保健・医療・福祉などに関わる専門職者の知識と技術の向上のためのサポートや、県民の皆さんの健康に対する意識向上のための健康啓発活動に教職協働で取り組んでいます。健康長寿研究センター事業の1つでもある「健康長寿体験型セミナー」では地域包括支援センターや保健師さんが考える地域の健康課題からその地域に合ったセミナーを教職協働で企画・実施しています。毎年県内2~3ヶ所の市町村にお伺いし、これまでに県内34市町村のうち23市町村でセミナーを実施しました。
その他にも高知県から寄附や補助金を受け、県内の新卒・新任訪問看護師育成をおこなう「高知県中山間地域等訪問看護師育成講座」や高校生を対象に社会福祉のことを分かりやすく学んでいただく「高知県キャリア教育推進事業」などを担当しています。
さまざまな経験を通じて、学生時代は分からなかった大学の姿が見えてきました。
現在、職員として高校生から高齢者の方まで幅広い世代の人たちと関わらせていただいて、大学が学内だけでなく、広く地域社会とコミットしていることを実感しています。本当に大学は奥が深く、まだまだ私の知らない姿があると思うので、これからいろいろな課で経験を積んで、多くの視点から大学を見てみたいなと思っています。


後輩のみんなにエール!
学びたいこと・なりたいものに出会える高知県立大学
「何を学びたいかわからない、将来何をしたいかもわからない」と悩んでいた時に出会った文化学部の夜間主コース。周りの友達とは違い、夜間の時間帯に学ぶ夜間主コースに進学を決めたときは不安もたくさんありました。
しかし、文化学部での4年間を通して「防災」という深く学びたい学問分野や「大学職員」という憧れる職業を見つけることができました。
私と同じような悩みを抱えている方は、是非、文化学部夜間主コースを進路の選択肢のひとつとして考えてみてください。
※所属・職名等は掲載時点のものです。