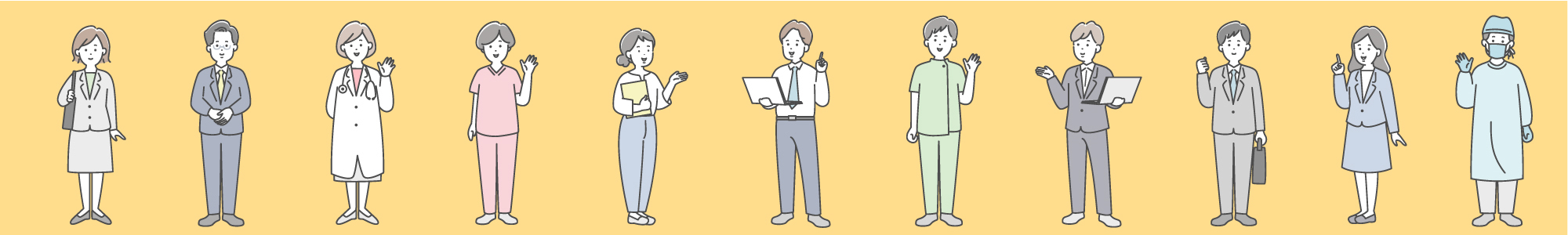本文
管理栄養士が役に立つには? あらゆる「食」への興味を突き進んで、今。
幼い頃から興味のあった「食」を学びに高知の大学へ。卒業後は、病院、企業、研究所などさまざまな場所で、管理栄養士の知識を活かした村井詩子さん。働きながら博士号を取得し、現在は縁あって母校・高知県立大学にて大学教員をしています。

【Profile】
村井 詩子 さん
高知県立大学 健康栄養学部 講師
2010年 高知女子大学生活科学部健康栄養学科卒業
Q1 本学に進学を決めた理由を教えてください。
幼い頃から興味のあった「食」について学びたいと思いました。
私の母は料理上手で、毎食料理を作るのはもちろん、誕生日やイベントごとに季節の料理やケーキも作ってくれていました。小さい頃からその姿を見ていたこともあってか、高校時代には家にあった料理の本を自ら開き、お菓子やパンを実験のように作って楽しんでいましたね。また、祖父母が、帰省の時に時々フレンチのレストランなどに連れて行ってくれ、食事マナーを学ばせてもらった経験もあります。家族のおかげで、幼い頃から「食」という分野に興味を持ち、将来はその道に進みたいと思うようになりました。親族が四国にいたこともあって、高知女子大学(現・高知県立大学)への進学を決めました。
Q2 どんな学生生活でしたか?
学内外関係なく、「食」についての知見を増やした4年間でした。
高知に来たのは大学生活が初めてでしたが、日曜市や市場がたくさんあって、地物の食材が手に入りやすいなと感じたのを覚えています。当時は、玄米や野菜を使った料理に興味を持ち、教室に通い、そこで知り合った方と一緒にお菓子を作って、販売したこともあります。当時は大学の授業だけでなく、学内外問わず興味のある「食」について学んでいましたね。
授業自体はカリキュラムも多かったですが、長期休みを使って姉たちのいる京都やドイツに行ったり、長野県のペンションへ住み込みのバイトに行ったり、学業だけでなく余暇もよく活動していましたよ。
―印象に残っている学びはなんですか。
授業のなかには、決まった栄養摂取基準の中で献立を考え、50人分ほどの大量調理を行い、食券を販売して実際に食べてもらうという実習がありました。原価は安く、かつ美味しく作ることを念頭に、それぞれグループに分かれて話し合い、試行錯誤していくのがとても面白かったです。栄養価的に使いたいものがあっても、原価の計算をすると、この時期にこの食材を使うと高すぎるなども出てくるので、折り合いをつけながら、お互いに試作品を作ってきて食べあって。実際に考えて作っても、あれ?こんなはずじゃなかったのに、なんて結果になることもありましたね(笑)他にも、実験では、バナナの香料や疑似いくらを作るなど、楽しく取り組んでいました。
あと、私が学生だった頃は、ひろめ市場がクリスマスにチャリティイベントを開催しており、健康栄養学部として参加したこともあります。その時はリーダーを任せてもらい、周りの協力をもらいながら、皆でツリー型のドーナツを作って、販売しました。衛生管理のことや原材料名の記載など、初めてのことを先生と相談しながら行ったのは良い経験で、今でも思い出に残っています。
Q3 卒業後はどのような道をたどりましたか?
興味のあることに挑戦する日々でしたね。
 大学の授業や実習で学ぶうちに、病気になってからではなく、なる前の状態、いわゆる“健康増進”という部分に興味を持つようになりました。卒業後、高知県内の病院に就職することに。当時は、各病院にN S T※が普及されてきた頃で、就職した病院でもそれを積極的に取り入れていくというタイミングで、病院へ研修などに行かせてもらいました。右も左もわからない1年目に、N S Tに関しては、覚えること、やらなければならないことが盛りだくさんでしたが、とても勉強になりました。
大学の授業や実習で学ぶうちに、病気になってからではなく、なる前の状態、いわゆる“健康増進”という部分に興味を持つようになりました。卒業後、高知県内の病院に就職することに。当時は、各病院にN S T※が普及されてきた頃で、就職した病院でもそれを積極的に取り入れていくというタイミングで、病院へ研修などに行かせてもらいました。右も左もわからない1年目に、N S Tに関しては、覚えること、やらなければならないことが盛りだくさんでしたが、とても勉強になりました。
※N S T(Nutrition Support Team):医師や看護師、薬剤師、管理栄養士、臨床検査技師、理学療法士、言語聴覚士、歯科医師、歯科衛生士など、さまざまな専門職が連携して患者さんの栄養管理を行う医療チームのこと
病院に勤めた後、兵庫県で“健康増進”に関わる会社へ就職。腎臓病や糖尿病の方への食品や健康増進のサプリメントを取り扱っている会社でしたが、依頼があれば病院へ栄養指導に行くこともあり、管理栄養士の資格を活かせる仕事でした。その後、結婚をきっかけに関東へ移住。移住した地域では、博士号を持って、地域で活躍している管理栄養士さんの存在を知りました。直接会いに行き話を聞かせてもらうと、“栄養士がもっと役に立つにはどうしたらいいか”を実践している方だったので、その方が立ち上げた会社で働かせてもらうことに。その間、大学院への進学を決め、働きながら大学院に通い、修士を取得。その後は縁に導かれるように、博士課程への進学、研究所で働くなど、研究者への道を進んでいました。興味のある方向に進み、気づいたら今こうなっていたという気持ちです(笑)結果、さまざまな分野に足を踏み入れ勉強したことで、栄養について多角的な視点が大事であることに気づき、また、いろんな世代の方とも関わりを持つことができました。
Q4 現在のお仕事について教えてください。
2024年4月から母校・県立大学で栄養学の教員をしています。
色々経験してきたなかで、何が自分にできるかを考え、その時ふと、教育という分野はどうかと感じました。そんな折に、大学教員について知る機会があり、教員という選択肢があることに気付かされました。私はこれまで、非常勤講師などで、疫学や栄養学について教える機会があり、教育の大変さも少なからず体験していました。元々興味がある人たちに伝えるのは簡単だけれど、そうではない人たちにはどうやって興味を持ってもらうかなど、授業を進める難しさも感じていました。この度、ご縁をいただき、2024年4月から大学教員として働いています。今は講義で教えている公衆栄養に対して、どうやったら興味を持ってもらえるか、分かりやすく伝えられるのかを模索する毎日ですね。
今自分がここにいるのは、県立大学のおかげです!
今年度は、学内の授業以外にも行政の新任栄養士さんなどに向けた研修会も行いました。また、以前働いていた職場でも研究員として在籍させていただいており、そちらでの活動も可能な限り続けたいと考えています。
今、私がここにいるのは、県立大学のおかげ。当時、健康栄養学科の学生は20人しかいなかったので、先生や同級生との関わりもとても密で、卒業後も連絡を取ったりできたからこそ、今につながっているのだと思っています。いろんなところで学びを深めてきていますが、一番初めにここで栄養について学べてよかったと思います。
後輩のみんなにエール!
私もまだまだやりたいことに挑戦していきます!
 学生さんたちの中には、管理栄養士や栄養に興味がないと悩む時期もあるようです。管理栄養士養成校なので、必要な科目を履修することは大事ですが、同級生との関わり、分からなければ先生に聞くなど、自分が楽しんで取り組めるかどうかで気持ちも変わっていくものだと思います。私がそうだったように、自分で探せば働く場所も見つけられるし、例え管理栄養士ではない仕事に就いたとしても、「食」というものは、私たちにとって切っても切り離せないもの。資格を持つことで選択肢も広がります。
学生さんたちの中には、管理栄養士や栄養に興味がないと悩む時期もあるようです。管理栄養士養成校なので、必要な科目を履修することは大事ですが、同級生との関わり、分からなければ先生に聞くなど、自分が楽しんで取り組めるかどうかで気持ちも変わっていくものだと思います。私がそうだったように、自分で探せば働く場所も見つけられるし、例え管理栄養士ではない仕事に就いたとしても、「食」というものは、私たちにとって切っても切り離せないもの。資格を持つことで選択肢も広がります。
私自身、今もやりたいことがあるので、大学生活にかかわらず、勉強も、遊びもなんでも進んで楽しみながら取り組むことが一番ですかね。
※所属・職名等は掲載時点のものです。