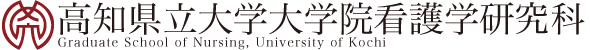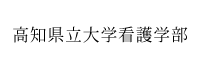本文
災害・国際看護学-研究コース [博士前期課程]
さまざまな分野に共通する課題を科学的に探究します
災害・国際看護学領域は、2012年に文部科学省の博士課程教育リーディングプログラムに採択された、災害看護グローバルリーダー養成プログラム(通称DNGL)の後継コースとして2021年度に看護学研究科に開設されました。
DNGLプログラム(2012-2019)は、兵庫県立大学、東京医科歯科大学、千葉大学、日本赤十字看護大学、そして本学の5大学からなるコンソーシアムによって実現した、日本の災害看護学教育を代表する大学院教育プログラムです。DNGLプログラムでは、人間の安全保障を基本理念とし、いかなる状況にあっても『その人らしく健康に生きる』ことができる社会の実現に向けて、学際的、グローバルな視点から災害看護学の発展に貢献できる能力を有し、災害看護学を教育できる人材を育成すること、を教育目標としていました。
新しい課程でもこの方針は変わりません。幅広い視野をもち、学際的、グローバルに災害看護学、国際看護学の発展のために貢献できる人材の育成を目指しています。災害も国際的な健康問題も人や時間を選ばずに起こるものばかりです。したがって、災害看護学も国際看護学も、小児や母性、急性期など、看護のすべての領域に共通する分野横断的な課題を探究します。
修了生の活躍
修了生は、国際協力、災害救援、看護教育など、各分野の基幹組織に進み、本学での学びを生かして活躍中です。
受験生の皆様へ
看護の実務経験を、災害または国際的な側面で科学的に探究する意志のある方、研究成果を現場で生かしたいと思っている方にとって、最適な分野といえます。
本課程では看護学研究科が提供する規定科目の他に、DNGLコンソーシアムが提供する災害看護学に関する科目も受講できます。所定の単位を取得することによって、博士後期課程修了時は、博士(看護学)の学位に「Disaster Nursing Global Leader」が付記されます。
また、社会のニーズに対応して、感染症看護、人道支援看護などの特徴的なセミナーも開講されており、希望者は国際保健医療をテーマに研究を行うことも可能です。
DNGLは5年一貫の博士課程のみでしたが、本課程は博士前期課程、後期課程の二区分に分かれており、前期課程修了後、ライフサイクルに合わせて後期課程への進学を遅らせることが可能です。
研究テーマ
・災害時の健康状態把握および情報活用に関するイノベーションおよび研究
・避難生活の環境評価・医療ケア提供に関する研究
・地域での感染症ケアに関する研究
・移民・難民・避難民の健康に関する研究
・グローバル・ウェルネスに関する研究
災害・国際看護学に関するお問い合わせは、下記へご連絡ください。
高知県立大学大学院看護学研究科博士前期課程
災害・国際看護学 教授 木下 真里
〒781-8515 高知県高知市池2751-1
Tel:088-847-8762
e-mail:kinoshita@cc.u-kochi.ac.jp